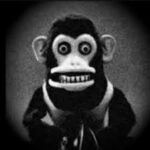🧠嗅ぐとは?
「嗅ぐ」は、2ちゃんねるのオカルト板に投稿された実話風怪談、いわゆる“洒落怖(しゃれこわ)”の中でも異彩を放つ短編怪談である。
タイトルの通り、本作では「霊が見える男」と「霊が嗅げる男」が登場し、幽霊の出没する社員寮での一夜を描いている。
話の主人公は霊感を持つ“見える人”。彼は、幽霊に悩まされる会社の同僚・Tさんを助けるため、霊を“嗅ぎ分ける”特異な能力を持つZと共にTの部屋を訪れる。
Zは目視できないが、霊の種類をニオイで判別できるという特異体質を持っており、その嗅覚描写がリアルかつユーモラスで読者の印象に残る。
物語は、Zが発する嗅覚に基づく霊への辛辣なコメントで恐怖の対象だった幽霊を撃退し、結果的にTさんの安眠を取り戻すという展開で幕を閉じる。
一見ギャグのようでありながら、独特なオカルト的リアリティを持ち、「嗅覚による霊的対処」という斬新な切り口が魅力だ。
📖 嗅ぐあらすじ
バイト先の社員寮で、幽霊騒ぎが頻発していた。特に被害に遭っていたのはTさんの部屋。Tさんの様子が日に日におかしくなっていたため、霊感のある「俺」と、霊のニオイを嗅ぎ分けられる特異体質を持つ友人Z(通称:カオル)が、Tさんの部屋に様子を見に行く。
部屋に入った途端、「俺」は何かの気配を感じ、不安を覚える。一方Zは特に感じるものはないと言うが、夜になると怪異が起きる。
「俺」の上に、小さな頭の女の霊が現れ、胸に正座してくる。金縛りのように動けない中、Zが起き出し、ニオイで幽霊の位置を特定し始める。そして、幽霊のニオイを「小動物系」「ペットショップ」「水槽の底に溜まったエサの臭い」と言って分析し出すと、霊はショックを受けたのか、すぐに消えてしまった。
以来、Tさんの部屋では霊現象が起きなくなり、寮の人々はZのことを「カオルさん」と敬意を込めて呼ぶようになった。
212 :本当にあった怖い名無し:2010/03/13(土) 01:15:22 ID:9DpGI0OI0
バイト先の会社の寮で、幽霊騒ぎがあった。
俺は入社して1年も経たないのでよく知らなかったが、以前から気味の悪い事が起こっていたらしい。
寮に入っている社員のTさんの部屋が、特に出現率が高いそうで、俺に相談してきた。
T「この前もさ、顔洗って鏡を見たら、俺の後ろに怖い女が映ってたんだよ。
ウワッと思って振り向いたら、まだ居るんだよ…せめて振り向いたら居なくなってほしい…」
Tさんは精神的にカナリまいっているようだ。
俺は子供の頃から霊感が強く、いわゆる『見える人』だが、だからと言って霊をどうこう出来るわけではない。
しかし、仕事中もずっとウツロな目をしているTさんを放っておくのも酷だ。
俺は同時期に入ったバイトのZを誘って、寮に行くことにした。
Zは子供の頃から霊嗅覚が強く、いわゆる『嗅げる人』だ。
それが何を意味するのか、寮での実践を報告する。213 :本当にあった怖い名無し:2010/03/13(土) 01:16:22 ID:9DpGI0OI0
俺たちが行くと、Tさんはよほど一人が心細かったのか、わざわざ外まで出迎えてくれた。
けど俺は寮を見た時から、なんとなくイヤな感覚に襲われていた。
夜中にパトカーの回転灯が集まっている場所を見るような、いやな感じだ。
…ふと、窓の1つに目をやると、閉じたカーテンが不自然にめくれ上がり、
そこから妙に小さな顔っぽいのが、こっちを見ている気がした。
俺にはそれが、『近づくな』の警告だと思えた。
でも、極力明るく振舞うTさんに気を使って、言えずに見られるがまま。
俺「えー…と、どうだ、Z。何か感じないか?」
Z「ん…いや、特に無いな。まあ上がらせて貰おうか」
T「おう、酒も用意しといたぜ。さ、さ、入れよ、な?」
ハッキリ言って俺は、今日はやめておこう気分になっていたが、下戸のTさんに酒を用意されては退路が失われた。214 :本当にあった怖い名無し:2010/03/13(土) 01:17:09 ID:9DpGI0OI0
Tさんの部屋に近づくほど、イヤな感覚が増す。
案の定、さっきのめくれカーテンの部屋だった。
飲んでも気分が盛り上がるハズもないが、度胸付けの気持で飲む。
さりげなくカーテンを直しておいた。
Tさんによると、夜寝ている時が一番怖いのだと言う。
最近はマトモに眠れなかったそうだ。
今日は人が居ることに安心したのか、飲んでも無いのにウトウトとしている。
俺「布団で寝たらいいですよTさん」
T「ん、ああ、スマンな…」
Z「明日も仕事だし、俺らも寝るか」
この部屋ではとても眠れるような気分ではないが、俺とZも毛布を借りて寝ることに。
なんとなくカーテン側はイヤだったので、離れてソファーに横になった。
俺の様子が変だったのか、Zが小声で聞いてきた。
「なあ…何か見たのか?」
俺も小声で返す。
「ああ、ここに入る前に気味悪いのを…Zは?」
「特に無いって。俺は見れないもん、嗅げるだけ」
「…何度聞いてもわかんねーよソレ…あの、さ、幽霊ってどんなニオイなの?」
「…それぞれだな、モノによるよ。一つ言えるのは、人間のニオイじゃないって事かな」
それは少しわかる。俺も霊は人間には見えないから。215 :本当にあった怖い名無し:2010/03/13(土) 01:17:50 ID:9DpGI0OI0
…いつの間にか電気が消えている。どうやら寝ていた?そんな気はなかったが…
体の向きを変えようとして、奇妙な音に気づく。
ペタペタッ、ペタペタッと、低いところから聞こえてくる。
…床に手をつける音…?何かが床を這い歩いて…
そう判断している最中に、ペタペタのリズムが早くなり、体が強烈に重くなった。
金縛りとは違う、目を開けるにも全力を使うような状態…
俺が見たのは、正座で俺の胸の上に乗る女だった。
昔のアイドルが着るような黄色の派手な服だが、体は普通だ。
頭が野球ボールほどしかなく、頭蓋骨を抜いて干しあげたような質感をしている。
結果、やはり人間には見えない!
「…Z…お…い…Z」
声を絞り出す俺に、人間外女の顔が近づく…Z!気づいてくれ!
「ん…なんだ、どうし…あ、くせーな、居るなコレ、クンクン…」
ニオいながらこっちに近づいて来るZ。見えないは無敵。
Z「クンクン…この辺からだな…クン…え?なに、オマエの上に居んの?
うっわマジにか…クンクン…あ、コレはね、なんつーんだ、ペット売り場系のニオイだな…小動物。
あんまりたいした霊じゃないのかも…
クンク…ぇひっ!な、何だ、ひょっとしてこの辺アタマじゃね?
人外の部分は臭ぇーんだ、コイツ相当ブサイクだろ?
クン…ゴフォッ!なんだろ、ハムスターとかじゃねえぞ、亀の食い残したエサが水槽の底に溜まっ」
「あ、もういいよ、居なくなったから」
Zがニオイ分析~表現のあたりで、大抵の霊は消える。(女性霊は早く消える傾向がある)
幽霊にとってニオイを嗅がれるのは余程ショックなのか、2度と出て来ないらしい。翌日、久しぶりに熟睡できたというTさんが、職場でこの話を披露した。
もともと冗談が好きなTさんの話に、ほとんどの人は半信半疑だが、
寮の人は感謝と畏敬を込めてか、Zを下の名前『カオル』と呼ぶようになった。
📚出典と派生・類似伝承
出典:
- 初出投稿日時:2010年3月13日
- 投稿元:2ちゃんねる オカルト板「死ぬほど洒落にならない怖い話を集めてみない?」スレッド
類似・派生伝承:
本作のように「嗅覚」が超常的能力として描かれる事例は、民間伝承や怪異譚にはあまり多くない。しかし、以下のような関連概念が存在する。
- 犬神憑き・狐憑き:動物霊を扱う伝承において、「特有のニオイがする」と語られることがある。
- 「鼻が利く巫女」伝承:一部の地域では、神憑りや霊を“匂いで感じ取る”ことができる巫女の話が存在する。
- クトゥルフ神話の「黄衣の王」:怪異の存在が“臭い”として描写されるケースも見られる。
また、漫画や小説においても“異能としての嗅覚”は時折用いられる設定であり、嗅覚による恐怖認知や空間認識を題材とした作品と相通じるテーマである。
🎬メディア登場・現代への影響
現在まで「嗅ぐ」が明確にドラマ化・映像化された例は確認されていないが、以下のような関連メディアと親和性が高いと考えられる。
Web動画・朗読文化:YouTubeなどで朗読・演出された「洒落怖」作品として、読み上げ動画が一定の人気を博しており、「嗅ぐ」も朗読系配信者の間で取り上げられている。
『世にも奇妙な物語』シリーズ(フジテレビ):オチに風刺やユーモアを含んだホラー短編が特徴で、「嗅ぐ」のような異能系オカルトは類似傾向にある。
『ほんとにあった怖い話』:実話風の短編ホラー再現ドラマで、「見える人」「感じる人」の視点は共通点がある。
🔍考察と文化的背景
「嗅ぐ」の最大の特徴は、“幽霊を嗅覚で感知する”という特異な能力にある。
古来より人間は、“見えないモノ”を五感の一部で感じ取ることで超自然的存在を理解してきた。
その中でも「嗅覚」は比較的軽視されがちだが、動物的本能に根差す感覚であり、理屈ではなく本能的な“違和感”の象徴として機能する。
作中のZが放つ“臭いの分析”は、霊を一種の物質的存在と捉える試みとも解釈できる。
また、霊に対して「臭い」と評する行為は、神聖化や恐怖の対象であった霊を人間的に貶める行為でもあり、ユーモアと現代的懐疑主義が融合した描写と言える。
このようなアプローチは、ポストモダン的怪談の文脈――すなわち“恐怖の相対化”の手法として興味深い。
🗺️出現地点
物語内では具体的な地域名は明示されていないが、「会社の寮」という現代的・無機質な空間が舞台である点が重要である。
このような日常的空間に現れる“異物としての霊”という構図は、都市伝説系ホラーの特徴と一致する。
また、物語内に出てくる描写(狭い寮、カーテン越しの視線、深夜の静けさ)は、日本の団地・社宅文化に根ざした閉鎖的空間の恐怖を強調している。
📎関連リンク・参考資料
- 💀 嗅ぐ
- 🔊 YouTube朗読動画
💬編集者コメント・考察
「嗅ぐ」は、現代怪談として非常に完成度の高い短編である。
霊が“見える”ことを特別視しがちなホラー表現において、「嗅げる」という新しい異能の切り口は、読者に鮮烈な印象を残す。
とくに、Zの鼻による“霊のニオイの分析”というくだりは、恐怖と笑いを絶妙に交錯させており、ホラー×ギャグのバランスとしても秀逸だ。
また、「ニオイによって存在を暴かれることが霊にとって屈辱」という解釈は、単なる怪談にとどまらず、“見えないものを暴くことの暴力性”という哲学的なテーマを孕んでいるとも言える。
洒落怖初心者から玄人まで、強く推薦できる名作である。
🎧 都市伝説好き必見!“聴く怖い話”体験を始めよう【Audible / audiobook.jp 比較】
👣 この記事を読んで、背筋がゾワッとしたあなたへ。
もし“読む”だけでなく、“耳で聴く”怪談体験に興味があるなら――
オーディオブックサービスの【Audible】と【audiobook.jp】が、あなたをさらなる恐怖の世界へ案内してくれる。
イヤホン越しに囁かれる怨念、静寂の中で始まる恐怖体験。
一度聴いたら眠れなくなるかもしれない、人気の怪談朗読が多数ラインナップされている。
- 🔊 Audible(オーディブル)
Amazon提供。毎月1冊無料で、声優や芸人による怪談朗読をフルで聴ける。
『新耳袋』シリーズや、怪談師・ありがとうぁみ氏の朗読なども人気。
- 📚 audiobook.jp
日本発のオーディオブックサービス。月額で怪談やホラー作品が聴き放題。深夜に“連続再生”でじっくり楽しめる。
- 🎁 どちらも無料体験が可能。
まずは1本、深夜にイヤホンで試してみてほしい。文字では味わえない恐怖が、あなたの耳に忍び寄りよる。
🔥 話題の2大オーディオブックで聴ける《怪談・怖い話》作品
- 🔊 Audible(オーディブル):Amazon提供、1冊まるごと“無料”で試せる。プロ声優や芸能人による本格怪談朗読が魅力。
- 📚 audiobook.jp:月額プランで怪談やホラー作品が聴き放題。深夜にじっくり聴く“連続再生”が人気。
| タイトル | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 👻 新耳袋シリーズ | ✅ | ✅ |
| 🧟♂️ 稲川淳二 怪談ナイト | ✅ | ✅ |
| 🏚 事故物件怪談 恐音 | ✅ | ✅ |
| 🏞 廃墟・廃線にまつわる話 | ✅(一部) | ✅(一部) |
| 😨 実話怪談集 | 豊富 | 豊富 |
👇こんな人におすすめ!
- ✅ Audibleは…月1冊じっくり聴きたい人向け
- ✅ audiobook.jpは…いろんな怪談を聴き放題で楽しみたい人向け
🎧 どっちがいい?かんたん比較表
| 比較項目 | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 月額 | ¥1,500(1冊無料+聴き放題対象多数) | ¥1,330〜(聴き放題プラン) |
| 無料体験 | 30日間 | 14日間 |
| 怖い話の充実度 | ◎(稲川淳二/新耳袋ほか) | ◎(人気作+独自配信もあり) |
| アプリ使いやすさ | ○ | ◎(日本語対応に強い) |
| 配信ジャンル | 海外含め多彩 | 国内作品に強い |
🧟♂️ 聴くだけで“現地にいるような”恐怖体験
あなたは、ひとりでこの朗読を最後まで聴ける自信はあるだろうか?
「イヤホン越しに耳元で囁くような声がして、思わず音量を下げた…」
そんなレビューも少なくない、リアルな恐怖がここにある。
- ✅ 急に部屋が寒くなった気がする
- ✅ 背後に気配を感じた
- ✅ イヤホン越しに“もう一人”の声が聞こえる…
そんな体験を、ぜひ以下のリンクから始めてほしい。
🔽 無料で怪談体験を始めるならこちらから
👇どちらも無料で今すぐ試せるので、気になる作品を1本、まずは深夜に“イヤホンで”聴いてみてほしい――恐怖の臨場感がまるで違う。
\ 30日間無料体験キャンペーン実施中/
※Audibleは無料期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
\ 14日間無料体験キャンペーン実施中/
※audiobookは無料聴き放題プランの期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
👇こちらの記事も要チェック!
【もっと読む】↓