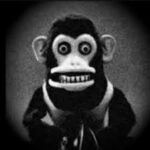🧠忌箱とは?
「忌箱(きばこ)」とは、インターネットのオカルト掲示板「2ちゃんねる」発祥の怪談・洒落怖(しゃれこわ)系都市伝説のひとつである。
物語の主人公は高校生。彼らが溜まり場としていた廃神社に、ある日突然、謎の老婆が現れ、古びた鞄を置いていったことからすべてが始まる。
鞄の中には、「開けてはならない」雰囲気を放つ木箱と、お札、古文書、不可解な紙幣などが詰め込まれていた。
興味本位でその箱を開けようとした友人たちは次第に様子がおかしくなり、錯乱、発狂、そして異常行動を見せ始める。
最後には「開けてしまった者」だけでなく、「見てしまった者」までもが巻き込まれる、
"触れてはいけないもの"の恐怖と代償を描いた物語である。
📖忌箱(きばこ)あらすじ
舞台は地方の田舎町。
夏休みを迎えた高校生たち数人が、よく集まっていた廃神社でいつものように時間を過ごしていた。
ある日、見知らぬ不気味な老婆が現れ、彼らに向かって古びた黒い革鞄を手渡してくる。老婆はほとんど言葉を発さないまま立ち去り、鞄だけが神社に残される。
興味を持った彼らは、その中身を確認することにする。
鞄の中には、和紙に包まれた木箱、意味不明な文字が書かれた古文書、汚れた紙幣、そしてお札が貼られた封印されたような物が入っていた。
その異様な雰囲気に戸惑いながらも、一人が箱に触れてしまう。
その日を境に、彼らの周囲で奇妙な出来事が立て続けに起こるようになる。
触れた者は高熱を出し、錯乱し、恐怖におびえるようになり、やがて異常な言動を繰り返すようになる。
他の仲間たちも次第に影響を受けはじめ、精神に異常をきたす者、行方不明になる者、死亡する者さえ現れる。
「箱を開けてしまった」「見てしまった」「そばにいただけ」の者まで呪いの影響を受けており、
封印されていた「何か」が解放されたのだと、投稿者(語り手)は悟る。
投稿者自身も不調を感じながら、かろうじて生き延びてこの体験談を残しているが、
最後に「今でも自分が呪われていないとは言い切れない」と記して終わる。
原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2010/01/16 21:15
これは高校3年の時の話。
俺の住んでた地方は田舎で、遊び場がなかったんで、近所の廃神社が遊び場というか溜まり場になってたんだよね。
そこへはいつも多い時は7人、少ない時は3人くらいで集まって、
煙草を吸ったり酒飲んだり、たまにギター持って唄ったりしてた。
その廃神社は人がまったく来ないし、民家や商店がある場所からはけっこう離れていたから、
高校生の俺達にはもってこいの溜まり場だった。ある日学校が終わって、まあその日も自然と廃神社に溜るかぁみたいな流れで、
俺と他の3人の計4人で自転車で廃神社に行ったんだ。
時間は4時過ぎくらい。そこで煙草吸ったりジュース飲んでたりしてた。
11月頃で、ちょっと寒いなぁなんて言いながらくだらない話に花を咲かせて溜ってたんだよね。
そしたら、ザッザッザッザッって神社の入り口から足音が聞こえてきたんだ。
最初は他の連れが溜まりに来たのかなぁと思ってたんだけど、
神社の境内に入ってきたのは、70代位のおばあさんだった。
俺を含めた4人とも会話がピタッと止まってね。
その廃神社に溜まり始めたのが高校1年の頃からで、約2年間溜まり場にしてたけど、
これまで一度も人が来た事がなかったんで、ビックリしたというか、人が来る事自体が意外だったんだよね。
俺たちは神社内の端側にある段差のある場所に溜まってたんで、おばあさんは俺たちの存在に気づいてない。
俺や俺以外の連れも、なんとなくバレたらいけない気がしてたのか、みんな黙ったままジッとおばあさんを見てた。
おばあさんは神社の賽銭箱(賽銭箱には落ち葉やゴミしかないのは2年前にリーサチ済みです)の前に立って拝んでた。
拝んでた時に聞き慣れない言葉で何かを呟いてた。
1分くらい拝んだあとに、賽銭箱の後ろのほうに片手に持っていた鞄を置いて帰っていった。
「おぉビックリした!」
「まさか人が来るとはww」
「ちょっと怖かった~」
とか話してたんだけど、当然気になるのは、おばあさんが放置した鞄。
俺はなんとなく嫌な予感がしてたんだけど、連れのAが賽銭箱のとこまで走って鞄を持ってきた。
「札束が入ってたりしてw」とか言ってるんだけど、
俺はわざわざ神社に置き去ったものだからロクでもないモンなんだろうなぁと思って、
「そんなもんあそこに置いとけよぉ~」とか言ったんだけど、他の3人は興味しんしん。
仕方なくA達が鞄を開けるのを見てた。
「なんだコレ」と言うBの手には古新聞。
相当古そうなのは新聞の黄ばみ方で分かったんだけど、
記事はよく覚えてないけど『なんたら座礁』『○○が逮捕』みたいな文字が書いてあったのは覚えてる。
新聞の日付は1972年って書いてあった。
「なんで24年前の新聞が…」ってみんな不思議がってた。
Cもちょっと気持ち悪くなったのか「やめとくか?」と言い始めたんだけど、AとBは更にガサゴソと鞄を物色しはじめた。
今度は財布。Aは「おぉ金入ってたら○○ストアで酒買って宴会するかw」と言いながら財布を開けた。
見た事もない札が一枚(昔のお札じゃなくて外国の札?)と、お守りとレシートと紙切れが入ってた。
AとBはすぐに興味なくして「なんだよ~金入ってねぇよ」と言ったんだけど、
俺は中身に興味があったんでCと一緒に見てみた。
お札はたぶん中国か韓国のかなり昔の札。レシートはボロボロでよく読めない。
お守りには梵字みたいな、たぶん梵字ではないけど、中国語か韓国語で書かれたお守りかなぁって感じの物。
俺とCが財布をくまなく調べてると、Aが中から小さな木製の箱を取り出した。
「なんだよコレ!お宝っぽくないか!?」と言って、Aは開けようとするんだけど開かない。
俺は「やめとけよ。どうせロクなもん入ってないって」って止めて、Cも「気持ち悪くなってきた…」って言うのに、
AとBは必死に開けようとしてる。
最初はコイツら馬鹿だなぁwって思ってたんだけど、
AとBはその箱を地面に叩きつけたり、二人が引っ張り合いをし始めたりして、
開けようとする行為がだんだん激しくなり始めた。
「ちくしょぉぉ開けよコノヤロ~」
「なんで開かないんだよぉぉぉ」
AとBはそう叫びながら必死に木箱を開けようとしてるんだけど、その姿が尋常じゃないって感じになってきて、
俺もCも唖然として見てた。
力づくで止めさせようとも思えないくらい、目が血走ってて必死なんだよ。
「お、落ち着けよ」と言ったんだけど、AとBには俺やCの存在すら目に入ってないみたいな感じで、
木箱をガンガン地面に叩きつけたり踏んづけたり、引っ張り合いしてる。
ヤバイなコレと思ってさすがに止めに入ったんだけど、
Aはガグガッと口からわけのわかんない声というか音を出して俺を突き飛ばした。
俺とCだけじゃどうしようもないから、他の連れを呼ぼうにも当時まだ誰も携帯電話を持ってなかったから、
誰かを呼ぶにもその場を立ち去らないといけない。
俺もCも一人になりたくないけど、仕方ないからCとジャンケンして俺が勝って、俺が他の連れ達を呼んで来る事になった。
もう五時過ぎくらいで、少しずつ夕陽が落ちかけて暗くなり始めたんで、
Aたちの行動とか周りの雰囲気がすごく気味悪く感じた。
2年間溜まり場にしてた場所がまるで別の空間に思えたんだよね。
AとBがコンビプレーしながら木箱を必死に開けようとしてる異常な姿を見ながら、「じゃすぐ戻る!」と走り去る俺に、
「頼むから早めに帰ってきてくれよ~」とCは泣きそうな感じで返事した。
神社の階段をダッシュで降りて、自転車を置いてる場所まで走って、自転車に跨いで走り出そうとした時にギョッとした。
さっきのおばあさんが、神社の向かい側の道でニタニタ笑ってた。俺の方じゃなく神社方向を見て笑ってた。
俺は神社に戻るわけにもいかず、おばあさんに話かけようなんて事も怖くて出来ず、
必死に自転車をこいで、神社から一番近いDの家に向かった。家から出てきたDは最初「は?なにそれw」と言っていたが、
俺が必死に説明してたらようやくヤバイ状況に気づいたみたいで、
「早く行こう!いや、Eも呼ぼう」とDの自宅からEに電話して、「早く家に来てくれ」と頼んでEの到着を待ってたんだけど、
Eは20分以上待っても来ないし、外がかなり暗くなり始めた事に焦って、
Dの弟にEが来たら神社に来るように伝言を頼んで、俺とDだけで神社に戻る事にした。二人で自転車こいで、神社に到着した時は、さっきいた場所におばあさんはいなかった。
俺とDは神社の階段を駆け上がった。以上、記憶はここまで。
次の瞬間俺は病院にいた。
エッと思って起き上がろうとしても起きあがれない。
一生懸命起き上がろうとしたら、足にギプスがはめてあって、腕には手首に包帯。
急に全身に鈍い痛みが走って、「うぉぉ」って小さい声が自然に出て、寝たまま苦しんでたら、
しばらくして病室に看護婦か入ってきて、
そこからもよく覚えてないけど、とりあえず家族が来たり先生が来たりして慌ただしい感じになった。
どうやら交通事故に遭って、4日間目を覚まさなかったらしい。
「Aは?Bは?神社は?Dは?」とまくしたてて聞く俺に、
母さんは最初は「今はいいの。今はゆっくり休みなさい」とか言ってはぐらかしてたんだけど、
何度もしつこく聞いたら、「A君もB君も亡くなって…D君は重体で…」と言われた。
意味が分からずポカーンとしていると、
ABD俺の4人が自転車に乗って歩道を帰っていたら、トラックが突っ込んできて、AとBは即死。Dは意識不明の重体。
(後日、図書館で地元新聞読んだらたしかにそう書いてあった)
駆けつけた担任の先生はボロボロ泣きながら「よかったなぁよかったなぁ」って言ってくれてるんだけど、
「おかしい…俺は神社に向かってたんだけど。AとBは箱を開けようとしてて、Dに助けを呼んで神社に行ったんだけど」
と説明した。
支離滅裂だったのか、親や先生は理解してくれなかった。
その日の夜は寝たり起きたりを繰り返しながら、
連れが死んだショックより(もちろん悲しかったけど)「おかしい…」という感情が強かった。翌朝一番でCとEが見舞いにきた。
Cは泣きながら「すまん!俺、30分待ってもお前が帰って来ないから、AとBを置いて逃げた」と言った。
俺は「あ~そうなのかぁ」としか返事が出てこなかった。せめて神社付近で待っておけよと思ったけど言えなかった。
Cは、
「あの後、Aが『もう少しで開く!開く!』って叫び出したんだよ。Bも『開く!開く!』って…それが怖くて逃げたんだ」
と言った。
Eは、
「よく分かんないけど、Dの家に行ったら、Dの弟から神社に行くから来てくれってお前らが言ってたって聞いて、
すぐに神社に行ったんだけど、お前らいなくて、別のがいたから仕方なく帰ったら、次の日事故ったって聞いて驚いたよ」
「別のって?」
「いつも溜ってる場所に何人かいて、暗くてよく見えなかったけど、
お前らの転車はないし、雰囲気がなんかおかしかったからすぐ帰ってきたんだよ」
CとEと神妙な顔をしたまま、20分くらい話して帰っていった。その後は、刑事が来ていろいろ聞かれたから正直に全部話したけど、
神社の話より事故の瞬間の話しか興味がないみたいで、
「事故前後はまったく覚えてないです」って言ったら、残念そうに帰っていった。
後日、何度かまた刑事や相手の保険屋や弁護士が来て、話を聞かれたけど、
神社のくだりより、事故の時の話しか興味ない感じだった。事故を起こしたトラック運転手は精神的な疾患を持ってたらしくて、事故後に逃走して自殺を図ったらしい。
でも死にきれずに病院にいて、会話にならない状態だって聞いた。
重体だったDは結局あの後亡くなった。
Dの弟は俺を恨んでいるみたいで、退院後にDの家に線香あげにいった時も無視された。
俺はもともと東京の大学に進学が決まってたから、一月から学校に登校して3月に卒業した。
周りは妙に優しくしてくれたけど、俺は気まずくてCやEとは距離を置いた。
Cは4年前に自殺したらしいけど、俺は長い間地元に戻ってないから疎遠になってて詳しい話はしらない。いろいろあったから地元とは距離を置いてきたけど、昨年11月に親父が亡くなったから12年ぶりに地元に帰った。
大学卒業の時に一度帰ったけど、日帰りで一時間位しかいなかったから、じっくり帰るのは12年ぶり。
葬式など全部終わって、すぐ東京に帰ろうと思ったけど、母さんがなんか不憫でギリギリまで実家にいる事にした。昼間やる事もないんで、12年ぶりに徒歩で田舎町をウロウロしてたら、急にあの廃神社が気になった。
本当は思い出したくもないんだけど、その気持ちに反して神社が気になる!行きたい!と強く思った。
あの時の関係者といえばEだけど、12年間疎遠になっていたし、連絡しにくい。仕方なく一人で行った。
歩いてみると、神社は家や学校からかなり遠かったんだなぁと思った。
神社に比較的近かった行きつけのスーパーは潰れてビルになってたり、
近くにコンビニや大きなショッピングモールやマンションが出来てたり、12年前とは景観がかなり変わってた。
神社はまだあった。あの日以来の神社だった。俺は急に怖くなった。心臓が高鳴り、手のひらは汗でジトッとしてきた。
引き返そうと思ったけど、わざわざここまで歩いて来て今さら引き返すのも抵抗があって、
思いきって恐る恐る階段を昇った。
変わらない風景のはずだった。でも変わっていた。
神社は綺麗になっていた。賽銭箱や社や石造りの道も綺麗になっていた。
近くに若い女の子が箒を持って掃除していた。可愛い娘だった。
俺は人見知りするタイプだから、普段は絶対に声をかけたりしないんだけど、
神社のこの変貌っぷりを目の当たりにして、迷わず声をかけれた。
「すみません。あの…あのですね。10年以上前に神社に来てた者なんですが」
すると女の子は「はい?」と答えた。
関係ない話だけど顔はアッキーナにソックリだった。髪のとても長いアッキーナだった。
「10年くらい前に神社によく来ていたんですよ、実は」と言ったら、
「少しお待ち下さい」と、箒を置いて誰かを呼びに行った。
俺は周囲を見渡した。12年前にはなかった神社の横のアパートのバルコニーで、洗濯物を干している主婦が見えた。
「どうされましたか?」
神主さんなんだろうけど、私服を着た上品な顔立ちの年輩の白髪のじいさんが近寄ってきた。
アッキーナは箒を持ってお辞儀して、別の場所を掃除し始めた。
「すみません。12年前に…」と説明をしたら、神主さんは驚いた表情をしながら聞いていた。
一通り話をした。二年間溜り場にしていた事や、おばあさんの話、事故の話。
「あ~なるほど…。実はこの神社は、3年前に○○神社(よくわかんない)から分祀されて復興したんです」
俺は「はぁ…そうですか…」と答えた。
「まさかそんな話を聞けるなんて思いもしていませんでした。
その箱はその時に、おそらく開いたんでしょうなぁ…。
アレは冥界の門みたいなもんで、私も実際に手にとった事はないんですが…」
「なんですか?冥界の門って?あの箱どこに行ったんですか?」
「いやぁアレにはいろいろな呼び方があって、私どもは忌箱(キバコ)と呼んでます。
私がここに来たのが半年前で、前任の者が失踪したんですよ。
詳しい事は私も聞かされていないんですが、前任者が忌箱に取り込まれたという話を聞きましたが…」
「ええ~!!忌箱ってなんなんですか?Aたちが死んだのも何か原因があるんですか?!」
「分かりません。う~ん…命をとる事もあるのかもしれませんね…申し訳ないですが…」それから神主さんはお祓いをしてくれた。
神主さんは神主衣装に着替えて、30分くらい物々しい雰囲気の中でお祓いの儀式をしてくれた。
アッキーナはたまに様子を覗きにきた。俺は正座してお祓いをしてもらいながらアッキーナにさりげなく微笑んだ。
アッキーナはたぶん微笑み返してくれて、出て行った。
「忘れなさい。アレはあなたの人生にたまたま通りかかった、通り魔のようなものですから」と言われた。
俺は話せて良かった事と、お祓いのお礼を言って帰った。その後は東京に戻って普通に生活している。
東京に戻ってしばらく経った頃から夢をよく見るようになった。3日に一回は見る。
あの日、Dと神社に到着した後の光景だった。
神社に到着した後から事故に遭うまでの内容が、断片的に夢に出てきた。
この前は、トラックにひかれたのは運転手の責任じゃなく、
俺とDがAとBと車道で揉み合いになっていたところに衝突してきた内容だった。
他にも神社の境内でのおぞましい内容の夢を見た。
内容は誰にも言っていない。
夢の内容を口にしたら、とても恐ろしい事が起こりそうだからだ。最近になって俺は、これは夢じゃなく記憶なんじゃないかと思い始めている。
📚出典と派生・類似伝承
「忌箱」は2000年代前半、2ちゃんねるの「死ぬほど洒落にならない怖い話を集めてみない?」スレッドに投稿された実話風怪談である。
投稿者は「高校時代に体験した」と語っており、文体や臨場感のある描写が当時の読者に強いインパクトを与え、ネット怪談の中でも高評価を受けている。
類似伝承として挙げられる例
- 「パンドラの箱」(ギリシャ神話):開けてはならない箱のモチーフ
- 「コトリバコ」(洒落怖):呪物が入った箱により不幸が連鎖する都市伝説
- 「風習系怪談」:地域に根ざした儀式・禁忌にまつわる話と構造が似ている
また、「忌箱」は日本民俗学における“封じ物”の文化とも通じており、土着信仰や陰陽道の「結界思想」との関連も読み取れる。
🎬メディア登場・現代への影響
「忌箱」自体は商業メディアで明確に映像化・出版されている例は少ないが、その影響は多数のホラー創作に及んでいる。
類似構造を持つ作品の一例:
- 『コトリバコ』:YouTubeや実話怪談ドラマで再構成され人気
- 『呪詛』(Netflix):「触れてはならない映像」を扱う近年の呪物系作品
- 『リング』(貞子):「見る・開ける・知る」ことで呪いが伝播する構造が共通
また、YouTubeチャンネル「ナナフシギ」「オカルト部」などでも「忌箱」に触れる派生動画や考察が増加している。
🔍考察と文化的背景
「忌箱」が現代日本のネット文化において広く語られるようになった背景には、以下の要因がある。
- 日本文化における“タブー”と“禁忌”の根強さ
- 箱という日常的な物への“異物性”
- 若者の好奇心と代償というホラーの王道構造
また、物語の舞台となる「廃神社」は、かつて信仰されていたが忘れられた神や霊の怒りを示す舞台装置としても機能している。
「忌箱」は単なるホラーではなく、“見えないものを信じること”と、“忘却された信仰”に対する警鐘とも解釈できる。
🗺️出現地点
「忌箱」の物語では、具体的な地名は明かされていないが、以下のような描写がある:
- 山のふもとの廃神社
- 人気のない林道
- 地元でも訪れる人がいなくなった旧跡
このような描写から、日本の地方都市や農村部にある神社のイメージと重ねて語られることが多い。
📎関連リンク・参考資料
💬編集者コメント・考察
「忌箱」はいわゆる“洒落怖”の中でも、恐怖の本質が“明かされないまま進行する”点において完成度が高い。
恐怖を直接的に描かず、異変が起きるまでの“空気”を描写することで読者に強烈な不安を与える。この演出はホラー創作における理想的な手法であり、インディーホラーや創作ゲームにも応用が利く。
また、「見るな・触るな・持ち帰るな」といった“3禁ルール”が一貫して描かれる点も、ホラー民俗の定型として非常に興味深い。
近年では、「都市伝説系インフルエンサー」や「ネット発ホラー創作」において再注目されており、今後も派生コンテンツやゲームへの展開が期待されるテーマである。
🎧 都市伝説好き必見!“聴く怖い話”体験を始めよう【Audible / audiobook.jp 比較】
👣 この記事を読んで、背筋がゾワッとしたあなたへ。
もし“読む”だけでなく、“耳で聴く”怪談体験に興味があるなら――
オーディオブックサービスの【Audible】と【audiobook.jp】が、あなたをさらなる恐怖の世界へ案内してくれる。
イヤホン越しに囁かれる怨念、静寂の中で始まる恐怖体験。
一度聴いたら眠れなくなるかもしれない、人気の怪談朗読が多数ラインナップされている。
- 🔊 Audible(オーディブル)
Amazon提供。毎月1冊無料で、声優や芸人による怪談朗読をフルで聴ける。
『新耳袋』シリーズや、怪談師・ありがとうぁみ氏の朗読なども人気。
- 📚 audiobook.jp
日本発のオーディオブックサービス。月額で怪談やホラー作品が聴き放題。深夜に“連続再生”でじっくり楽しめる。
- 🎁 どちらも無料体験が可能。
まずは1本、深夜にイヤホンで試してみてほしい。文字では味わえない恐怖が、あなたの耳に忍び寄りよる。
🔥 話題の2大オーディオブックで聴ける《怪談・怖い話》作品
- 🔊 Audible(オーディブル):Amazon提供、1冊まるごと“無料”で試せる。プロ声優や芸能人による本格怪談朗読が魅力。
- 📚 audiobook.jp:月額プランで怪談やホラー作品が聴き放題。深夜にじっくり聴く“連続再生”が人気。
| タイトル | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 👻 新耳袋シリーズ | ✅ | ✅ |
| 🧟♂️ 稲川淳二 怪談ナイト | ✅ | ✅ |
| 🏚 事故物件怪談 恐音 | ✅ | ✅ |
| 🏞 廃墟・廃線にまつわる話 | ✅(一部) | ✅(一部) |
| 😨 実話怪談集 | 豊富 | 豊富 |
👇こんな人におすすめ!
- ✅ Audibleは…月1冊じっくり聴きたい人向け
- ✅ audiobook.jpは…いろんな怪談を聴き放題で楽しみたい人向け
🎧 どっちがいい?かんたん比較表
| 比較項目 | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 月額 | ¥1,500(1冊無料+聴き放題対象多数) | ¥1,330〜(聴き放題プラン) |
| 無料体験 | 30日間 | 14日間 |
| 怖い話の充実度 | ◎(稲川淳二/新耳袋ほか) | ◎(人気作+独自配信もあり) |
| アプリ使いやすさ | ○ | ◎(日本語対応に強い) |
| 配信ジャンル | 海外含め多彩 | 国内作品に強い |
🧟♂️ 聴くだけで“現地にいるような”恐怖体験
あなたは、ひとりでこの朗読を最後まで聴ける自信はあるだろうか?
「イヤホン越しに耳元で囁くような声がして、思わず音量を下げた…」
そんなレビューも少なくない、リアルな恐怖がここにある。
- ✅ 急に部屋が寒くなった気がする
- ✅ 背後に気配を感じた
- ✅ イヤホン越しに“もう一人”の声が聞こえる…
そんな体験を、ぜひ以下のリンクから始めてほしい。
🔽 無料で怪談体験を始めるならこちらから
👇どちらも無料で今すぐ試せるので、気になる作品を1本、まずは深夜に“イヤホンで”聴いてみてほしい――恐怖の臨場感がまるで違う。
\ 30日間無料体験キャンペーン実施中/
※Audibleは無料期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
\ 14日間無料体験キャンペーン実施中/
※audiobookは無料聴き放題プランの期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
👇こちらの記事も要チェック!
【もっと読む】↓