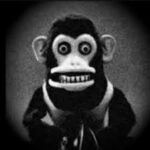🧠リゾートバイトとは?
『リゾートバイト』とは、2009年に怖い話投稿サイト「ホラーテラー」に初投稿され、その後「2ちゃんねる」の「洒落にならない怖い話」スレッドに再投稿されたネット怪談である。
舞台は日本のとある離島にある古びた旅館。主人公である「俺」と、大学の先輩である「K」は、夏休みのリゾートバイトとしてその旅館で働くことになる。
『リゾートバイト』は、単なる怪談にとどまらず、「異界との境界」「禁忌を破った代償」「伝承に根差す儀式」といった要素が複雑に絡み合うことで、読者にじわじわと迫る恐怖と違和感を与える構成となっている。
📖 リゾートバイトあらすじ
大学の夏、友人Kとともに離島の古びた旅館でリゾートバイトを始めた「俺」。仕事自体は単調だが、旅館の女将が「誰もいないはずの部屋に毎晩食事を運ぶ」という奇妙な行動を目撃したことで、次第に不穏な空気が漂い始める。
島の裏手にある封印された祠、Kの様子の変化、そして旅館の従業員や島民の言動が徐々におかしくなっていく。「俺」は恐怖と疑念のなかで、島の過去と女将の秘密、そして祠にまつわる禁忌の儀式の存在に気づく。
物語は後半、一気に加速。Kの突然の失踪、島民たちの異常な行動、祠の封印が解かれたことで異界との境界が崩れ始める。逃げ場のない孤島で、理性が通じない世界に巻き込まれた「俺」は、かつてない恐怖のなかで、生還を懸けた脱出を試みる。
原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2009/08/04 18:29
まずはじめに言っておくが、こいつは驚くほど長い。
そしてあろうことか、たいした話ではない。
死ぬほど暇なやつだけ読んでくれ。忠告はしたので、はじめる。
これは俺が大学3年の時の話。
夏休みも間近にせまり、大学の仲間5人で海に旅行に行こうって計画を立てたんだ。
計画段階で、仲間の一人がどうせなら海でバイトしないかって言い出して、
俺も夏休みの予定なんて特になかったから、二つ返事でOKを出した。
そのうち2人は、なにやらゼミの合宿があるらしいとかで、バイトはNGってことに。
結局、5人のうち3人が海でバイトすることにして、
残り2人は旅行として俺達の働く旅館に泊まりに来ればいいべって話になった。それで、まずは肝心の働き場所を見つけるべく、3人で手分けして色々探してまわることにした。
ネットで探してたんだが、結構募集してるもんで、友達同士歓迎っていう文字も多かった。
俺達はそこから、ひとつの旅館を選択した。
もちろんナンパの名所といわれる海の近く。そこはぬかりない。
電話でバイトの申し込みをした訳だが、それはもうトントン拍子に話は進み、
途中で友達と2日間くらい合流したいという申し出も、
『その分いっぱい働いてもらうわよ』という女将さんの一言で難なく決まった
計画も大筋決まり、テンションの上がった俺達は、そのまま何故か健康ランドへ直行し、
その後友達の住むアパートに集まって、風呂上りのツルピカンの顔で、ナンパ成功時の行動などを綿密に打ち合わせた。そして仲間うち3人(俺含む)が旅館へと旅立つ日がやってきた。
初めてのリゾートバイトな訳で、緊張と期待で結構わくわくしてる僕的な俺がいた。旅館に到着すると、2階建ての結構広めの民宿だった。
一言で言うなら、田舎のばーちゃんち。
『○○旅館』とは書いてあるけど、まあ民宿だった。○○荘のほうがしっくりくるかんじ。
入り口から声をかけると、中から若い女の子が笑顔で出迎えてくれた。
ここでグッとテンションが上がる俺。
旅館の中は、客室が4部屋、みんなで食事する広間が1つ、
従業員住み込み用の部屋が2つで計7つの部屋があると説明され、俺達ははじめ広間に通された。
しばらく待っていると、若い女の子が麦茶を持ってきてくれた。
名前は「美咲ちゃん」といって、この近くで育った女の子だった。
それと一緒に入ってきたのが、女将さんの「真樹子さん」。
恰幅が良くて笑い声の大きな、すげーいい人。もう少し若かったら俺惚れてた。
あと旦那さんもいて、計6人でこの民宿を切り盛りしていくことになった。ある程度自己紹介とかが済んで、女将さんが言った。
「客室は、そこの右の廊下を突き当たって左右にあるからね。
そんであんたたちの寝泊りする部屋は、左の廊下の突き当たり。
あとは荷物置いてから説明するから、ひとまずゆっくりしてきな」
ふと友達が疑問に思ったことを聞いた。(友達をA・Bってことにしとく)
A「2階じゃないんですか?客室って」
すると女将さんは、笑顔で答えた。
「違うよ。2階は今使ってないんだよ」
俺達は、今はまだシーズンじゃないからかな?って思って、特に気に留めてなかった。
そのうち開放するんだろ、くらいに思って。部屋について荷物を下ろして、部屋から見える景色とか見てると、本当に気が安らいだ。
これからバイトで大変かもしれないけど、こんないい場所でひと夏過ごせるのなら全然いいと思った。
ひと夏のあばんちゅーるも期待してたしね。
そうして俺達のバイト生活が始まった。大変なことも大量にあったが、みんな良い人だから全然苦にならなかった。
やっぱ職場は人間関係ですな。1週間が過ぎたころ、友達の一人がこう言った。
A「なあ、俺達良いバイト先見つけたよな」
B「ああ、しかもたんまり金はいるしな」
友達二人が話す中俺も、
俺「そーだな。でももーすぐシーズンだろ?忙しくなるな」
A「そういえば、シーズンになったら2階は開放すんのか?」
B「しねーだろ。2階って女将さんたち住んでるんじゃないのか?」
俺とAは「え、そうなの?」と声を揃える。
B「いやわかんねーけど。でも最近女将さん、よく2階に飯持ってってないか?」
A「知らん」
俺「知らん」
Bは夕時、玄関前の掃き掃除を担当しているため、2階に上がる女将さんの姿をよく見かけるのだという。
女将さんはお盆に飯を乗っけて、そそくさと2階へ続く階段に消えていくらしい。
その話を聞いた俺達は「へ~」「ふ~ん」みたいな感じで、別になんの違和感も抱いていなかった。それから何日かしたある日、いつもどおり廊下の掃除をしていた俺なんだが、
見ちゃったんだ。客室からこっそり出てくる女将さんを。
女将さんは基本、部屋の掃除とかしないんだ。そうゆうのするのは全部美咲ちゃん。
だから余計に怪しかったのかもしれないけど。
はじめは目を疑ったんだが、やっぱり女将さんで、
その日一日もんもんしたものを抱えていた俺は、結局黙っていられなくて友達に話したんだ。
すると、Aが言ったんだよ、
A「それ、俺も見たことあるわ」
俺「おい、マジか。なんで言わなかったんだよ」
B「それ、俺ないわ」
俺「じゃー黙れ」
A「だってなんか用あるんだと思ってたし、それに、疑ってギクシャクすんの嫌じゃん」
俺「確かに」
俺達はそのとき、残り1ヶ月近くバイト期間があった訳で。
3人で見てみぬふりをするか否かで話し合ったんだ。
そしたらBが「じゃあ、女将さんの後ろつけりゃいいじゃん」ていう提案をした。
A「つけるってなんだよ。この狭い旅館でつけるって、現実的に考えてバレるだろ」
B「まーね」
俺「なんで言ったんだよ」
AB俺「・・・」
3人で考えても埒があかなかった。
来週には残りの2人がここに来ることになってるし、何事もなく過ごせば楽しく過ごせるんじゃないかって思った。
だけど俺ら男だし。3人組みだし?
ちょっと冒険心が働いて、「なにか不審なものを見たら報告する」ってことで、その晩は大人しく寝たわけ。そしたら次の日の晩、Bがひとつ同じ部屋の中にいる俺達をわざとらしく招集。
お前が来いや!!と思ったが、渋々Bのもとに集まる。
B「おれさ、女将さんがよく2階に上がるっていったじゃん?あれ、最後まで見届けたんだよ。
いつも女将さんが、階段に入っていくところまでしか見てなかったんだけど、
昨日はそのあと出てくるまで待ってたんだよ。
そしたらさ、5分くらいで降りてきたんだ」
A「そんで?」
B「女将さんていつも俺らと飯くってるよな?
それなのに盆に飯のっけて2階に上がるってことは、誰かが上に住んでるってことだろ?」
俺「まあ、そうなるよな・・・」
B「でも俺らは、そんな人見たこともないし、話すら聞いてない」
A「確かに怪しいけど、病人かなんかっていう線もあるよな」
B「そそ。俺もそれは思った。でも5分で飯完食するって、結構元気だよな?」
A「そこで決めるのはどうかと思うけどな」
B「でも怪しくないか?お前ら怪しいことは報告しろっていったじゃん?だから報告した」
語尾がちょっと得意げになっていたので俺とAはイラっとしたが、そこは置いておいて、
確かに少し不気味だなって思った。
2階にはなにがあるんだろう?
みんなそんな思いでいっぱいだったんだ。原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2009/08/05 01:15
次の日、いつもの仕事を早めに済ませ、俺とAはBのいる玄関先へ集合した。
そして女将さんが出てくるのを待った。
しばらくすると女将さんは盆に飯を載せて出てきて、2階に上がる階段のドアを開くと、奥のほうに消えていった。
ここで説明しておくと、2階へ続く階段は玄関を出て外にある。
1階の室内から2階へ行く階段は、俺達の見たところでは確認できなかった。
玄関を出て壁伝いに進み角を曲がると、そこの壁にドアがある。
そこを開けると階段がある。わかりずらかったらごめん。とりあえずそこに消えてった女将さんは、Bの言ったとおり5分ほど経つと戻ってきて、お盆の上の飯は空だった。
そして俺達に気づかないまま1階に入っていった。
B「な?早いだろ?」
俺「ああ、確かに早いな」
A「なにがあるんだ?上」
B「知らない。見に行く?」
A「ぶっちゃけ俺、今ちょーびびってるけど?」
B「俺もですけど?」
俺「とりあえず行ってみるべ」
そう言って、3人で2階に続く階段のドアの前に行ったんだ。
A「鍵とか閉まってないの?」
というAの心配をよそに、俺がドアノブを回すとすんなり開いた。
「カチャ」
ドアが数センチ開き、左端にいたBの位置からならかろうじて中が見えるようになったとき、
B「うっ」
Bが顔を歪めて手で鼻をつまんだ。
A「どした?」
B「なんか臭くない?」
俺とAにはなにもわからなかったんだが、Bは激しく匂いに反応していた。
A「おまえ、ふざけてるのか?」
Aはびびってるから、Bのその動作に腹が立ったらしく、
でもBはすごい真剣で「いやマジで。匂わないの?ドアもっと開ければわかるよ」と言った。
俺は意を決してドアを一気に開けた。
モアっと暖かい空気が中から溢れ、それと同時に埃が舞った。
俺「この埃の匂い?」
B「あれ?匂わなくなった」
A「こんな時にふざけんなよ。俺、なにかあったら絶対お前置いてくからな。今心に決めたわ」
と、びびるAは悪態をつく。
B「いやごめんって。でも本当に匂ったんだよ。なんていうか・・生ゴミの匂いっぽくてさ」
A「もういいって。気のせいだろ」
そんな二人を横目に、俺はあることに気づいた。
廊下がすごい狭い。人が一人通れるくらいだった。
そして電気らしきものが見当たらない。外の光でかろうじて階段の突き当たりが見える。
突き当たりにはもうひとつドアがあった。
俺「これ、上るとなるとひとりだな」
A「いやいやいや、上らないでしょ」
B「上らないの?」
A「上りたいならお前行けよ。俺は行かない」
B「おれも、むりだな」
AがBをどつく。
俺「結局行かねーのかよ。んじゃー、俺行ってみる」
AB「本気?」
俺「俺こういうの、気になったら寝れないタイプ。寝れなくて真夜中一人で来ちゃうタイプ。
それ完全に死亡フラグだろ?だから、今行っとく。」
訳のわからない理由だったが、
俺の好奇心を考慮すれば、今AとBがいるこのタイミングで確認するほうがいいと思ったんだ。
でも、その好奇心に引けを取らずして恐怖心はあったわけで。
とりあえず俺一人行くことになったが、なにか非常事態が起きた場合は、
絶対に(俺を置いて)逃げたりせず、真っ先に教えてくれっていう話になったんだ。
ただし、何事もないときは、急に大声を出したりするなと。
もしそうしてしまったときは、命の保障はできないとも伝えた。俺のね。そんでソロソロと階段を上りだす俺。
階段の中は外からの光が差し込み、薄暗い感じだった。
慎重に一段ずつ階段を上り始めたが、途中から「パキっ・・・パキっ」と音がするようになった。
何事かと思い、怖くなって後ろを振り返り、二人を確認する。
二人は音に気づいていないのか、じっとこちらを見て親指を立てる。『異常なし』の意味を込めて。
俺は微かに頷き、再度2階に向き直る。
古い家によくある、床の鳴る現象だと思い込んだ。
下の入り口からの光があまり届かないところまで上ると、好奇心と恐怖心の均衡が怪しくなってきて、
今にも逃げ帰りたい気分になった。
暗闇で目を凝らすと、突き当たりのドアの前に何かが立っている・・・かもしれないとか、
そういう『かもしれない思考』が本領を発揮しだした。
「パキパキパキっ・・」
この音も段々激しくなり、どうも自分が何かを踏んでいる感触があった。
虫か?と思った。背筋がゾクゾクした。
でも何かが動いている様子はなく、暗くて確認もできなかった。
何度振り返ったかわからないが、途中から下の二人の姿が逆光のせいか、薄暗い影に見えるようになった。
ただ親指はしっかり立てていてくれた。そしてとうとう突き当たりに差し掛かったとき、強烈な異臭が俺の鼻を突いた。
俺はBとまったく同じ反応をした。
俺「うっ」
異様に臭い。生ゴミと下水の匂いが入り混じったような感じだった。
なんだ?なんだなんだなんだ?そう思って当たりを見回す。
その時、俺の目に飛び込んできたのは、突き当たり踊り場の角に大量に積み重ねられた飯だった。
まさにそれが異臭の元となっていて、何故気づかなかったのかってくらいに蝿が飛びかっていた。
そして俺は半狂乱の中、もうひとつあることを発見してしまう。
2階の突き当たりのドアの淵には、ベニヤ板みたいなのが無数の釘で打ち付けられていて、
その上から大量のお札が貼られていたんだ。
さらに、打ち付けた釘になんか細長いロープが巻きつけられてて、くもの巣みたいになってた。
俺、正直お札を見たのは初めてだった。
だからあれがお札だったと言い切れる自信もないんだが、大量のステッカーでもないだろうと思うんだ。
明らかに、なにか閉じ込めてますっていう雰囲気全開だった。
俺はそこで初めて、自分のしたことは間違いだったんだと思った。
帰ろう。そう思って踵を返して行こうとしたとき、
突然背後から「ガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリガリ」という音がしたんだ。
ドアの向こう側でなにか引っかいているような音だった。
そしてその後に、「ひゅー・・ひゅっひゅー」と不規則な呼吸音が聞こえてきた。
このときは本当に心臓が止まるかと思った。
そこに誰かいるの?誰?誰なの?
あの時の俺は、ホラー映画の脇役の演技を遥かに逸脱していたんじゃないかと思う。
そのまま後ろを見ずに行けばいいんだけど、あれって実際できないぞ。
そのまま行く勇気もなければ、振り返る勇気もないんだ。
そこに立ちすくむしかできなかった。
眼球だけがキョロキョロ動いて、冷や汗で背中はビッショリだった。
その間も「ガリガリガリガリガリガリ」「ひゅー・・ひゅっひゅー」って音は続き、
緊張で硬くなった俺の脚をどうにか動かそうと必死になった。
すると背後から聞こえていた音が一瞬やんで、シンっとなったんだ。
ほんとに一瞬だった。瞬きする間もなかったくらい。
すぐに「バンっ!」って聞こえて、「ガリガリガリガリガリガリ」って始まった。
信じられなかったんだけど、それはおれの頭の真上、天井裏聞こえてきたんだ。
さっきまでドアの向こう側で鳴っていたはずなのに、ソレが一瞬で頭上に移動したんだ。
足がブルブル震えだして、もうどうにもできないと思った。
心の中で、助けてって何度も叫んだ。
そんな中、本当にこれも一瞬なんだけど、視界の片隅に動くものが見えた。
あのときの俺は動くものすべてが恐怖で、見ようか見まいかかなり躊躇したんだが、
意を決して目をやると、それはAとBだった。
下から何か叫びながら手招きしている。
そこでやっとAとBの声が聞こえてきた。
A「おい!早く降りてこい!!」
B「大丈夫か?」
この瞬間一気に体が自由になり、我に返った俺は一目散に階段を駆け下りた。
あとで二人に聞いたんだが、俺はこの時目を瞑ったまま、一段抜かししながらものすごい勢いで降りてきたらしい。
駆け下りた俺は、とにかく安全な場所に行きたくて、そのままAとBの横を通りすぎ部屋に走っていったらしい。
この辺はあまり記憶がない。恐怖の記憶で埋め尽くされてるからかな。部屋に戻ってしばらくすると、AとBが戻ってきた。
A「おい、大丈夫か?」
B「なにがあったんだ?あそこになにかあったのか?」
答えられなかった。というか、耳にあの音たちが残っていて、思い出すのが怖かった。
するとAが慎重な面持ちで、こう聞いてきた。
A「お前、上で何食ってたんだ?」
質問の意味がわからず聞き返した。
するとAはとんでもないことを言い出した。
A「お前さ、上についてすぐしゃがみこんだろ?
俺とBで何してんだろって目を凝らしてたんだけど、なにかを必死に食ってたぞ。というか、口に詰め込んでた」
B「うん・・。しかもさ、それ・・」
AとBは揃って俺の胸元を見つめる。
なにかと思って自分の胸元を見ると、大量の汚物がくっついていた。
そこから、食物の腐ったような匂いがぷんぷんして、俺は一目散にトイレに駆け込み、胃袋の中身を全部吐き出した。
なにが起きているのかわからなかった。
俺は上に行ってからの記憶はあるし、あの恐怖の体験も鮮明に覚えている。
ただの一度もしゃがみこんでいないし、ましてやあの腐った残飯を口に入れるはずがない。
それなのに、確かに俺の服には腐った残飯がこびりついていて、よく見れば手にもソレを掴んだ形跡があった。
気が狂いそうになった。俺を心配して見に来たAとB。
A「何があったのか話してくれないか?ちょっとお前尋常じゃない」
俺は恐怖に負けそうになりながらも、一人で抱え込むよりはいくらかましだと思い、
さっき自分が階段の突き当たりで体験したことをひとつひとつ話した。
AとBは、何度も頷きながら真剣に話を聞いていた。
二人が見た俺の姿と、俺自身が体験した話が完全に食い違っていても、最後までちゃんと聞いてくれたんだ。
それだけで安心感に包まれて泣きそうになった。
少しホッとしていると、足がヒリヒリすることに気づいた。
なんだ?と思って見てみると、細かい切り傷が足の裏や膝に大量にあった。
不思議に思って目を凝らすと、なにやら細かいプラスチックの破片ようなものが所々に付着していることに気づいた。
赤いものと、ちょっと黒みのかかった白いものがあった。
俺がマジマジと見ていると、
Bは「何それ?」と言ってその破片を手にとって眺めた。
途端、「ひっ」と言ってそれを床に投げ出した。
その動作につられてAと俺も体がビクってなる。
A「なんなんだよ?」
B「それ、よく見てみろよ」
A「なんだよ?言えよ恐いから!」
B「つ、爪じゃないか?」
瞬間、三人共完全に固まった。
AB俺「・・・」
俺はそのとき、ものすごい恐怖のそばで、何故か冷静にさっきまでの音を思い返していた。
ああ、あれ爪で引っかいてた音なんだ・・・
どうしてそう思ったかわからない。
だけど、思い返してみれば繋がらないこともないんだ。
階段を上るときに鳴っていた「パキパキ」っていう音も、何かを踏みつけていた感触も、
床に大量に散らばった爪のせいだったんじゃないか?って。
そしてその爪は、壁の向こうから必死に引っかいている何かのものなんじゃないか?って。
きっと、膝をついて残飯を食ったとき、恐怖のせいで階段を無茶に駆け下りたとき、
床に散らばる爪の破片のせいでケガをしたんだろう。
でも、そんなことはもうどうでもいい。
確かなことは、ここにはもういられないってことだった。
俺はAとBに言った。
俺「このまま働けるはずがない」
A「わかってる」
B「俺もそう思ってた」
俺「明日、女将さんに言おう」
A「言っていくのか?」
俺「仕方ないよ。世話になったのは事実だし、謝らなきゃいけないことだ」
B「でも、今回のことで女将さん怪しさナンバーワンだよ?
もしあそこに行ったって言ったら、どんな顔するのか俺見たくない」
俺「バカ。言うはずないだろ。普通にやめるんだよ」
A「うん、そっちのほうがいいな」そんなこんなで、俺たちはその晩のうちに荷物をまとめ、
男なのにむさくるしくて申し訳ないが、あまりの恐怖のため、布団を2枚くっつけてそこに3人で無理やり寝た。
めざしのように寄り添って寝た。
誰一人、寝息を立てるやつはいなかったけど。
そうして明日を迎えることになるんだ。原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2009/08/06 01:05
次の日、誰もほとんど口をきかないまま朝を迎えた。
沈黙の中、急に携帯のアラームが鳴った。いつも俺達が起きる時間だった。
Bの体がビクンってなって、相当怯えているのが伺えた。
Bは根がすごく優しいヤツだから、前の晩俺に言ったんだ。
B「ごめんな。俺なんかより、お前のほうが全然怖い思いしたよな。
それなのに俺がこんなんでごめん。助けに行かなくて本当ごめん」
俺はそれだけで本当に嬉しくて目頭が熱くなった。
でもよくよく考えてみると、『俺なんかより怖い思い』ってなんだ?
実際に恐怖の体験をしたのは俺だし、AもBも下から眺めていただけだ。
もしかしてあれか?俺の階段を駆け下りる姿がマズかったか?
普通に考えて、俺の体験談が恐ろしかったってことか?
少し考えて、俺も大概、恐怖に呑まれて相手の言葉に過敏になりすぎてると思った。
こんな時だからこそ、早く帰ってみんなで残りの夏休みを楽しくゆっくり過ごそうと、そればかりを考えるようにした。だが、その後のBの怯えようは半端なかった。
俺達がたてる音一つ一つに反応したり、俺の足の傷を食い入るようにじっと見つめたり、明らかに様子がおかしかった。
Aも普段と違うBを見て、多少びびりながらも心配したんだろう、
A「おい、大丈夫か?寝てないから頭おかしくなってんのか?」と問いかけながらBの肩を掴んだ。
するとBは急に「うるさいっ!!」と叫び、Aの腕をすごい勢いで振り払ったんだ。
Aと俺は一瞬沈黙した。
俺「おい、どうしたんだよ?」
Aは急のできごとに驚いて声を出せずにいた。
B「大丈夫かだって?大丈夫なわけねーだろ?俺も○○(俺の名前)も死ぬような思いしてんだよ。
何にもわかってねーくせに心配したふりすんな!!」
Aを睨み付けながらそう叫んだ。
何を言ってるんだろうと思った。
Bの死ぬ思いってなんだ?俺の話を聞いて恐怖してたわけじゃないのか?
AとBは仲間内でも特に仲が良かったんだが、
その関係もAがBをいじる感じで、どんな悪ふざけにもBは怒らず調子を合わせていた。
だからBがAに声を荒げる場面なんか見たことなかったし、もちろん当の本人Aもそんな経験なかったんだと思う。
Aはこれも見たことないくらいにオロオロしていた。
俺は疑問に思ったことをBに問いかけた。
俺「死ぬ思いってなんだ?お前ずっと下にいたろ?」
B「いたよ。ずっと下から見てた」
そして少し黙ってから下を向いて言った。
B「今も見てる」
俺「・・・」
今も?え、何を?俺は訳がわからない。
全然わからないんだが、よくある話で、Bの気が狂ったんだと思った。何かに取り憑かれたんだと。
そんな思いをよそに、Bは震える口調で、でもしっかりと喋りだした。
B「あの時、俺は下にいたけど、でもずっと見てたんだ」
俺「上っていく俺だよな?」
B「違うんだ・・・いや、始めはそうだったんだけど。お前が階段を上りきったくらいから、見え出したんだ」
俺「・・・うん」
本当はこのとき俺の心の中は、聞きたくないという気持ちが大半を占めていた。
でもBは、もうこれ以上一人で抱えきれないという表情で、まるで前の日の自分を見ているようだったんだ。
あのとき、俺の話を最後までちゃんと聞いてくれたAとB、
あれで自分がどれだけ救われたかを考えると、俺には聞かなくちゃならない義務があるように思えた。
俺「何が、見えたんだ?」
B「・・・」
Bはまた少し黙りこみ、覚悟したように言った。
B「影・・・だと思う」
俺「影?」
B「うん。初めはお前の影だと思ってたんだ。
けど、お前がしゃがみこんで残飯を食っている間にも、ずっと影は動いてたんだ。
お前の影が小さくなるのはちゃんと見えたし、自分らの影も足元にあった。
それで、それ以外に動き回る影が・・・3つ・・・いや、4つくらいあった」
俺は全身にぶわっと鳥肌が立つのを感じた。
どうかこれがBの冗談であってくれと思った。
しかし、今目の前にいるBは、とてもじゃないが冗談を言っているように見えなかった。
むしろ、冗談という言葉を口に出したとたんに殴りかかってくるんじゃないかってくらいに真剣だった。
俺「あそこには、俺しかいなかった」
B「わかってる」
俺「そもそも、あのスペースに人が4,5人も入って動き回れるはずない」
あの階段は人が一人通れる位のスペースだったんだ。
B「あれは人じゃない。それ位わかるだろ」
俺「・・・」
B「それに、どう考えても人じゃ無理だ」
Bはポツリと言った。
俺「どういうことだ?」
B「全部、壁に張り付いてた」
俺「え?」
B「蜘蛛みたいに、全部壁の横とか上に張り付いてたんだ。
それで、もぞもぞ動いてて、それで、それで・・・」
自分の見た光景を思い出したのか、Bの呼吸が荒くなる。
俺「落ち着け!深呼吸しろ。な?大丈夫だみんないる」
Bはしばらく興奮状態だったが、落ち着きを取り戻してまた話しだした。
B「あれは人じゃない。いや、元から人じゃないんだけど、形も人じゃない。
いや、人の形はしてるんだけど、違うんだ」
Bが何を言いたいのかなんとなくわかった俺は、
俺「人間の形をしたなにかが、壁に張り付いてたってことか?」と聞いた。
Bは黙って頷いた。
口から飛び出そうなくらいに心臓の鼓動が激しくなった。
とっさに、Bが見たのは影じゃないと思った。
影が横や上の天井を動き回るのは不自然だ。
仮にそれが影だったとしても、確実にそこに何かがいたから影ができたんだ。
それくらいバカの俺でもわかる。
ということは、俺は自分の周りで這い回る何かに気づかず、しかも腐った残飯をモリモリと食べていたってことなのか?
あの音は・・?
あのガリガリと壁を引っかく音は、壁やドアの向こう側からじゃなくて、俺のいる側のすぐそばで鳴っていたということか?
あの呼吸音も?
恐怖のあまり頭がクラクラした。
そんな俺の様子を知ってか知らずか、Bは傍に立っていたAに向き直り、
B「ごめん、さっきは取り乱して。悪かった」と謝った。
A「いや、大丈夫・・こっちこそごめんな」
Aもすかさず謝った。その後なんとなく気まずい雰囲気だったが、俺は平静を保つのに必死だった。無意味に深呼吸を繰り返した。
そんな中Aが口を開いた。
A「お前さ、さっき今も見てるっていったけど」
BはAが言い終わらないうちに答えた。
B「ああ、ごめん。あれはちょっと、錯乱してたんだわ。ははっごめん、今は大丈夫」
そういったBの笑顔は、完全に作り笑いだった。
明らかに無理した笑顔で、目はどこか違うところを見ているようだった。関係ないんだが、このとき何故かものすごい印象的だったのは、Bの目の下がピクピクいってたことだ。
こんなん何人かに一人はよくあることだよな?
だけど無理して笑う人の目の下ピクピクは、結構くるものがあるぞ。話を戻すと、Aと俺はそれ以上聞かなかった。
臆病者だと思われても仕方ない。だけど怖くて聞けなかったんだ。
ちょっと考えてみろ、ここまで話したBが敢えて何かを隠すんだぞ。
絶対無理だろ。聞いたら、俺の心臓砕け散るだろ。それこそ俺が発狂するわ。少しの沈黙のあと、広間のほうから美咲ちゃんが朝飯の時間だと俺達を呼んだ。
3人で話している間に結構な時間が過ぎていたらしい。
正直、食欲などあるはずもなく。だが不審に思われるのは嫌だったし、行くしかないと思った。
俺はのっそりと立ち上がり、二人に言った。
俺「なるべく早いほうがいいよな。朝飯食い終わったら言おう」
A「そうだな」
B「俺、飯いいや。Aさ、ノートPCもってきてたよな?ちょっと貸してくれないか?」
A「いいけど、朝飯食えよ」
B「ちょっと調べたいことがあるんだ。あんまり時間もないし、悪いけど二人でいってきて」
俺「了解。美咲ちゃんに頼んで、おにぎり作ってもらってきてやるよ」
B「うん、ありがと」
A「パソコンは俺のカバンの中に入ってる。勝手に使っていいよ。ネットも繋がるから」
そう言って俺達はそのまま広間に行った。
後から考えると、辞めるその日の朝飯食うってどうなの?
他人がやってたら絶対突っ込むくせして、俺らふっつーに食べたんだが。広間に着くと、女将さんが俺らを見て、更には俺の足元をみて、満面の笑顔で聞いてきたんだ。
「おはよう、よく眠れた?」って。
そんな言葉、初日以来だったし、昨日のこともあったからすごい不気味だった。
びびった俺は直立不動になってしまったわけだが、
Aが「はい。すみません遅れて」と返事をしながら、俺のケツをパンと叩いた。
体がスっと動いた。
いつも人一倍びびってたAに、助け舟を出してもらうとは思わなかったから、正直驚いた。
そしてBが体調不良のためまだ部屋で寝ていることを伝え、美咲ちゃんにおにぎりを作ってもらえるよう頼んだ。
「あ、いいですよ。それよりBくん、今日は寝てたほうがいいんじゃ」
美咲ちゃんは心配そうにそう言った。
Aと俺は特に何も言わず席についた。
『もう辞めるから大丈夫』とは言えないからな。朝飯を食っている間、女将さんはずっとニコニコしながら俺を見てた。
箸が完全に止まってるんだ。俺ときどき飯、みたいな。
美咲ちゃんも旦那さんもその異様な光景に気づいたのか、チラチラ俺と女将さんを見てた。
Aは言うまでもなく凝固。
凄まじく気分の悪くなった俺達は朝飯を早々に切り上げて、女将さん達に話をするため部屋にBを呼びに行った。部屋に戻る途中、Bの話し声が聞こえてきた。
どうやらどこかに電話をしているようだった。
俺達は電話中に声をかけるわけにもいかなかったので、部屋に入り座って電話が終わるのを待った。
B「はい、どうしても今日がいいんです。・・・・はい、ありがとうございます!
はい、はい、必ず伺いますのでよろしくお願いします」
そう言って電話を切った。
どうやらBは、ここから帰ってすぐどこかへ行く予定を立てたらしい。
俺もAも別に詮索するつもりはなかったんで何も聞かず、すぐにBを連れて広間に向かった。広間に戻ると、美咲ちゃんが朝飯の片付けをしていた。女将さんはいなかった。
俺はふと思った。
あそこに行ってるんじゃないか?って。
盆に飯のっけて、2階への階段に消えていったあの女将さんの後姿がフラッシュバックした。
きっとあの時持って行った飯は、あの残飯の上に積み重ねてあったんだろう。
そうして何日も何日も繰り返して、あの山ができたんだろうな。
一体あれは何のためなんだ?
俺の頭に疑問がよぎった。
けど、そんなこと考えるまでもないとすぐに思い直した。
俺は今日で辞めるんだ。ここともおさらばするんだ。すぐに忘れられる。忘れなきゃいけない。
心の中で自分に言い聞かせた。
Aが女将さんの居場所を美咲ちゃんに尋ねた。
「女将さんならきっと、お花に水やりですね。すぐ戻ってきますよ」
そう言って美咲ちゃんはBの方を見て、「Bくん、すぐおにぎり作るからまっててね」と笑顔で台所に引っ込んだ。
ああ、美咲ちゃん・・・何もなければきっと俺は美咲ちゃんとひと夏のあばん(ry
俺達は女将さんが戻ってくるのを待った。しばらくすると女将さんは戻ってきて、仕事もせずに広間に座り込む俺達を見て、
「どうしたのあんたたち?」とキョトンとした顔をしながら言った。
俺は覚悟を決めて切り出した。
俺「女将さん、お話があるんですけど、ちょっといいですか?」
女将さんは「なんだい?深刻な顔して」と俺達の前に座った。
俺「勝手を承知で言います。俺達、今日でここを辞めさせてもらいたいんです」
AとBもすぐ後に「お願いします」と言って頭を下げた。
女将さんは表情ひとつ変えずにしばらく黙っていた。
俺はそれがすごく不気味だった。
眉ひとつ動かさないんだ。まるで予想していたかのような表情で。
そして沈黙の後、「そうかい。わかった、ほんとにもうしょうがない子たちだよ~」と言って笑った。そして給料の話、引き上げる際の部屋の掃除などの話を一方的に喋り、
用意ができたら声をかけるようにと俺達に言ったんだ。
拍子抜けするくらいにすんなり話が通ったことに、三人とも安堵していた。
だけど、心のどこかでなんかおかしいと思う気持ちもあったはずだ。話が決まったからには俺達は即行動した。
荷物は前の晩のうちにまとめてある。あとは部屋の掃除をするだけで良かった。
バイトを始めてから、仕事が終われば近くの海で遊んだり、疲れてる日には戻ってすぐに爆睡だったんで、
部屋にいる時間はあまりなかったように思う。
だから男3人の部屋といえど、元からそんなに汚れているわけでもなかった。
そんなこんなで、一時間ほどの掃除をすれば部屋も大分綺麗になった。準備ができたということで、俺達は広間に戻り女将さんたちに挨拶をすることにした。
原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2009/08/10 00:11
広間に着くと女将さんと旦那さん、そして悲しそうな顔をした美咲ちゃんが座っていた。
俺達は3人並んで正座し、
俺「短い間ですが、お世話になりました。勝手言ってすみません」
俺AB「ありがとうございました」と言って頭を下げた。
すると女将さんが腰を上げて、俺達に近寄りこう言った。
「こっちこそ、短い間だったけどありがとうね。これ、少ないけど・・・」
そう言って茶封筒を3つ、そして小さな巾着袋を3つ手渡してきた。
茶封筒は思ったよりズッシリしてて、巾着袋はすごく軽かった。
そして後ろから美咲ちゃんが「元気でね」と、ちょっと泣きそうな顔しながら言うんだ。
そして、「みんなの分も作ったから」って、3人分のおにぎりを渡してくれた。
おいおい止めてくれ。泣いちゃうよ俺!
そう思ってあんまり美咲ちゃんの顔を見れなかった。
前日で死にそうな思いしたのにまさかのセンチって思うだろ?
だけど、実際すげー世話になった人との別れって、その時はそういうの無しになるものなんだわ。挨拶も済んで、俺達は帰ることになった。
行きは近くのバス停までバスを使って来たんだが、帰りはタクシーにした。
旦那さんが車で駅まで送ってくれるって話も出たんだが、Bが断った。
そして美咲ちゃんに頼んでタクシーを呼んでもらった。タクシーが到着すると、女将さんたちは車まで見送りに来てくれた。
周りから見ればなんとなく感動的な別れに見えただろうが、実際俺達は逃げ出す真っ最中だったんだよな。
タクシーに乗り込む前に、俺は振り返った。
かろうじて見えた2階への階段のドア。目を凝らすと、ほんの少し開いてるような気がして思わず顔を背けた。
そして3人とも乗り込み、行き先を告げた後すぐ車が動き出した。旅館から少し離れると、急にBが運転手に行き先を変更するよう言ったんだ。
運転手になにかメモみたいなものを渡して、「ここに行ってくれ」と。
運転手はメモを見て怪訝な顔をして聞いてきた。
「大丈夫?結構かかるよ?」
B「大丈夫です」
Bはそう答えると、後部座席でキョトンとしているAと俺に向かって、
B「行かなきゃいけないとこがある。お前らも一緒に」と言った。
俺とAは顔を見合わせた。考えてることは一緒だったと思う。
どこへ行くんだ・・?
だが、朝のBの様子を見た後だったんで、正直気が引けて何も聞けなかった。
またキレ出すんじゃないかとびびってたんだ。しばらく走っていると、運転手さんが聞いてきた。
「後ろ走ってる車、お客さんたちの知り合いじゃない?」
え?と思って振り返ると、軽トラックが一台後ろにぴったりくっついて走っていた。
そして中から手を振っていたのは旦那さんだった。
俺達は何か忘れ物でもしたのかと思い、車を止めてもらえるよう頼んだ。
道の端に車が止まると、旦那さんもそのまますぐ後ろに軽トラを止めた。
そして出てくると俺達のところに来て、「そのまま帰ったら駄目だ」と言った。
B「帰りませんよ。こんな状態で帰れるはずないですから」
Bと旦那さんはやけに話が通じあっていて、Aと俺は完全に置いてけぼりを食らった。
俺「え、どういうこと?」
なにがなにやらわからんかったので、素直に質問した。
すると旦那さんは俺のほうを向き、まっすぐ目を見つめて言った。
旦「おめぇ、あそこ行ったな?」
心臓がドクンって鳴った。
なんで知ってんの?
この時は本気で怖かった。
霊的なものじゃなくて、なんていうか、大変なことをしてしまったっていう思いがすごくて。
俺は「はい」と答えるだけで精一杯だった。
すると旦那さんは、ため息をひとつ吐くと言った。
旦「このまま帰ったら完全に持ってかれちまう。なぁんであんなとこ行ったんだかな。
まあ、元はと言えば、俺がちゃんと言わんかったのが悪いんだけどよ」
おい、『持ってかれる』ってなんだ。勘弁してくれよ。
ここから帰ったら楽しい夏休みが待ってるはずだろ?
不安になってAを見た。Aは驚くような目で俺を見ていた。
さらに不安になってBを見た。
するとBは言うんだ。
B「大丈夫。これから御祓いに行こう。そのためにもう向こうに話してあるから」
信じられなかった。
憑かれていたってことか?
何だよ俺死ぬのか?この流れは死ぬんだよな?
なんであんなとこ行ったんだって?行くなと思うなら始めから言ってくれ。
あまりの恐怖で、自分の責任を誰か他の人に転嫁しようとしていた。
呆然としている俺を横目に、旦那さんは話を進めた。
旦「御祓いだって?」
B「はい」
旦「おめぇ、見えてんのか」
B「・・・」
A「おい、見えてるって・・・」
B「ごめん。今はまだ聞かないでくれ」
俺は思わずBに掴みかかった。
俺「いい加減にしろよ。さっきから何なんだよ!」
旦那さんが割って入る。
旦「おいおい止めとけ。おめぇら、逆にBに感謝しなきゃならねぇぞ」
A「でも、言えないってことないんじゃないすか?」
旦「おめぇらはまだ見えてないんだ。一番危ないのはBなんだよ」
俺とAは揃ってBを見た。
Bは困ったような顔をしてそこにいた。
俺「どうしてBなんですか?実際にあそこに行ったのは俺です」
旦「わかってるさ。でもおめぇは見えてないんだろ?」
俺「さっきから見えてるとか見えてないとか、なんなんですか?」
旦「知らん」
俺「はぁ!?」
トンチンカンなことを言う旦那さんに対して俺はイラっとした。
旦「真っ黒だってことだけだな、俺の知ってる情報は。だがなぁ・・」
そう言って旦那さんはBを見る。
旦「御祓いに行ったところで、なんもなりゃせんと思うぞ」
Bは疑いの目を旦那さんに向けて聞いた。
B「どうしてですか?」
旦「前にもそういうことがあったからだな。でも、詳しくは言えん」
B「行ってみなくちゃわからないですよね?」
旦「それは、そうだな」
B「だったら」
旦「それで駄目だったら、どうするつもりなんだ?」
B「・・・」
旦「見えてからは、とんでもなく早いぞ」
『早い』という言葉が何のことを言っているのか、俺にはさっぱりわからなかった。
だが、旦那さんがそういった後、Bは崩れ落ちるようにして泣き出したんだ。
声にならない泣き声だった。
俺とAは傍で立ち尽くすだけで何もできなかった。
俺達の異様な雰囲気を感じ取ったのか、タクシーの窓を開けて中から運転手が話しかけてきた。
「お客さんたち大丈夫ですか?」
俺達3人は何も答えられない。Bに限っては道路に伏せて泣いてる始末だ。
すると旦那さんが、運転手に向かってこう言った。
旦「あぁ、すまんね。呼び出しておいて申し訳ないんだが、こいつらはここで降ろしてもらえるか?」
運転手は「え?でも・・」と言って、俺達を交互に見た。
その場を無視して旦那さんはBに話しかける。
旦「俺がなんでおめぇらを追いかけてきたかわかるか?
事の発端を知る人がいる。その人のとこに連れてってやる。
もう話はしてある。すぐ来いとのことだ」
時間がねぇ。俺を信じろ」
肩を震わせ泣いていたBは精一杯だったんだろうな、顔をしわくちゃにして声を詰まらせながら言った。
B「おねが・・っ・・します・・・」
呼吸ができていなかった。
男泣きでもなんでもない、泣きじゃくる赤ん坊を見ているようだった。
昨日の今日だが、Bは一人で何かものすごい大きなものを抱え込んでいたんだと思った。
あんなに泣いたBを見たのは、後にも先にもこの時だけだ。
Bのその声を聞いた俺は、運転手に言った。
俺「すいません。ここで降ります。いくらですか?」その後、俺達は旦那さんの軽トラに乗り込んだ。
といっても、俺とAは後の荷台なわけで。乗り心地は史上最悪だった。
旦那さんは俺達が荷台に乗っているにも関わらず、有り得んほどにスピードを出した。
Aから軽く女々しい悲鳴を聞いたがスルーした。どれくらい走ったのか分からない。あんまり長くなかったんじゃないかな。
まあ正直、それどころじゃないほど尾てい骨が痛くて覚えていないだけなんだが。
着いた場所は普通の一軒家だった。
横に小さな鳥居が立っていて、石段が奥の方に続いていた。
俺達の通されたのはその家の方で、
旦那さんは呼び鈴を鳴らして待っている間、俺達に「聞かれたことにだけ答えろ」と言った。
旦「おめぇら、口が悪いからな。変なこと言うんじゃねぇぞ」
俺は思った。この人にだけは言われる筋合いがないと。
少し待つと、家から一人の女の人が出てきた。
年は20代くらいの普通の人なんだけど、額の真ん中にでっかいホクロがあったのがすごく印象的だった。その女の人に案内されて通されたのは、家の一角にある座敷だった。
そこには一人の坊さん(僧って言うのか?)と、一人のおっさん、一人のじいさんが座っていた。
俺達が部屋に入るなり、おっさんが「禍々しい」と呟いたのが聞こえた。
旦「座れ」
旦那さんの掛け声で俺達は、坊さんたちが並んで座っている丁度向かい側に3人並んで座った。
そして旦那さんがその隣に座った。
するとじいさんは口を開いた。
「○○(旅館の名前)の旦那、この子ら全部で3人かね?」
旦「えぇ、そうなんですわ。このBって奴は、もう見えてしまってるんですわ」
旦那さんがそう言った瞬間、おっさんとじいさんは顔を見合わせた。
すると坊さんが口を開いた。
坊「旦那さん、堂に行ったというのは彼ですか?」
旦「いえ。実際行ったのはこの○○(俺の名前)って奴で」
坊「ふむ」
旦「Bは下から覗いていただけらしいんです」
坊「そうですか」
そして少し黙ったあと、坊さんはBに聞いたんだ。
坊「あなたは、この様な経験は初めてですか?」
Bが聞き返す。
B「この様な経験?」
坊「そうです。この様に、霊を見たりする体験です」
B「え・・ないです」
坊「そうですか。不思議なこともあるものです」
B「・・俺」
Bが何か喋ろうとしていた。
そこにいた全員がBを見た。
坊「はい」
B「俺・・・死ぬんでしょうか?」
そう言ったBの腕は、正座した膝の上で突っ張っているのにガクガクと震えていた。
すると坊さんは静かに答えた。
坊「そうですね。このままいけば、確実に」
Bは言葉を失った様子だった。震えが急に止まって、畳を一点食い入るように見つめだした。
それを見たAが口を挟んだ。
A「死ぬって」
坊「持って行かれるという意味です」
意味を説明されたところで俺達はわからない。何に何を持って行かれるのか。
更に坊さんは続けた。
坊「話がわからないのは当然です。○○くんは、堂へ行った時に何か違和感を感じませんでしたか?」
坊さんが堂といっているのは、どうやらあの旅館の2階の場所らしかった。
それで俺は答えた。
俺「音が聞こえました。あと、変な呼吸音が。2階のドアには、お札の様なものが沢山貼ってありました」
坊「そうですか。気づいているかも知れませんが、あそこには人ではないものがおります」
あまり驚かなかった。事実、俺もそう思っていたからだ。
坊「恐らくあなたは、その人ではないものの存在を耳で感じた。
本来ならば、人には感じられないものなのです。誰にも気づかれず、ひっそりとそこにいるものなのです」
そう言うと、坊さんはゆっくりと立ち上がった。
坊「Bくん、今は見えていますか?」
B「いえ。ただ音が、さっきから壁を引っかく音がすごくて」
坊「ここには入れないということです。幾重にも結界を張っておきました。その結界を必死に破ろうとしているのですね」
しかし、皆がいつまでもここに留まることは出来ないのです。
今からここを出て、おんどう(ごめん音でしかわからない)へ行きます。
Bくん、ここから出れば、またあのものたちが現れます」
また苦しい思いをすると思います。
でも必ず助けますから、気をしっかり持って付いて来てくださいね」
Bはカクカクと首を縦に振っていた。そうして坊さんに連れられて俺達は、その家を出てすぐ隣の鳥居をくぐり、石段を登った。
旦那さんは家を出るまで一緒だったが、おっさんたちと何やら話をした後、坊さんに頭を下げて行ってしまった。
知ってる人がいなくなって一気に心細くなった俺達は、3人で寄り添うように歩いた。
特にBは目を左右に動かしながら背中を丸めて歩いていて、明らかに憔悴しきっていた。
だから俺達は、できる限りBを真ん中にして二人で守るように歩いた。石段を上り終わる頃、大きな寺が見えてきた。
だが坊さんはそこには向かわず、俺達を連れて寺を右に回り奥へと進んだ。
そこにはもう一つ鳥居があり、更に石段が続いていた。
鳥居をくぐる前に坊さんがBに聞いた。
坊「Bくん、今はどんな感じですか?」
B「二本足で立っています。ずっとこっちを見ながら、付いてきてます」
坊「そうか、もう立ちましたか。よっぽどBくんに見つけてもらえたのが嬉しかったんですね。
ではもう時間がない。急がなくてはなりませんね」そして石段を上り終えると、さっきの寺とは比べ物にならない位小さな小屋がそこにあり、
坊さんはその小屋の裏へ回ると、俺達を呼んだ。
俺達も裏へ回ると坊さんは、ここに一晩入り憑きモノを祓うのだと言った。
そして、中には明りが一切ないこと、夜が明けるまでは言葉を発っしてはならないことを伝えてきた。
坊「もちろん、携帯電話も駄目です。明りを発するものは全て。食ったり寝たりすることもなりません」
どうしても用を足したくなった場合はこの袋を使用するようにと、変な布の袋を渡された。
俺は目を疑った。布って・・・
だが坊さん曰く、中から液体が漏れないようになっているらしい。
信じ難かったが、そこに食いついてもしょうがないので大人しくしといた。その後、俺達に竹の筒みたいなものに入った水を一口ずつ飲ませ、自分も口に含むと俺達に吹きかけてきた。
そして、小さな小屋の中に入るように言った。
俺達は順番に入ろうとしたんだが、Bが入る瞬間、口元を押さえて外に飛び出して吐いたんだ。
突然のことで驚いた俺達だったが、坊さんが慌てた様子で聞いてきた。
坊「あなたたち、堂に行ったのは今日ではないですよね?」
俺「え?昨日ですけど」
坊「おかしい、一時的ではあるが身を清めたはずなのに、おんどうに入れないとは」
言ってる意味がよく分からなかった。
すると坊さんはBのヒップバッグに目をつけ、
坊「こちらに滞在する間、誰かから何かを受け取りましたか?」と聞いてきた。
俺は特に思い浮かばず、だがAが言ったんだ。
A「今日給料もらいましたけど」
当たり前すぎて忘れてた。
そういえば給料も貰いものだなって妙に感心したりして。
俺「あ、あと巾着袋も」
A「おにぎりも。もらい物に入るなら」
給料を貰った時に、女将さんにもらった小さな袋を思い出した。
そして美咲ちゃんには、朝おにぎりを作って貰ったんだった。
坊さんはそれを聞くと、Bに話しかけた。
坊「Bくん、それのどれか一つを今、持っていますか?」
B「おにぎりはデカイ鞄の方に入れてありますけど、給料と袋は今持ってます」
Bはそう言って、バッグからその二つを取り出した。
坊さんはまず巾着袋を開けた。
すると「これは・・」と言って、俺達に見えるように袋の口を広げた。
中を覗き込んで俺達は息を呑んだ。
そこには、大量の爪の欠片が詰まっていたんだ。
俺の足に張り付いていたものと一緒だった。見覚えのある、赤と黒ずんだものだった。
Bはその場ですぐまた吐いた。俺もそれに釣られて吐いた。
周辺が汚物の匂いでいっぱいになり、坊さんも顔を歪めていた。
坊さんはBの持ち物を全て預かると言い、俺達2人も持ち物を全て出すように言った。
俺は携帯と財布を坊さんに手渡し、旅行鞄の方に入っている巾着袋を処分してもらえるよう頼んだ。
坊さんは頷き、再度Bに竹筒の水を飲ませ、吹きかけた。そして俺達3人がおんどうの中に入ると、
坊「この扉を開けてはなりません。皆、本堂のほうにおります。明日の朝まで、誰もここに来ることはありません。
そして、壁の向こうのものと会話をしてはなりません。このおんどうの中でも言葉を発してはなりません。
居場所を教えてはなりません。
これらをくれぐれもお守りいただけますよう、お願いします」
そう言って俺達の顔を見渡した。
俺達は頷くしかなかった。
この時既に言葉を発してはならない気がして、怖くて何も言えなかったんだ。
坊さんは俺達の様子を確認すると、扉を閉め、そのまま何も言わず行ってしまった。原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2009/08/13 03:42
おんどうの中はひんやりしていた。
実際ここで飲まず食わずでやっていけるのかと不安だったが、これなら一晩くらいは持ちそうだと思った。
建物自体はかなり古く、壁には所々に隙間があった。といっても結構小さいものだけど。
まだ昼時ということもあり、外の光がその隙間から入り、AとBの顔もしっかり確認できた。
顔を見合わせても何も喋ることができないという状況は、生まれて初めてだった。
『大丈夫だ』という意味を込めて俺が頷くと、AもBも頷き返してくれた。しばらくすると顔を見合わせる回数も少なくなり、終いにはお互い別々の方向を向いていた。
喋りたくても喋れないもどかしさの中、後どれくらいの時間が残っているのか見当も付かない俺達は、
ただただ呆然とその場にいることしかできなかったんだ。
途方もない時間が過ぎていると感じているのに、まだ外は明るかった。
するとAがゴソゴソと音を立て出した。
何をしているのかと思い、あまり大きな音を出す前に止めさせようと思ってAの方に向き直ると、
Aは手に持った紙とペンを俺達に見せた。
こいつは坊さんの言うことを聞かずに、密かにペンを隠し持っていたのだ。
そして紙は、板ガムの包み紙だった。
まあメモ用紙なんて持っているはずない俺達なので、きっとそれしか思い浮かばなかったんだろう。
こいつ何やってんだよ・・・
一瞬そう思った俺だが、意思の疎通ができないこの状況で極限に心細くなっていた所為もあり、
Aの取った行動に何も言う事が出来なかった。
むしろ、ひとつの光というか、上手く説明できないんだが、とにかくすごく安心したのを覚えてる。
Aはまず自分で紙に文字を書き、俺に渡してきた。
『みんな大丈夫か?』
俺はAからペンを受け取り、なるべく小さく、スペースを空けるようにして書き込んだ。
『俺は今のところ大丈夫、Bは?』
そしてBに紙とペンを一緒に手渡した。
『俺も今は平気。何も見えないし聞こえない。』
そしてAに紙とペンが戻った。
こんな感じで、俺達の筆談が始まったんだ。
A『ガム残り4枚。外紙と銀紙で8枚。小さく文字書こう』
俺『OK。夜になったらできなくなるから今のうちに喋る』
B『わかった』
A『今何時くらい?』
俺『わからん』
B『5時くらい?』
A『ここ来たの1時くらいだった』
俺『なら4時くらいか』
B『まだ3時間か』
A『長いな』
こんな感じで他愛もない話をして、1枚目が終わった。
するとAが書いてきた。
A『○○文字でかい』
俺は謝る仕草を見せた。
するとAは俺にペンを渡してきたので、『腹減った』と書き込みBに渡した。
そしてBが何も書かずにAに紙を渡した。
するとAは『俺も』と書いて俺に渡してきた。
あれだけ心細かったのに、いざ話すとなるとみんな何も出てこなかった。
俺は日が沈む前に言っておかなければならないことを書いた。
俺『何があっても、最後までがんばろうな』
B『うん』
A『俺、叫んだらどうしよう』
俺『なにか口に突っ込んどけ』
B『突っ込むものなんてないよ』
A『服脱いでおくか』
俺『てか、何も起きない、そう信じよう』
Bは俺の書いた言葉にはノーコメントだった。
俺も書いたあと、自分で何を言ってるんだろうと思った。
坊さんは、何も起きないとは一言も言っていなかった。
むしろ、これから何が起こるのかを予想しているような口ぶりで、俺達にいくつも忠告をしたんだ。
そう考えると俺達は、一刻も早く時間が過ぎてくれることを願っている一方で、
本当の本当は、夜を迎えるのがすごく怖かったんだ。
夜だけじゃない、あの時ああしてる時間も、本当は怖くてしょうがなかった。
唯一の救いが、互いの存在を目視できるということだっただけで。
俺の一言で空気が一気に重くなった。
俺はこの空気をどうにかしようと、Bの持っていた紙とペンをもらい、
俺『何か喋れ時間もったいない』と書いてAに渡した。他人任せもいいとこ。
Aは一瞬困惑したが、少し考えて書き出し、俺に渡してきた。
A『じゃあ、帰ったら何するか』
俺『いいね。俺はまずツタヤだな』
B『なんでツタヤ?』
俺『DVD返すの忘れてた』
A『どんだけ延泊!?』
まあ嘘だった。どうにかして気を紛らわせたかったから、なんでもいいやって適当に書いた。
結果、雰囲気はほんの少しだが和み、AもBもそれぞれ帰ったら何をするかを書いた。少しずつだが、ゆっくりと俺達は静かな時間を過ごした。
そして残りの紙も少なくなった頃、Bはある言葉を紙に書いた。
B『俺は坊さんに言われたことを必ず守る。死にたくない』
俺もAも、最後の言葉を見つめてた。
俺は『死にたくない』なんて言葉、生まれてこの方本気で言ったことなんかない。きっとAもそうだろう。
死ぬなんて考えていなかったからだ。
死を間近に感じたことがないからだ。
それを今目の前で心の底から言うヤツがいる。その事実がすごく衝撃的だった。
俺はBの目をしっかりと見つめ、頷いた。
その後は特に何も話さなかったが、不思議と孤独感はなかった。
お互いの存在を感じながら、俺達は日が暮れるのを感じていた。何もせずにいると蝉の鳴き声がうるさくて、でも徐々に耳が慣れて気にならなくなった。
でも、なんか違和感なんだ。よく耳を凝らすと、なにか他の音が聞こえるんだ。
さらに耳を凝らすと、段々その音がクリアに聞こえるようになった。
俺は考えるより先に確信した。あの呼吸音だって。
Bを見た。薄暗くて分かりづらかったが、Bに気づいている気配はなかった。
Bには聞こえないのか?
そういえばBって呼吸音について言ってたっけ?
もしかしてあれは聞いたことがないのか?
それとも単に気づいていないだけか?
頭の中で色々な考えが浮かんだ。
すると硬直する俺の様子に気づいたBが、周りをキョロキョロと見回し始めた。
この状況の中で、神経が過敏にならないはずがなかった。俺の異変にすぐ気づいたんだ。
するとBの視線が一点に止まった。俺の肩越しをまっすぐ見つめていた。
白目が一気にデカくなり、大きく見開いているのがわかった。
AもBの様子に気が付き、Bの見ている方を見ていたが、何も見つけられないようだった。
俺は怖くて振り返れなかった。
それでも、あの呼吸音だけは耳に入ってくる。
ソレがすぐそこにいることがわかった。動かず、ただそこで「ひゅーっひゅーっ」といっていた。
しばらく硬直状態が続くと、今度は俺達のいるおんどうの周りを、ズリズリとなにか引きずるような音が聞こえ始めたんだ。
Aはこの音が聞こえたらしく、急に俺の腕を掴んできた。
その音はおんどうの周りをぐるぐると回り、
次第に呼吸音が「きゅっ・・・・きゅえっ・・」っていう、何か得体の知れない音を挟むようになった。
俺には音だけしか聞こえないが、ソレがゆっくりとおんどうの周りを徘徊していることは分かった。
Aの腕から心臓の音が伝わってくるのを感じた。
Bを確認する余裕がなかったが、固まってたんだと思う。
全員微動だにしなかった。
俺は恐怖から逃れるために、耳を塞いで目を瞑っていた。
頼むから消えてくれと、心の中でずっと願っていた。どれくらい時間が経ったかわからない。ほんの数分だったかも知れないし、そうでないかも知れない。
目を開けて周りを見回すと、おんどうの中は真っ暗で、ほぼ何も見えない状態だった。
そしてさっきまでのあの音は消えていた。
恐怖の波が去ったのか、それともまだ周りにいるのか、判断がつかず動けなかった。
そして目の前に広がる深い闇が、また別の恐怖を連れて来たんだ。
目を凝らすが何も見えない。
『いるか?』『大丈夫か?』の掛け声さえ出せない。
ただAはずっと俺の腕を握ってたので、そこにいるのが分かった。
俺はこの時猛烈にBが心配になった。Bは明らかに何かを見ていた。
暗がりの中でBを必死に探すが見えない。
俺はAに掴まれた腕を自分の左手に持ち直し、Aを連れてBのいた方へソロソロと歩き出した。
なるべく音を立てないように、そしてAを驚かせないように。
暗すぎて意思の疎通ができないんだ。
誰かがパニックになったら終わりだと思った。
どこにいるか全くわからないので、左手にAの腕を持ったまま、右手を手前に伸ばして左右にゆっくり振りながら進んだ。
すると指先が急に固いものに当たり、心臓がボンっと音を立てた。
手に触れたそれは、手触りから壁だということがわかった。
おかしい、Bのいた方角に歩いてきたのにBがいない。
俺は焦った。さらに壁を折り返してゆっくりと進んだ。だがまた壁に行き着いた。
途方に暮れて泣きそうになった。
『Bどこだ』の一言を何度も飲み込んだ。
どうしていいかわからなくなり、その場に立ち尽くしたままAの腕を強く握った。
すると、今度はAが俺の腕を掴み、ソロソロと歩き出したんだ。
まず、Aは壁際まで行くと、掴んだ俺の腕を壁に触らせた。
そしてそのままゆっくりと壁沿いを移動し、角に着いたら進路を変えてまた壁沿いに歩く。
そうやっていくうちに、前を歩くAがぱたりと止まった。そして俺の腕をぐいっと引っ張ると、何か暖かいものに触れさせた。
それは小刻みに震える人の感触だった。
Bを見つけたと思った。
でもすぐ後に、これは本当にBなのか?という疑問が芽生えた。
よく考えたらAもそうだ。ずっと近くにいたが、実際俺の腕を掴んでいるのはAなのか?
俺は暗闇のせいで、完全に疑心暗鬼に陥っていた。
俺が無言でいると、Aはまた俺の腕を掴み、ソロソロと歩き出した。
俺はゆっくりとついていった。
すると、ほんの僅かだが、視界に光が見えるようになった。
不思議に思っていると、部屋にある隙間から少しだけ月の明かりが入ってきているのが目に入った。
Aはそこへ俺達を連れて行こうとしているのだと思った。
何故気づかなかったのか、今思っても不思議なんだ。
暗闇に目が慣れるというのを聞いたことがあったけど、恐怖に呑まれてそれどころじゃなかった。
ほんとに真っ暗だったんだ。
とにかく、その時俺はその光を見て心の底から救われた気持ちになった。
そしてAに感謝した。
後から聞いたんだが、
A「俺は見えもしなかったし、聞こえもしなかった。なんか引きずってる音は聞こえたんだけどな。
でもそのおかげで、お前達よりは余裕があったのかも」
と言っていた。
大した奴だって思った。
光の下に来ると、Aの反対側の手にBの腕が握られているのが見えた。
月明かりで見えたBの顔は、汗と涙でぐっしょり濡れていた。
何があったのか、何を見たのか、聞くまでもなかった。
夜は昼と違ってすごく静かで、遠くで鈴虫が鳴いていた。
俺達はしばらくそこでじっとしていた。
恥ずかしながら、3人で互いに手を取り合う格好で座った。ちょうど円陣を組む感じで。
あの状態が一番安心できる形だったんだと思う。
そして何より、例え僅かな光でも、相手の姿がそこに確認できるだけで別次元のように感じられたんだ。しばらくそうしていると、とうとう予想していたことが起きた。Aが催したのだ。
生理現象だから絶対に避けられないと思っていた。
Aは自分のズボンのポケットから坊さんに貰った布の袋をゴソゴソと取り出すと、立ち上がって俺達から少し離れた。
静寂の中、Aの出す音が響き渡る。
なんか、まぬけな音に若干気が抜けて、俺もBも顔を見合わせてニヤっとした。
その瞬間だった。
「Bくん」
AB俺『・・・』
一瞬にして体に緊張が走る。
するとまた聞こえた。
俺達がおんどうに入った扉のすぐ外側からだった。
「Bくん」
俺達は声の主が誰か一瞬で分かった。
今朝も聞いた美咲ちゃんの声だった。
「Bくんおにぎり作ってきたよ」
こちらの様子を伺うように、少し間を空けながら喋りかけてくる。
抑揚が全くなく、機械のようなトーンだった。
Bの手にぐっと力が入るのが分かった。
「Bくん」
「・・・」
しばらくの沈黙の後、突然関を切ったように、
「Bくんおにぎり作ってきたよ」
「いらっしゃいませ~」
「おにぎり作ってきたよ」
「Bくん」
「いらっしゃいませ~」
「おにぎり作ってきたよ」
と、同じ言葉を何度も何度も繰り返すようになった。
尋常じゃないと思った。
恐かった。美咲ちゃんの声なのに、すげー恐かった。
坊さんは、おんどうには誰も来ないと俺達に言っていた。
そしてこの無機質な喋り方だ。
扉の外にいるのは、絶対に美咲ちゃんじゃないと思った。
気づくとAが俺達の側に戻り、俺とBの腕を掴んだ。
力が入ってたから、こいつにも聞こえてるんだと思った。
俺達は3人で、おんどうの扉の方を見つめたまま動けなかった。
その間もその声は繰り返し続く。
「いらっしゃいませ~」
「Bくん」
「おにぎり作ってきたよ」
そしてとうとう、扉がガタガタと音を出して揺れ始めた。
おい、ちょ、待て。
扉の向こうのヤツは、扉をこじ開けて入ってくるつもりなんだと思った。
俺は扉が開いたらどうするかを咄嗟に考えた。
全速力で逃げる、坊さんたちは本堂にいるって言ってたからそこまで逃げて・・・おい本堂ってどこだ、とか。
もうここからどうやって逃げるかしか考えてなかった。
やがてそいつは、ガンガンと扉に体当たりするような音を立てだした。無機質な声で喋りながら。
そしてそのまま少しずつ、おんどうの壁に沿って左に移動し始めたんだ。
一定時間そうした後にまた左に移動する。その繰り返しだった。
何してるんだ・・?
不思議に思っていると、俺はあることに気づいた。
俺達のいる壁際には隙間が開いている。
そしてそいつは今そこにゆっくりと向かっている。
もし隙間から中が見えたら?
もし中からアイツの姿が見えたら?
そう考えると居ても立ってもいられなくなり、俺は2人を連れて急いで部屋の中央に移動した。
移動している。ゆっくりと、でも確実に。
心臓の音さえ止まれと思った。
ヤツに気づかれたくない。
いや、ここにいることはもう気づかれているのかもしれないけど。
恐怖で歯がガチガチといい始めた俺は、自分の指を思いっきり噛んだ。
そして俺は、隙間のある場所に差し掛かったそいつを見た。
見えたんだ。月の光に照らされたそいつの顔を、今まで音でしか感じられなかったそいつの姿を。
真っ黒い顔に、細長い白目だけが妙に浮き上がっていた。
そして体当たりだと思っていたあの音は、そいつが頭を壁に打ち付けている音だと知った。
そいつの顔が一瞬壁の隙間から消える。外でのけぞっているんだろう。
そしてその後すぐ、ものすごい勢いで壁にぶち当たるんだ。
壁にぶち当たる瞬間も白目をむき出しにしてるそいつから、俺は目が離せなくなった。
金縛りとは違うんだ、体ブルブル動いてたし。
ただ見たことのない光景に、目を奪われていただけなのかも知れないな。
あの勢いで頭を壁にぶつけながら、それでも淡々と喋り続けるそいつは、完全に生きた人間とはかけ離れていた。
結局、そいつは俺達が見えていなかったのか、
隙間の場所でしばらく頭を打ち付けた後、さらにまた左へ左へと移動していった。
俺の頭の中で残像が音とシンクロし、そいつが外で頭を打ち付けている姿が鮮明に想像できた。
正直なところ、そいつがどれくらいそこに居たのかを俺は全く覚えていない。
残像と現実の区別がつけられない状態だったんだ。
後から聞いた話だと、そいつがいなくなって静まりかえった後、3人ともずっと黙っていたらしい。
Aは警戒したから。
Bは恐怖のため動けなかったから。
そして俺は、残像の中で延長戦が繰り広げられていたから。
そんでAが俺を光の場所へ連れていこうと腕を掴んだ時、体の硬直が半端なくて一瞬死んだと思ったらしい。
本気で死後硬直だと思ったんだって。
BはBで、恐怖で歯を食いしばりすぎて歯茎から血を流してた。
Aだけはやっぱり姿を見ていなかった。
あと、そいつはそこから遠ざかって行く時、カラスのように「ア゛ーっア゛ー」と奇声を発していたらしい。
その声はAだけが聞いていたんだけど。
そいつの2度の襲来によって、その後の俺達の緊張の糸が緩むことはなかった。
ただ、神経を張り巡らせている分、体がついていかなかった。
みんな首を項垂れて、目を合わすことは一切無かった。
Bは催したものをそのまま垂れ流していたが、Aと俺はそれを何とも思わなかった。
あんなに夜が長いと思ったのは生まれて初めてだ。
憔悴しきった顔を見たのも、見せたのも、もちろん人でないものの姿を見たのも。
何もかも鮮明に覚えていて、今も忘れられない。おんどうの隙間から光が差し込んできて、夜が明けたと分かっても、俺達は顔を上げられずそこに座っていた。
雀の鳴き声も、遠くから聞こえる民家の生活音も、すべてが俺の心臓に突き刺さる。
ここから出て生きていけるのか、本気でそう思ったくらいだ。
本格的に太陽の光が中に入りこんできた頃、遠くからこっちに近づいてくる足音が聞こえた。
俺達は完全に身構え体制に入った。
足音はすぐ近くまで来ると、おんどうの裏へ回り入り口の前で止まった。
息を呑んでいると、ガタガタっと音がし、「キィーッ」と音を立てて扉が開いた。
そこに立っていたのは、坊さんだった。
坊さんは俺達の姿を見つけると、一瞬泣きそうな顔をして、「よく、頑張ってくれました」と言った。
あの時の坊さんの目は、俺一生忘れないと思う。
本当に本当に優しい目だった。
俺は不覚にも腰を抜かしていた。
そして、いい年こいてわんわん泣いた。
坊さんは、俺達の汗と尿まみれのおんどうの中に迷わず入って来て、そして俺達の肩を一人一人抱いた。
その時坊さんの僧衣?から、なんか懐かしい線香の香りがして、ああ、俺達、生きてるって心の底から思った。
そこでまた俺子供のように泣いた。しばらくしても立ち上がれない俺を見て、坊さんはおっさんを呼んできてくれた。
そして2人に肩を抱えられながら、前日に居た一軒家に向かった。
途中、行く時に見た大きな寺の横を通ったんだが、その時俺達3人は叫び声を聞いた。
低く、そして急に高くなって叫ぶ人の声だった。
家の玄関に着くと耳元でAが囁いた。
A「さっきのあれ、女将さんの声じゃね?」
まさかと思ったが、確かに女将さんの声に聞こえなくもなかった。
だが俺はそれどころじゃないほど疲れていたわけで。
早く家に上げて欲しかったんだが、玄関に出てきた女の人がすげー不快そうに俺達を見下しながら、
「すぐお風呂入って」って言うんだわ。
まーしょうがない。だって俺達有り得んくらい臭かったしね。
そして俺達は3人仲良く風呂に入った。
まあ怖かった。いきなり一人になる勇気はさすがになかった。風呂を上がると見覚えのある座敷に通され、そこに3枚の布団が敷いてあった。『まず寝ろ』ということらしかった。
ここは安全だという気持ちが自分の中にあったし、極限に疲れていたせいもあった。
というか、理屈よりまず先に体が動いて、俺達は布団に顔を埋めてそのまま泥のように眠った。
俺は眠りに入る中で、まったくもってどうでもいいことを思った。
起きたらあいつらに、俺達が帰るって電話しなきゃな。
旅行の準備満タンでスタンバイする友達2人は、俺達が今こうして死にそうな思いをしていたことを知らない。
もちろん、旅行計画がオジャンになることも。
そういえば、おんどうから出る時俺はBに聞いたんだ。
俺「B、もう、見えないよな?」
するとBは確かな口調で答えた。
B「ああ、見えない。助かったんだ。ありがとう」
おれはその最後の一言を聞いて、Bが小便を垂らしたことは内緒にしておいてやろうと思った。
俺達は助かったんだ。その事実だけで十分だった。その後目を覚ました俺達は、事の真相を坊さんに聞かされることになる。
そして、人間の本当の怖さと、信念の強さがもたらした怪奇的な現実を知るんだ。
Bの見たもの、俺の見たもの、Aの聞いたもの。
それを全て知って、俺達は再び逃げ出す決心をする。今まで読んでくれた人たち、本当にありがとう。
自分でもこんな長文になるとは思ってもなかった。
沢山の期待がある分、それに沿えない結果だったかもしれないけど、
話を湾曲させたくなかったからそのまま書かせてもらった。
長すぎるのもなんなんで、一応ここで完結にしておく。
これから先は、事の真相を書くんで、本当に気になる人だけ読んでくれ。
ここまでで十分だって人は、またいつか~
原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2009/08/18 19:18あの後、俺達は死んだように眠り、坊さんの声で目を覚ました。
坊「皆さん、起きれますか?」
特別寝起きが悪いAをいつものように叩き起こし、俺達は坊さんの前に3人正座した。
坊「皆さん、昨日は本当によく頑張ってくれました。無事、憑き祓いを終えることができました」
そう言って坊さんは優しく笑った。
俺達はその言葉に何と言っていいか分からず、曖昧な笑顔を坊さんに向けた。
聞きたいことは山ほどあったのに、何も言い出せなかった。
すると坊さんは俺達の心中を察したのか、
坊「あなたたちには、全てお話しなくてはなりませんね。お見せしたい物があります」と言って立ち上がった。
坊さんは家を出ると、俺達を連れて寺の方に向かった。石段を上る途中、Bはキョロキョロと辺りを警戒する仕草を見せた。
それにつられて俺も、昨日見たアイツの姿を思い出して同じ行動を取った。
それに気づいた坊さんは俺達に聞いた。
坊「もう大丈夫のはずです。どうですか?」
B「大丈夫・・何も見えません」
俺「俺も平気です」
その返事を聞くと、坊さんはにっこりと笑った。大きな寺に着くと、ここが本堂だと言われた。
坊さんの後ろに続いて寺の横にある勝手口から中に入り、さっきまで居た座敷とさほど変わらない部屋に通された。
坊さんは俺達にここで少し待つように言うと、部屋を出て行った。
Bは落ち着かないのか貧乏揺すりを始めた。
暫くすると、坊さんは小さな木箱を手に戻って来た。
そして俺達の対面に腰を下ろすと、「今回の事の発端をお見せしますね」と言って箱を開けた。
3人で首を伸ばして箱の中を覗き込んだ。
そこには、キクラゲがカサカサに乾燥したような、黒く小さい物体が綿にくるまれていた。
AB俺「何だこれ?」
よく見てみるが分からない。
だがなんとなく、どっかで見たことのある物だと思った。
俺は暫く考え、咄嗟に思い出した。
昔、俺がまだ小さい頃、母親がタンスの引き出しから、大事そうに木の箱を持ってきたことがあった。
そして箱の中身を俺に見せるんだ。すげー嬉しそうに。
箱の中には綿にくるまれた黒くて小さな物体があって、俺はそれが何か分からないから母親に尋ねたんだ。
そしたら母親は言ったんだ。
「これはねぇ、臍(へそ)の緒って言うんだよ。お母さんと、○○が繋がってた証」
俺は子供心に、なんでこんなの大事そうにしてるんだろ?って思った。
目の前にあるその物体は、あの時に見た臍の緒に似ているんだと思った。
A「これ何ですか?」
坊「これは、臍の緒ですよ」
というか、似てるもなにも臍の緒だった。
A「俺初めて見たかも」
B「おれ見たことある」
俺「俺も」
坊「みなさん親御さんに見せてもらったのでしょう。こういうものは、大切に取っておく方が多いですから」
この臍の緒も、それはそれは大切に保管されていたものなのです」
俺たちは黙って坊さんの話を聞いていた。
坊「母親の胎内では、親と子は臍の緒で繋がっております。
今ではその絆や出産の記念にと、それを大切にする方が多いですが、
臍の緒には色々な言い伝えがあり、昔はそれを信じる者も多かったのです」
B「言い伝え?」
坊「そうです。昔の人はそういう言い伝えを非常に大切にしておりました。今となっては迷信として語られるだけですが」
そう前置きをして、坊さんは臍の緒に関する言い伝えを教えてくれた。主に『子を守る』という意味を持っているが、解釈は様々。
『子が九死に一生の大病を患った際に煎じて飲ませると命が助かる』とか、
『子に持たせるとその子を命の危険から守る』というのがあって、
親が子供を想う気持ちが込められているところでは共通しているらしい。
俺たちはその話を聞いて、「へぇ~」なんて間抜けな返事をしていた。
坊さんは一息入れると、微かに口元を上げて言った。
坊「ひとつ、この土地の昔話をしてもよろしいですか?今回の事に関わるお話として聞いいただきたいのです」
俺達は坊さんに頷いた。
ここから坊さんの話が始まる。
結構長くて、正確には覚えてない。所々抜け落ち部分があるかも。坊「この土地に住む者も、臍の緒に纏わる言い伝えを深く信じておりました。
土地柄、ここでは昔から、漁を生業として生活する者が多くおりました。
漁師の家に子が生まれると、その子は物心がつく頃から、親と共に海に出るようになります。
ここでは、それがごく普通のしきたりだったようです。
漁は危険との隣り合わせであり、我が子の帰りを待つ母親の気持ちは、私には察するに余りありますが、
それは深く辛いものだったのでしょう。
母親達はいつしか、我が子に御守りとして、臍の緒を持たせるようになります。
海での危険から命を守ってくれるように、
そして行方のわからなくなったわが子が、自分の元へと帰ってこれるようにと」
俺「帰ってくる?」
俺は思わず口を挟んだ。
坊「そうです。まだ体の小さな子は、波にさらわれることも多かったと聞きます。
行方の分からなくなった子は、何日もすると死亡したことと見なされます。
しかし、突然我が子を失った母親は、その現実を受け入れることができず、
何日も何日もその帰りを待ち続けるのだそうです。
そうしていつからか、子に持たせる臍の緒には、
『生前に自分と子が繋がっていたように、子がどこにいようとも自分の元へ帰ってこれるように』と、
命綱の役割としての意味を孕むようになったのだと言います」
皮肉な話だと思った。
本来海の危険から身を守る御守りとしての役割を成すものが、いざ危険が起きたときの命綱としての意味も持ってる。
母親はどんな気持ちで子どもを送り出してたんだろうな。
坊「実際、臍の緒を持たせていた子が行方不明になり、無事に帰ってくることはなかったそうです。
しかしある日、『子供が帰ってきた』と涙を流して喜ぶ、1人の母親が現れます。
これを聞いた周囲の者はその話を信用せず、とうとう気が狂ってしまったかと哀れみさえ抱いたそうです。
何故なら、その母親が海で子を失ったのは、3年も前のことだったからです」
B「どこかに流れついて、今まで生きてたとかじゃないんですか?」
坊「そうですね。始めはそう思った者もいたようです。
そして母親に、子供の姿を見せてほしいと言い出した者もいたそうなのです」
B「それで?」
坊「母親はその者に言ったそうです。『もう少ししたら見せられるから待っていてくれ』と」
どういう意味だ?
帰って来たら見せられるはずじゃないのか?
俺はこの時、理由もなく鳥肌が立った。
坊「もちろん、その話を聞いて村の者は不振に思ったそうですが、
子を亡くしてからずっと伏せっていた母親を見てきた手前、強く言うことができず、
そのまま引き下がるしかできなかったそうです。
しかし次の日、同じ事を言って喜ぶ別の母親が現れるのです。
そしてその母親も、子の姿を見せることはまだできないという旨の話をする。
村の者達は困惑し始めます。
前日の母親は既に夫が他界し、本当のところを確かめる術が無かったのですが、この別の母親には夫がおりました。
そこで村の者達は、この夫に真相を確かめるべく、話を聞くことになったそうです。
するとその夫は言ったそうです。『そんな話は知らない』と。
母親の喜びとは反対に、父親はその事実を全く知らなかったのです。
村人達が更に追求しようとすると、『人の家のことに首を突っ込むな』と、ついには怒りだしてしまったそうです」
まあ、そうだよな。
何にせよ周りの人に家の中のことをごちゃごちゃ聞かれたら、いい気はしないだろうななんて思ったりもした。
坊「その後何日かすると、ある村の者が、
最初に子が戻ってきたと言い出した母親が、昨晩子共を連れて海辺を歩く姿を見たと言い出します。
暗くてあまり良く見えなかったが、手を繋ぎ隣にいる子供に話しかけるその姿は、本当に幸せそうだったと。
この話を聞いた村の者達は皆、これまでの非を詫びようと、そして子が戻ってきたことを心から祝福しようと、
母親の家に訪ねに行くことにしたそうです。
家に着くと、中から満面の笑顔で母親が顔を出したそうです。
村の者達はその日来た理由を告げ、何人かは頭を下げたそうです。
すると母親は、『何も気にしていません。この子が戻って来た、それだけで幸せです』と言いながら、
扉に隠れてしまっていた我が子の手を引き寄せ、皆の前に見せたそうです。
その瞬間、村の者達はその場で凍りついたそうです」
AB俺「・・・」
坊「その子の肌は、全身が青紫色だったそうです。
そして体はあり得ない程に膨らみ、腫れ上がった瞼の隙間から白目が覗き、
辛うじて見える黒目は、左右別々の方向を向いていたそうです。
そして口から何か泡のようなものを吹きながら、母親の話しかける声に寄生を発していたそうです。
それはまるで、カラスの鳴き声のようだったと聞きます。
村の者達は、子供の奇声に優しく笑いかけ、髪の抜け落ちた頭を愛おしそうに撫でる母親の姿を見て、
恐怖で皆その場から逃げ出してしまったのだそうです。
散り散りに逃げた村の者達はその晩、村の長の家に集まり出します。
何か得体の知れないものを見た恐怖は誰一人収まらず、それを聞いた村の長は自分の手には負えないと判断し、
皆を連れてある住職の元へ行くことにします。
その住職というのが、私のご先祖に当たる人物らしいのですが・・・
相談を受けた住職は事の重大さを悟り、すぐさま母親の元に向かいます。
そして母親の横に連れられた子を見るや、母親を家から引きずり出し、寺へと連れて帰ったそうです。
その間も、その子は住職と母親の後をずっと付いてきて、奇声を発していたのだとか。
寺に着くと、まず結界を強く張った一室に母親を入れ、話を聞こうとします。
しかし、一瞬でも子と離れた母親は、その不安からかまともに話をできる状態ではなかったと聞きます。
ついには子供を返せと、住職に向かってものすごい剣幕で怒鳴り散らしたのだそうです」
A「それでどうなったんですか?」
坊「子を想う母は強い。
住職が本気で押さえ込もうとしたその力を跳ね飛ばし、そのまま寺を飛び出してしまったのだそうです」
坊さんは少し情けなそうな顔をしてそう言った。
坊「その後、村の者と従者を何人か連れて、母親の家に行きましたが、そこに母と子の姿はなかったそうです。
そして家の中には、どこのものかわからない札が至る所に貼り付けられ、
部屋の片隅には、腐った残飯が盛られ異臭が立ち込めていのだとか」
この時俺は思った。あの旅館の2階で見たものと同じだと。
坊「そこに居た皆は同じことを思いました。母親は子を失った悲しみから、ここで何かしらの儀を行っていたのだと。
そして信じ難いことだが、その産物としてあのようなモノが生まれたのだと。
その想いを悟った村の者達は、母親の行方を村一丸になって捜索します。
住職はすぐさま従者を連れ、もう一人の母親の家に向かいますが、こちらも時既に遅しの状態だったそうです。
得体の知れないモノに語りかけ、子の名前を呼ぶ母親に恐怖する父親。
その光景を見た住職は、経を唱えながらそのモノに近づこうとしますが、
子を守る母親は住職に白目を向き、奇声を発しながら威嚇してきたのだそうです」
現実味のない話だったのに、なぜかすごく汗ばんだ。
坊「村の者は恐れ、一歩も近寄れなかったと言います。
しかし住職とその従者は、臆することなくその母親とそのモノに近づき、興奮する母親を取り押さえ寺へ連れ帰ります。
暴れる母親を抱えながら、背後から付いて来るモノに経を唱え、道に塩を盛りながら少しずつ進んだのだそうです。
寺に着くと、住職は母親をおんどうへ連れて行き、体を縛りその中に閉じ込めたのだそうです」
A「そんなことを・・・」
Aが哀れみの声を出した。
坊「仕方がなかったのです。親と子を離すのが先決だった、そうしなければ何もできなかったのでしょう」
坊さんがしたことではないが、Aは坊さんから顔を背けた。
少しの沈黙の後、坊さんは続けた。
坊「母親の体には自害を防ぐための処置が施されたようですが、その詳細は分かりません。
その後、おんどうの周りに注連縄を巻きつけ、住職達はその周りを取り囲むようにして座り、経を唱え始めたそうです。
中から母親の呻き声が聞こえましたが、その声が子に気づかれぬよう、全員で大声を張り上げながら経を唱えたそうです」
住職達が必死に経を唱える中、いよいよ子の姿が現れます。
子は親を探し、おんどうの周りをぐるぐると回り始めます。
何を以って親の場所を捜すのか、果たして経が役目を成すのかもわからない状態で、
とにかく住職達は必死に経を唱えたのです」
そこで坊さんは一息ついた。
B「それで、どうなったんですか?」
Bの声は恐る恐るといった感じだった。
坊「おんどうの周りを回っていたそのモノは、次第に歩くことを困難とし、四足歩行を始めたそうです。
その後、四肢の関節を大きく曲げ、蜘蛛のように地を這い回ったそうです。
それはまるで、人間の退化を見ているようだったと。
その後、なにやら呻き声を上げたかと思うと、
そのモノの四肢は失われ、芋虫のような形態でそこに転がっていたのだとか。
そしてそのモノは、夜が明けるにつれて小さくすぼみ、最終的に残ったのが、臍の緒だったのです」
原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2009/08/18 19:18俺は坊さんの話に聞き入っていた。
まるで自分達の話に毛が生えて、昔話として語られているような感覚だった。
するとAが聞いたんだ。
A「え、もしかしてその臍の緒って・・・」
すると坊さんは静かに答えた。
坊「今朝、おんどう奥の岩の上に転がっていたものです」
B「マジかよ・・」
Bは呆然として呟いた。
俺「なんで?なんで俺達なんですか?」
坊「詳しくはわかりません。
この寺には、代々の住職達の手記が残されていますが、
母親でない者にこのような現象が起きた事例は、見当たりませんでした。
何より、肝心の母親の行った儀式について、これがまだ謎に包まれたままなのです」
B「母親に聞かなかったんですか?」
坊「聞かなかったのではなく、聞けなかったのです」
ポカンとしていると坊さんはまた話し始めた。
坊「住職達がおんどうを開け中を確認すると、疲れ果ててぐったりした母親がいたそうです。
子を求めて一晩中叫んでいたのでしょう。
すぐさま母親を外に運びだし手当てをしましたが、目を覚ました時には、母親は完全に正気を失っておりました。
二度も子を失った悲しみからなのか、はたまた何か禍々しいモノの所為なのか、それも分かりかねますが。
そして村の者が捜索していたもう一人の母親ですが、
一晩経を読み上げ疲れ果てた住職達の元に、発見の知らせが届いたそうです。
近海の岸辺に、遺体となって打ち上げられていたと。
母親は体中を何かに食い破られており、それでいて顔はとても幸せそうだったとあります。
何が起きたのかはわかりませんが、住職の手記にはこうありました。
『子に食われる母親の最後は、完全な笑顔だった』と」
信じられないような話なんだが、俺達は坊さんの話す言葉一つ一つをそのまま飲み込んだ。
坊「遺体となって見つかった母親の家は、村の者達による話し合いで取り壊されることとなり、
その際に家の中から、母親の書いたものらしいメモが見つかったそうです」
そう言って坊さんは、そのメモの内容を俺達に説明してくれた。
簡単に言うと、儀式を始めてからの我が子を記録した、成長記録のようなものだったそうだ。
どんな風に書かれていたのかは憶測でしかないんだが、内容は覚えているので以下に書く。わかりづらいかも。○月?日 堂の作成を開始する
×月?日 変化なし・・・
△月?日 △△(子の名前)が帰ってくる
△月?日 移動が困難な状態
△月?日 手足が生える
△月?日 はいはいを始める
△月?日 四つ足で動き回る
△月?日 言葉を発する
△月?日 立つこの成長記録に、母親の心情がビッシリと書き連ねてあったらしい。
ちなみに、もう一人の母親は、屋根裏に堂を作っていたらしく、父親はその存在に全く気づいていなかったのだそうだ。坊「私もすべてを理解しているとは言えませんが、この母親の成長記録と住職の手記を見比べると、
そのモノは、自分の成長した過程を遡るようにして、退化していったと考えられませんか?」
確かにその通りだと思った。
そして坊さんは、それ以上の言及を避けるように話を続けた。
坊「これ以降手記には非常に稀ですが、同じような事象の記述が見られます。
だがその全てに、母親達がいつどのようにしてこの儀を知るのかが、明記されていないのです。
それは全ての母親が、命を落とす、若しくは、話すこともままならない状態になってしまったことを、意味しているのです」
坊さんは、早期に発見できないことを悔やんでいると言った。
坊「今回の現象は初めてのことで、私自身もとても戸惑っているのです。
何故母親ではないあなたが、そのモノを見つけてしまったのか。
子の成長は母親にしか分からず、共に生活する者にも、それを確認することはできないはずなのです」
そんなデタラメな話有りなのか?と思った。
そしてBが、話の核心を知ろうと恐る恐る質問した。
B「あの、母親って、・・・もしかして女将さんなんですか?」
坊さんは少し黙り、答えた。
坊「その通りです。
真樹子さんは、この村出身の者ではありません。○○さん(旦那さんの名前)に嫁ぎこの村にやってきました。
息子を一人儲け、非常に仲の良い家族でした」
そう言って話してくれた坊さんの話の内容は、大方予想が付いていたものだった。
女将さんの一人息子は、数年前のある日海で行方不明になったそうだ。
大規模な捜索もされたが、結局行方は分からなかったらしい。
悲しみに暮れた女将さんは、周囲から慰めを受け、少しずつだが元気を取り戻していったそうだ。
旅館もそれなりに繁盛し、周囲も事件のことを忘れかけた頃、急に旅館が2階部分を閉鎖することになったんだって。
周りは不振に思ったが、そこまで首を突っ込むことでもないと、別段気にすることはなかったそうだ。
そしてこの結果だ。
女将さんはどこから情報を得たのか不明だが、あの2階へ続く階段に堂を作り上げ、そこで儀式を行っていた。
そしてその産物が俺達に憑いてきたという訳だが、ここがこれまでの事例と違うのだと坊さんは言った。
本来儀式を行った女将さんに憑くはずの子が、第3者の俺達に憑いたんだ。
考えられる違いは、女将さんは息子に臍の緒を持たせていなかったということ。
そこの村の人達は、昔からの風習で未だに続けている人もいるらしいが、女将さんはその風習すら知らなかった。
これは旦那さんが証言していたらしい。
そして妙な話だが、旅館の2階を閉鎖したというのに、バイトを3人も雇った。
旦那さんも初めは反対したそうだが、
女将さんに「息子が恋しい。同年代くらいの子達がいれば、息子が帰ってきたように思える」と泣きつかれ、
渋々承知したそうなんだ。
これは坊さんの憶測なんだが、
女将さんは初めから、帰ってきた息子が俺達を親として憑いていくことを知っていたんではないか、ということだった。
結局これらのことを俺達に話した後、坊さんはこう言った。
坊「あなた達をあのおんどうに残したこと、本当に申し訳なく思います。
しかし私は、真樹子さんとあなた達の両方を救わなければならなかった。
あなた達がここにいる間、私達は真樹子さんを本堂で縛り、先代が行ったように経を読み上げました。
あのモノがおんどうへ行くのか、本堂へ来るのか分からなかったのです」
つまり、俺達に憑いてきてはいるが、これまでの事例からいくと母親の女将さんにも危険が及ぶと、
坊さんはそう読んでいたってことだ。
俺は別に坊さんが謝ることじゃないと思った。
それにこの人は命の恩人だろ?と思ってBを見ると、肩を震わせながら坊さんを睨み付けて言ったんだ。
B「納得いかない。自分の息子が帰ってくりゃ人の命なんてどーでもいいのか?」
坊「・・・」
B「全部吐かせろよ!なんでこんな目に遭わせたのか、それができないなら俺が直接会って聞いてやる」
旦那さんだって知ってたんだろ?それなのに何で言わなかったんだ?」
坊「○○さんは知らなかったのです」
B「嘘つくな。知ってるようなこと言ってたんだ」
坊「この話は、この土地には深く根付いています。○○さんが知っていたのは伝承としてでしょう」
坊さんが嘘を吐いているようには見えなかった。
だがBの興奮は収まりきらなかったんだ。
B「ふざけんじゃねーぞ。早く会わせろ。あいつらに会わせろよ!」
俺達はBを取り押さえるのに必死だった。
坊さんは微動だにせず、Bの怒鳴り声を静かに聞いていた。
そして、
坊「この話をすると決めた時点で、あなた達には全てをお見せしようと思っておりました。
真樹子さんのいる場所へ案内します」
と言って立ち上がったんだ。坊さんの後を付いてしばらく歩いた。
本堂の中にいるかと思っていたんだが、渡り廊下みたいなのを渡って離れのような場所に通された。
近づくにつれて、なにやら呻き声と何人かの経を唱える声が聞こえてきた。
そしてその声と一緒に、バタンッバタンという音が聞こえた。かなりでかかった。
離れの扉の前に立つと、その音はもうすぐそこで鳴っていて、中で何が起きているのかと俺は内心びくびくしていた。
そして坊さんが離れの扉を開けると、そこには女将さん一人と、それを取り囲む坊さん達が居た。
俺達は全員、言葉を発することができなかった。
女将さんはそこに居たというか・・・なんか跳ねてた。エビみたいに。うまく説明できないんだが。
寝た状態で、畳の上で、はんぺんみたいに体をしならせて、ビタンビタンと跳ねていたんだ。
人間のあんな動きを俺は初めてみた。
そして時折、苦しそうにうめき声を上げるんだ。
俺は怖くて女将さんの顔が見れなかった。
正直、前の晩とは違う、でもそれと同等の恐怖を感じた。
呆然とする俺達に坊さんは言った。
坊「この状態が、今朝から収まらないのです」
するとAが耐え切れなくなり、「俺、ここにいるのキツイです」と言ったので、一旦外に出ることになった。
音を聞くことさえ辛かった。
つい昨日の朝に見た女将さんの姿とは、まるで別人の様になっていた。そこから少し離れたところで、俺達は坊さんに尋ねた。憑き物の祓いは成功したのではないかと。
坊「確かに、あなた達を親と思い憑いてきたものは、祓うことができたのだと思います。
現にあなた達がいて、ここに臍の緒がある。しかし・・・」
すると急にBが言ったんだ。
B「そうか・・・俺が見たのは、1つじゃなかったんだ」
初めは何のことを言ってるのかわからなかったんだが、そのうちに俺もピンときた。
Bはあの時、2階の階段で複数の影を見たと言っていなかったか?
坊「1つではないのですか?」
坊さんは驚いたように聞き返し、Bがそうだと答えるのを見ると、また少し黙った。
そして暫く考え込んでいたかと思うと、急に何かを思い出したような顔をして、俺達に言ったんだ。
坊「あなた達は鳥居の家に行ってください。そしてあの部屋を一歩も出ないでください。後で人を行かせます」
ポカンとする俺達を置いて、坊さんはそのまま女将さんのいる離れの方に走って行った。
俺達は急に置いてけぼりを食らい、暫く無言で突っ立っていた。
すると離れの方から、複数の坊さんが大きな布に包まった物体を運び出しているのが見えた。
その布の中身がうねうねと動いて、時折痙攣しているように見えた。
あの中にいるのは女将さんだと全員が思った。
そのままおんどうの方に運ばれていく様を、俺達は呆然と見ていたんだ。
ふとお互い顔を見合わせると、途端に怖くなり、俺たちは早足で家に向かった。
そこからは、説明することが何も無いほど普通だった。
家に行って暫くすると、別の坊さんがやって来て「ここで一晩過ごすように」と言われた。
そしてその坊さんは俺たちの部屋に残り、微妙な雰囲気の中4人で朝を迎えたというわけ。次の朝、早めに目が覚めた俺達がのん気にめざにゅ~を見ていると、坊さんがやって来た。
俺達は坊さんの前に並んで話を聞いた。
坊さんは俺達の憑き祓いは完全に終わったと言った。
昨日言っていた通り、俺達に憑いてきたモノは一匹で、それは退化を遂げて消滅したのを確認したんだと。
俺達はそれを聞いて安堵した。
しかし坊さんはこう続けた。
女将さんを救うことができなかったと。
泣きそうなのか怒っているのか、なんとも言えない表情を浮かべてそう言った。
死んだのかと聞くと、そうではないと言うんだ。
俺はその言葉から、女将さんが跳ね回っている姿を思い出した。
ずっとあの状態なのか・・?
恐る恐るそれを聞くと、坊さんは苦い顔をしただけで、肯定も否定もしなかった。
女将さんの今の状態は、憑きものを祓うとかそういう次元の話ではなく、何かもっと別のものに起因してるんだって。
詳しくは話してくれなかったんだが、女将さんが行った儀式は、この地に伝わる『子を呼び戻す儀』と似て非なるものらしい。
どこかでこの儀の存在と方法を知った女将さんは、息子を失った悲しみからこれを実行しようと試みる。
だが肝心の臍の緒は自分の手元にあったわけだ。
こっからは坊さんの憶測なんだが、女将さんはこれを試行錯誤しながら、完成系に繋げたんじゃないかということだった。
自分の信念の元に。
そしてそこから得た結果は、本来のものとは別のものだった。
堂には複数のモノがおり、そこに息子さんがいたかは分からないと。
坊さんが言ってた。
この儀の結末は、非常に残酷なものでしかないんだと。
それを重々承知の上で、母親達は時にその禁断の領域に足を踏み入れてしまう。
子を失う悲しみがどれ程のものなのか、我々には推し量ることしかできないが、
心に穴の開いた母親がそこを拠り所としてしまうのは、いつの時代にもあり得ることなのではないかと。
Bは女将さんのこれからを執拗に聞いていたが、坊さんは何も分からないの一点張りで、
俺たちは完全に煙に巻かれた状態だった。俺達が坊さんと話終えると、部屋に旦那さんが入ってきた。
俺は正直ぎょっとした。
顔が土色になって、明らかにやつれ切った顔をしてたんだ。
そして、俺達の前に来ると泣きながら謝って来た。
泣きすぎて何を言ってるのかは全部聞き取れなかったんだけど、俺達は旦那さんのその姿を見て誰も何も言えなかった。
俺達に申し訳ないことをしたと泣いているのか、それとも女将さんの招いた結果を思って泣いているのか、
どっちだったんだろうな。今となってはわかんねーな。
その後、俺達は何度も坊さんに確認した。
これ以降俺達の身には何も起きないのか?と。
すると坊さんは、困ったような顔をしながら「大丈夫」だと言った。その後、坊さんの所にタクシーを呼んでもらって俺達は帰ることになった。
一応、昨日の朝俺を家まで運んでくれたおっさんが、駅まで同乗してくれることになったんだが。
このおっさんがやたら喋る人で、それまでの出来事で気が沈んでる俺達の空気を一切読まずに、一人で喋くりまくるんだ。
そんでこのおっさんは、「それにしても、子が親を食うなんて、蜘蛛みたいな話だよなぁ」と言ったんだ。
俺達は胸糞悪くなって黙ってたんだけど、おっさんは一人で続けた。
「お前達、ここで聞いた儀法は試すんじゃねーぞ。自己責任だぞ」
そう言って笑うんだ。
俺達の気持ちを和らげようとして言ってるのか、本気でアホなのかわかんなかったけど、一つ確かなことがあった。
俺達は、坊さんに真実を隠されて教えられたんだ。
儀の方法は、その結果と一緒にこの地に伝わってるんだ。
このおっさんが知ってて坊さんが知らないはずないだろ?
そう思うと、これだけの体験をさせといて、結局は大事なところを隠して話されたことにすげーショックを受けた。
坊さんを信用していた分、なんか怒りにも似たものが湧き上がってきたんだ。
タクシーが駅に着くと、おっさんが金を払うと言ったが俺達は断った。
早くこの場所から逃げ出したい、その一心だった。
坊さんが「大丈夫」と言った一言も、全部嘘に思えてきた。
それでも俺達には、あの寺に戻る勇気はなくて、帰りの電車をただただ無言で待つことしかできなかったんだ。その後、帰って来てからはなんともない。
まあ、なんともないからここに書き込めてるわけだけど。
「もう2度とあの場所へは行かない」
3人で話してると必ず1回はその言葉が出てくるくらい、俺達にとってトラウマになった出来事だったんだ。
あと、Bはあれから蜘蛛を見るのがどうもダメらしい。成長過程のアイツの姿を見てるからね。
俺はと言うと、今は普通に社会人やってます。若干暗闇が苦手になったくらい。
人間のど元過ぎれば熱さ忘れるって、あながち間違いじゃないかもしれないな。本当の本当に後日談なんだが、その話を残りの友達2人に話したんだ。
2人とも俺達3人の様子を見て、一応信じてはくれたんだけど。
でもそいつらその後に、興味半分で旅館に電話を掛けてみたんだって。(最低だろ)
そしたら、電話に出たのは普通のおばさんだったらしい。
そいつら俺達に言うんだよ。女将さんか確認しろって。そんで、後ろでカラスが異様に鳴いてるって言うんだ。
絶対無理だと思った。女将さんが無事でも無事じゃなくても、俺にはその後を知る勇気なんか出なかった。タラタラ書いて正直すまなかった。
真相といっても的を得ない内容だったかもしれないが、ご勘弁願います。
これがありのままっす。オチなしですが。
長々読んでくれてどうもありがとう。
📚出典と派生・類似伝承
本作の原作は、2009年に怖い話投稿サイト「ホラーテラー」に投稿されたネット怪談である。その後、「2ちゃんねる」の「洒落にならない怖い話」スレッドに再投稿され、ネット上で広く拡散された。初出の正確な日時や投稿者は不明だが、2000年代中頃にはすでに「長編ネット怪談の名作」として知られ、『きさらぎ駅』や『八尺様』と並ぶ現代怪談の代表格とされている。
この怪談には、日本各地の民俗的伝承や禁忌、離島に伝わる「外から来た者が触れてはならない儀式」「閉ざされた信仰体系」といったテーマが色濃く反映されている。特に、「人を神に捧げるような習俗」や「封印された存在を信仰する文化」は、日本の各地に存在する民間伝承とも共通点が多い。
類似する物語としては、以下が挙げられる:
- 『コトリバコ』:呪いの箱にまつわる禁忌の風習と、現代人が知らずにそれに触れてしまう構造が共通。
- 『ひとりかくれんぼ』:現代の若者が軽い気持ちで異界のルールを破るという構図が近い。
- 『神隠し』や『山の神信仰』系の伝承:異界との境界が曖昧な地方や離島に特有の怪異。
このように、『リゾートバイト』は単なる創作怪談という枠を超え、日本の土着信仰や伝承との接点を感じさせる作品となっている。
🎬メディア登場・現代への影響
『リゾートバイト』はネット発の怪談として広く認知されており、その知名度の高さからさまざまなメディアで取り上げられてきた。特に注目されたのは、2023年公開の映画『リゾートバイト』である。本作は原作怪談の構成を基にしながらも、新たなキャラクターや展開を加え、現代ホラーとして再構築された。
映画では、ネット怪談ならではの「語り手の視点」や「じわじわと迫る異様な日常」、そして“知ってしまった者”が逃れられない運命を巧みに描き、若年層を中心に話題となった。また、TikTokやYouTubeなどのショート動画プラットフォームでも、本怪談を題材にした朗読や考察動画が数多く投稿され、都市伝説系コンテンツの中でも高い再生数を記録している。
さらに、2020年代以降のホラー作品においては、『リゾートバイト』の影響を受けたと見られる「閉鎖的な共同体」「儀式の継承」「禁忌を破る若者たち」という構図が増えており、ネット怪談が日本のホラージャンルに与えた影響の大きさを物語っている。
2023年には、永江二朗監督によって映画化された。主演は伊原六花が務め、藤原大祐、秋田汐梨、松浦祐也らが共演している。映画では、リゾート地の旅館でアルバイトをする大学生たちが、禁忌の扉を開けてしまい、次々と怪異に巻き込まれていく様子が描かれている。
🔍考察と文化的背景
『リゾートバイト』の物語は、現代社会における若者たちの不安や孤独、禁断の興味が恐怖として具現化されている点が特徴的である。このネット怪談は、「未知の世界」と「日常の一部」が交錯する瞬間に焦点を当てており、その恐怖の本質を、現代に生きる若者たちが持つ「未知に対する興味」と「インターネットで知った情報への過信」に結びつけて考察することができる。
物語における島の旅館という閉鎖的な空間は、現代社会における「情報の隔離」や「疎外感」を象徴している。このような場所では、外部との接触が制限され、何か異常な事態があったとしても、それに気づくことが難しい。この環境は、「自分が知っている世界」から外れた事柄に触れることで生まれる恐怖を強調している。
また、物語内で描かれる儀式や異世界的な存在は、しばしば都市伝説や地方の伝承に根ざした恐怖がベースになっている。日本の伝承や民間信仰では、「神聖な場所や人物に触れてはいけない」という教訓が存在し、その禁忌を犯すことが物語の中で命運を分ける。こうした要素は、現代の若者が持つ「オカルトや都市伝説に対する関心」と密接に関係しており、ネットを通じて広まる不安や恐怖の表れでもある。
さらに、ネット怪談が広く受け入れられ、現代の若者文化に影響を与えている背景には、インターネットの普及と匿名性の高さがある。実際の出来事かどうかを疑うことなく、誰でも簡単に情報を発信できる環境は、「現実と虚構の境界が曖昧になる」という恐怖を増幅させる要因となっている。
🗺️出現地点
物語の舞台は、リゾート地の旅館であるが、具体的な地名は明示されていない。しかし、映画版では、離島の旅館が舞台となっており、自然豊かな場所であることが描かれている。
📎関連リンク・参考資料
💬編集者コメント・考察
『リゾートバイト』は、一見無害に見えるリゾート地という舞台で展開される恐怖の物語であり、その場所の持つ二重性が物語全体に緊張感を与えている。リゾート地や旅館という空間は、通常は人々が癒しを求めて訪れる場所だが、この物語ではその外見とは裏腹に、隠された恐怖が待ち受けていることが強調されている。こうした設定は、読者に日常の中に潜む異常さを感じさせ、身近に感じる恐怖を描いている点で非常に効果的である。
物語における「儀式」や「人外の存在」といったテーマは、都市伝説や民間信仰に見られる要素を巧みに取り入れている。これらの要素は、実際に存在するかどうかは定かではないものの、どこかで耳にしたことのあるような、非常にリアリティのある恐怖として読者に迫る。特に、閉鎖的なリゾート地で起こる奇怪な出来事が、まるでその場所の持つ歴史や呪いのような存在を感じさせ、恐怖を一層深めている。
また、物語が描く若者たちの「好奇心」とそれに伴う「無知な過信」も一つの重要なテーマである。彼らは異常を感じながらも、それを確かめようとすることで、次第に恐怖の渦に引き込まれていく。この心理描写は、現実世界でもよく見られる「人間の好奇心がもたらす結果」を反映しており、読者に深い共感を呼び起こすとともに、物語への没入感を高める。
本作は、リゾートバイトという一般的にはポジティブなイメージのあるテーマを使いながら、そこに潜むダークな面を掘り下げていくことで、読者に強い印象を残す作品となっている。これからも、こうしたテーマを持つ怪談や都市伝説が多くの読者に愛されることだろう。
🎧 都市伝説好き必見!“聴く怖い話”体験を始めよう【Audible / audiobook.jp 比較】
👣 この記事を読んで、背筋がゾワッとしたあなたへ。
もし“読む”だけでなく、“耳で聴く”怪談体験に興味があるなら――
オーディオブックサービスの【Audible】と【audiobook.jp】が、あなたをさらなる恐怖の世界へ案内してくれる。
イヤホン越しに囁かれる怨念、静寂の中で始まる恐怖体験。
一度聴いたら眠れなくなるかもしれない、人気の怪談朗読が多数ラインナップされている。
- 🔊 Audible(オーディブル)
Amazon提供。毎月1冊無料で、声優や芸人による怪談朗読をフルで聴ける。
『新耳袋』シリーズや、怪談師・ありがとうぁみ氏の朗読なども人気。
- 📚 audiobook.jp
日本発のオーディオブックサービス。月額で怪談やホラー作品が聴き放題。深夜に“連続再生”でじっくり楽しめる。
- 🎁 どちらも無料体験が可能。
まずは1本、深夜にイヤホンで試してみてほしい。文字では味わえない恐怖が、あなたの耳に忍び寄りよる。
🔥 話題の2大オーディオブックで聴ける《怪談・怖い話》作品
- 🔊 Audible(オーディブル):Amazon提供、1冊まるごと“無料”で試せる。プロ声優や芸能人による本格怪談朗読が魅力。
- 📚 audiobook.jp:月額プランで怪談やホラー作品が聴き放題。深夜にじっくり聴く“連続再生”が人気。
| タイトル | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 👻 新耳袋シリーズ | ✅ | ✅ |
| 🧟♂️ 稲川淳二 怪談ナイト | ✅ | ✅ |
| 🏚 事故物件怪談 恐音 | ✅ | ✅ |
| 🏞 廃墟・廃線にまつわる話 | ✅(一部) | ✅(一部) |
| 😨 実話怪談集 | 豊富 | 豊富 |
👇こんな人におすすめ!
- ✅ Audibleは…月1冊じっくり聴きたい人向け
- ✅ audiobook.jpは…いろんな怪談を聴き放題で楽しみたい人向け
🎧 どっちがいい?かんたん比較表
| 比較項目 | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 月額 | ¥1,500(1冊無料+聴き放題対象多数) | ¥1,330〜(聴き放題プラン) |
| 無料体験 | 30日間 | 14日間 |
| 怖い話の充実度 | ◎(稲川淳二/新耳袋ほか) | ◎(人気作+独自配信もあり) |
| アプリ使いやすさ | ○ | ◎(日本語対応に強い) |
| 配信ジャンル | 海外含め多彩 | 国内作品に強い |
🧟♂️ 聴くだけで“現地にいるような”恐怖体験
あなたは、ひとりでこの朗読を最後まで聴ける自信はあるだろうか?
「イヤホン越しに耳元で囁くような声がして、思わず音量を下げた…」
そんなレビューも少なくない、リアルな恐怖がここにある。
- ✅ 急に部屋が寒くなった気がする
- ✅ 背後に気配を感じた
- ✅ イヤホン越しに“もう一人”の声が聞こえる…
そんな体験を、ぜひ以下のリンクから始めてほしい。
🔽 無料で怪談体験を始めるならこちらから
👇どちらも無料で今すぐ試せるので、気になる作品を1本、まずは深夜に“イヤホンで”聴いてみてほしい――恐怖の臨場感がまるで違う。
\ 30日間無料体験キャンペーン実施中/
※Audibleは無料期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
\ 14日間無料体験キャンペーン実施中/
※audiobookは無料聴き放題プランの期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
👇こちらの記事も要チェック!
【もっと読む】↓