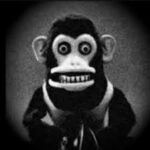🧠パンドラ[禁后]とは?
「禁后(パンドラ)」とは、2009年頃に某ホラー系掲示板に投稿された体験談を発端とする、日本のインターネット怪談の一つである。
内容は、ある空き家にまつわる“呪物”と“母娘の儀式”を巡る怪異で、心霊系・民俗系・スプラッター系ホラーの要素を併せ持つ異色のストーリーとなっている。
物語の中心には、玄関のない空き家と、そこに残された2つの鏡台が存在する。鏡台には「禁后」と書かれた半紙や人体の一部(歯・爪など)が納められており、引き出しを開けた者には異変が起こる。
この“禁后”とは、かつて娘を「捧げもの」にして母が“救済”されるという、狂気的な儀式と信仰を指すとされている。名前にまつわる呪い、自己喪失、自我崩壊といったテーマが複雑に絡み合う、現代怪談でも特に陰惨かつ哲学的な話である。
📖 禁后(パンドラ)あらすじ
とある空き家で見つかったのは、二つ並んだ古びた鏡台と、そこに隠されていた「禁后」と記された紙。そして、中には人間の歯、髪の毛、爪といった“何かの痕跡”が入っていた──。
それを目にした友人Sは次第に精神を病んでいき、「名前を呼ぶな」「忘れてくれ」と言い残し、姿を消す。投稿者はSの行方を追い、例の空き家を再び訪れるが、そこでは信じがたい光景が広がっていた。鏡の前に佇む少女が、自らの髪をむしり、舐め、笑っている──まるで「何か」に取り憑かれているように。
調査を進めた投稿者は、この家ではかつて「若い娘を鏡台に捧げることで母親が若さを保つ」というおぞましい風習が代々行われていたことを知る。そして、「禁后(パンドラ)」とは、そうした“老いと死を拒んだ女たちの呪術”の象徴であり、覗いた者、関わった者に連鎖的な呪いを残す“決して開けてはならない箱”だったのだ。
原著作者「怖い話投稿:ホラーテラー」「匿名さん」 2009/02/11 13:11
私の故郷に伝わっていた『禁后』というものにまつわる話です。
どう読むのかは最後までわかりませんでしたが、私たちの間では『パンドラ』と呼ばれていました。私が生まれ育った町は、静かでのどかな田舎町でした。
目立った遊び場などもない寂れた町だったのですが、一つだけとても目を引くものがありました。
町の外れ、田んぼが延々と続く道にぽつんと建っている、一軒の空き家です。
長らく誰も住んでいなかったようでかなりボロく、古くさい田舎町の中でも一際古さを感じさせるような家でした。
それだけなら単なる古い空き家…で終わりなのですが、目を引く理由がありました。一つは、両親など町の大人達の過剰な反応。
その空き家の話をしようとするだけで厳しく叱られ、時にはひっぱたかれてまで怒られることもあったぐらいです。
どの家の子供も同じで、私もそうでした。
もう一つは、その空き家にはなぜか玄関が無かったということ。
窓やガラス戸はあったのですが、出入口となる玄関が無かったのです。
以前に誰かが住んでいたとしたら、どうやって出入りしていたのか?
わざわざ窓やガラス戸から出入りしてたのか?
そういった謎めいた要素が興味をそそり、いつからか勝手に付けられた『パンドラ』という呼び名も相まって、
当時の子供達の一番の話題になっていました。(この時点では、『禁后』というものについてまだ何も知りません)私を含め大半の子は、何があるのか調べてやる!と探索を試みようとしていましたが、
普段その話をしただけでも親達があんなに怒るというのが身に染みていたため、なかなか実践できずにいました。
場所自体は子供だけでも難なく行けるし、人目もありません。
たぶん、みんな一度は空き家の目の前まで来てみたことがあったと思います。
しばらくはそれで雰囲気を楽しみ、何事もなく過ごしていました。私が中学にあがってから何ヵ月か経った頃、
ある男子がパンドラの話に興味を持ち、「ぜひ見てみたい」と言いだしました。名前はAとします。
A君の家は、お母さんがもともとこの町の出身で、他県に嫁いでいったそうですが、
離婚を機に、実家であるお祖母ちゃんの家に戻ってきたとのこと。
A君自身はこの町は初めてなので、パンドラの話も全く知らなかったようです。
その当時私と仲の良かったB君・C君・D子の内、B君とC君が彼と親しかったので、
自然と私達の仲間内に加わっていました。
五人で集まってたわいのない会話をしている時、私達が当たり前のようにパンドラという言葉を口にするので、
気になったA君がそれに食い付いたのでした。
「うちの母ちゃんとばあちゃんもここの生まれだけど、その話聞いたらオレも怒られんのかな?」
「怒られるなんてもんじゃねえぜ?うちの父ちゃん母ちゃんなんか、本気で殴ってくるんだぞ!」
「うちも。意味わかんないよね」
A君にパンドラの説明をしながら、みんな親への文句を言い始めます。ひととおり説明し終えると、一番の疑問である「空き家に何があるのか」という話題になりました。
「そこに何があるかってのは、誰も知らないの?」
「知らない。入ったことないし、聞いたら怒られるし。知ってんのは親達だけなんじゃないか?」
「だったらさ、何を隠してるのかオレたちで突き止めてやろうぜ!」
Aは意気揚揚と言いました。
親に怒られるのが嫌だった私と他の三人は、最初こそ渋っていましたが、
Aのノリにつられたのと、今までそうしたくともできなかったうっぷんを晴らせるということで、結局みんな同意します。
その後の話し合いで、いつも遊ぶ時によくついてくるDの妹も行きたいという事になり、
六人で日曜の昼間に作戦決行となりました。当日、わくわくした面持ちで空き家の前に集合。
なぜか各自リュックサックを背負って、スナック菓子などを持ち寄り、みんな浮かれまくっていたのを覚えています。
前述のとおり、問題の空き家は田んぼに囲まれた場所にぽつんと建っていて、玄関がありません。
二階建の家ですが窓まで昇れそうになかったので、中に入るには一階のガラス戸を割って入るしかありませんでした。
「ガラスの弁償ぐらいなら大した事ないって」
そう言ってA君は思いっきりガラスを割ってしまい、中に入っていきました。
何もなかったとしてもこれで確実に怒られるな…と思いながら、みんなも後に続きます。そこは居間でした。
左側に台所、正面の廊下に出て左には浴室と突き当たりにトイレ、右には二階への階段と本来玄関であろうスペース。
昼間ということもあり明るかったですが、玄関が無いせいか廊下のあたりは薄暗く見えました。
古ぼけた外観に反して中は予想より綺麗…というより何もありません。
家具など物は一切なく、人が住んでいたような跡は何もない。
居間も台所も、かなり広めではあったもののごく普通。
「何もないじゃん」
「普通だな?何かしら物が残ってるんだと思ってたのに」何もない居間と台所をあれこれ見ながら、男三人はつまらなそうに持ってきたお菓子をボリボリ食べ始めました。
「てことは、秘密は二階かな」
私とD子は、D妹の手を取りながら二階に向かおうと廊下に出ます。
しかし、階段は…と廊下に出た瞬間、私とD子は心臓が止まりそうになりました。
左にのびた廊下には途中で浴室があり、突き当たりがトイレなのですが、
その間くらいの位置に鏡台が置かれ、真前につっぱり棒のようなものが立てられていました。
そして、その棒に髪がかけられていたのです。
どう表現していいかわからないのですが、カツラのように髪型として形を成したものというか、
ロングヘアの女性の後ろ髪が、そのままそこにあるという感じです。(伝わりにくかったらごめんなさい)
位置的にも、平均的な身長なら大体その辺に頭がくるだろうというような位置で棒の高さが調節してあり、
まるで『女が鏡台の前で座ってる』のを再現したみたいな光景。
一気に鳥肌が立ち、「何何!?何なのこれ!?」と軽くパニックの私とD子。
何だ何だ?と廊下に出てきた男三人も、意味不明な光景に唖然。
D妹だけが、「あれなぁに?」ときょとんとしていました。
「なんだよあれ?本物の髪の毛か?」
「わかんない。触ってみるか?」
A君とB君はそんな事を言いましたが、C君と私達は必死で止めました。
「やばいからやめろって!気持ち悪いし絶対何かあるだろ!」
「そうだよ、やめなよ!」
どう考えても異様としか思えないその光景に恐怖を感じ、ひとまずみんな居間に引っ込みます。
居間からは見えませんが、廊下の方に視線をやるだけでも嫌でした。
「どうする…?廊下通んないと二階行けないぞ」
「あたしやだ。あんなの気持ち悪い」
「オレもなんかやばい気がする」
C君と私とD子の三人は、あまりに予想外のものを見てしまい、完全に探索意欲を失っていました。
「あれ見ないように行けばだいじょぶだって。二階で何か出てきたって、階段降りてすぐそこが出口だぜ?
しかもまだ昼間だぞ?」
AB両人はどうしても二階を見たいらしく、引け腰の私達三人を急かします。
「そんな事言ったって…」
私達が顔を見合わせどうしようかと思った時、はっと気付きました。
「あれ?D子、○○ちゃんは?」
「えっ?」
全員気が付きました。D妹がいないのです。
私達は唯一の出入口であるガラス戸の前にいたので、外に出たという事はありえません。
広めといえど居間と台所は一目で見渡せます。
その場にいるはずのD妹がいないのです。
「○○!?どこ!?返事しなさい!!」
D子が必死に声を出しますが、返事はありません。
「おい、もしかして上に行ったんじゃ…」
その一言に、全員が廊下を見据えました。
「やだ!なんで!?何やってんのあの子!?」
D子が涙目になりながら叫びます。
「落ち着けよ!とにかく二階に行くぞ!」
さすがに怖いなどと言ってる場合でもなく、すぐに廊下に出て階段を駆け上がっていきました。「おーい、○○ちゃん?」
「○○!いい加減にしてよ!出てきなさい!」
みなD妹へ呼び掛けながら階段を進みますが、返事はありません。
階段を上り終えると、部屋が二つありました。どちらもドアは閉まっています。
まずすぐ正面のドアを開けました。その部屋は、外から見たときに窓があった部屋です。
中にはやはり何もなく、D妹の姿もありません。
「あっちだな」
私達はもう一方のドアに近付き、ゆっくりとドアを開けました。
D妹はいました。
ただ、私達は言葉も出せずその場で固まりました。
その部屋の中央には、下にあるのと全く同じものがあったのです。
鏡台とその真前に立てられた棒、そしてそれにかかった長い後ろ髪。
異様な恐怖に包まれ、全員茫然と立ち尽くしたまま動けませんでした。「ねえちゃん、これなぁに?」
不意にD妹が言い、次の瞬間とんでもない行動をとりました。
D妹は鏡台に近付き、三つある引き出しの内、一番上の引き出しを開けたのです。
「これなぁに?」
D妹がその引き出しから取り出して、私達に見せたもの…
それは、筆のようなもので『禁后』と書かれた半紙でした。
意味がわからず、D妹を見つめるしかない私達。
この時、どうしてすぐに動けなかったのか、今でもわかりません。
D妹は構わずその半紙をしまって引き出しを閉め、今度は二段目の引き出しから中のものを取り出しました。
全く同じもの、『禁后』と書かれた半紙です。
もう何が何だかわからず、私はがたがたと震えるしか出来ませんでしたが、
D子が我に返り、すぐさま妹に駆け寄りました。
D子ももう半泣きになっています。
「何やってんのあんたは!」
妹を厳しく怒鳴りつけ、半紙を取り上げると、引き出しを開けしまおうとしました。
この時、D妹が半紙を出した後、すぐに二段目の引き出しを閉めてしまっていたのが問題でした。
慌てていたのか、D子は二段目ではなく三段目、一番下の引き出しを開けたのです。
ガラッと引き出しを開けたとたん、D子は中を見つめたまま動かなくなりました。
黙ってじっと中を見つめたまま微動だにしません。
「ど、どうした!?何だよ!?」
ここでようやく私達は動けるようになり、二人に駆け寄ろうとした瞬間、
ガンッ!!と大きな音をたて、D子が引き出しを閉めました。
そして肩より長いくらいの自分の髪を口元に運び、むしゃむしゃとしゃぶりだしたのです。
「お、おい?どうしたんだよ!?」
「D子?しっかりして!」
みんなが声をかけても反応が無い。
ただひたすら、自分の髪をしゃぶり続けている。
その行動に恐怖を感じたのかD妹も泣きだし、ほんとうに緊迫した状況でした。
「おい!どうなってんだよ!?」
「知らねえよ!何なんだよこれ!?」
「とにかく外に出てうちに帰るぞ!ここにいたくねえ!」D子を三人が抱え、私はD妹の手を握り急いでその家から出ました。
その間もD子は、ずっと髪をびちゃびちゃとしゃぶっていましたが、
どうしていいかわからず、とにかく大人のところへ行かなきゃ!という気持ちでした。その空き家から一番近かった私の家に駆け込み、大声で母を呼びました。
泣きじゃくる私とD妹、汗びっしょりで茫然とする男三人、そして奇行を続けるD子。
どう説明したらいいのかと頭がぐるぐるしていたところで、声を聞いた母が何事かと現われました。
「お母さぁん!」
泣きながらなんとか事情を説明しようとしたところで、母は私と男三人を突然ビンタで殴り怒鳴りつけました。
「あんた達、あそこへ行ったね!?あの空き家へ行ったんだね!?」
普段見たこともない形相に、私達は必死に首を縦に振るしかなく、うまく言葉を発せませんでした。
「あんた達は奥で待ってなさい。すぐみんなのご両親達に連絡するから」
そう言うと母はD子を抱き抱え、二階へ連れていきました。私達は言われた通り、私の家の居間でただぼーっと座り込み、何も考えられませんでした。
それから一時間ほどはそのままだっと思います。みんなの親たちが集まってくるまで、母もD子も二階から降りてきませんでした。
親達が集まった頃にようやく母だけが居間に来て、ただ一言、
「この子達があの家に行ってしまった」と言いました。
親達がざわざわとしだし、みんなが動揺したり取り乱したりしていました。
「お前ら!何を見た!?あそこで何を見たんだ!?」
それぞれの親達が一斉に我が子に向かって放つ言葉に、私達は頭が真っ白で応えられませんでしたが、
何とかA君とB君が懸命に事情を説明しました。
「見たのは鏡台と変な髪の毛みたいな…あと、ガラス割っちゃって…」
「他には!?見たのはそれだけか!?」
「あとは…何かよくわかんない言葉が書いてある紙…」
その一言で急に場が静まり返りました。と同時に、二階からものすごい悲鳴。
私の母が慌てて二階に上がり、数分後、母に抱えられて降りてきたのはD子のお母さんでした。
まともに見れなかったぐらい涙でくしゃくしゃでした。
「見たの…?D子は引き出しの中を見たの!?」
D子のお母さんが私達に詰め寄りそう問い掛けます。
「あんた達、鏡台の引き出しを開けて、中にあるものを見たか?」
「二階の鏡台の三段目の引き出しだ。どうなんだ?」
他の親達も問い詰めてきました。
「一段目と二段目は僕らも見ました…三段目は…D子だけです…」
言い終わった途端、D子のお母さんがものすごい力で私達の体を掴み、
「何で止めなかったの!?あんた達友達なんでしょう!?何で止めなかったのよ!?」と叫びだしたのです。
D子のお父さんや他の親達が必死で押さえ、「落ち着け!」「奥さんしっかりして!」となだめようとし、
しばらくしてやっと落ち着いたのか、D妹を連れてまた二階へ上がっていってしまいました。そこでいったん場を引き上げ、私達四人はB君の家に移り、B君の両親から話を聞かされました。
「お前達が行った家な、最初から誰も住んじゃいない。
あそこは、あの鏡台と髪の為だけに建てられた家なんだ。
オレや他の親御さん達が子供の頃からあった。
あの鏡台は実際に使われていたもの、髪の毛も本物だ。
それから、お前達が見たっていう言葉。この言葉だな?」
そういってB君のお父さんは紙とペンを取り、『禁后』と書いて私達に見せました。
「うん…その言葉だよ」
私達が応えると、B君のお父さんはくしゃっと丸めたその紙をごみ箱に投げ捨て、そのまま話を続けました。
「これはな、あの髪の持ち主の名前だ。読み方は、知らないかぎりまず出てこないような読み方だ。
お前達が知っていいのはこれだけだ。金輪際あの家の話はするな。近づくのもダメだ。わかったな?
とりあえず今日は、みんなうちに泊まってゆっくり休め」
そう言って席を立とうとしたB君のお父さんに、B君は意を決したようにこう聞きました。
「D子はどうなったんだよ!?あいつは何であんな…」と言い終わらない内に、B君のお父さんが口を開きました。
「あの子の事は忘れろ。もう二度と元には戻れないし、お前達とも二度と会えない。それに…」
B君のお父さんは少し悲しげな表情で続けました。
「お前達はあの子のお母さんから、この先一生恨まれ続ける。
今回の件で誰かの責任を問う気はない。
だが、さっきのお母さんの様子でわかるだろ?お前達はもうあの子に関わっちゃいけないんだ」
そう言って、B君のお父さんは部屋を出ていってしまった。
私達は何も考えられなかった。
その後どうやって過ごしたかもよくわからない。
本当に長い1日でした。それからしばらくは普通に生活していました。
翌日から私の親もA達の親も一切この件に関する話はせず、D子がどうなったかもわかりません。
学校には一身上の都合となっていたようですが、一ヵ月程してどこかへ引っ越してしまったそうです。
また、あの日、私達以外の家にも連絡が行ったらしく、あの空き家に関する話は自然と減っていきました。
ガラス戸などにも厳重な対策が施され、中に入れなくなったとも聞いています。
私やA達はあれ以来一度もあの空き家に近づいておらず、D子の事もあってか疎遠になっていきました。
高校も別々でしたし、私も三人も町を出ていき、それからもう十年以上になります。ここまで下手な長文に付き合ってくださったのに申し訳ないのですが、結局何もわからずじまいです。
ただ、最後に…
私が大学を卒業した頃ですが、D子のお母さんから私の母宛てに手紙がありました。
内容はどうしても教えてもらえなかったのですが、
その時の母の言葉が意味深だったのが、今でも引っ掛かっています。「母親ってのは、最後まで子供の為に隠し持ってる選択があるのよ。
もし、ああなってしまったのがあんただったとしたら、私もそれを選んでたと思うわ。
それが間違った答えだとしてもね」代々、母から娘へと三つの儀式が受け継がれていたある家系にまつわる話。
まずはその家系について説明します。その家系では娘は母の『所有物』とされ、娘を『材料』として扱うある儀式が行われていました。
母親は二人または三人の女子を産み、その内の一人を『材料』に選びます。
(男子が生まれる可能性もあるはずですが、その場合どうしていたのかはわかりません)
選んだ娘には二つの名前を付け、一方は母親だけが知る本当の名として生涯隠し通されます。
万が一知られた時の事も考え、本来その字が持つものとは全く違う読み方が当てられるため、
字が分かったとしても、読み方は絶対に母親しか知り得ません。
母親と娘の二人きりだったとしても、決して隠し名で呼ぶ事はありませんでした。
忌み名に似たものかも知れませんが、『母の所有物』であることを強調・証明するためにしていたそうです。
また、隠し名を付けた日に必ず鏡台を用意し、娘の10,13,16歳の誕生日以外には絶対にその鏡台を娘に見せない、
という決まりもありました。
これも、来たるべき日のための下準備でした。本当の名を誰にも呼ばれることのないまま、『材料』としての価値を上げるため、
幼少時から母親の『教育』が始まります。 (選ばれなかった方の娘は、ごく普通に育てられていきます)
例えば…
・猫、もしくは犬の顔をバラバラに切り分けさせる
・しっぽだけ残した胴体を飼う
(娘の周囲の者が全員、これを生きているものとして扱い、娘にそれが真実であると刷り込ませていったそうです)
・猫の耳と髭を使った呪術を教え、その呪術で鼠を殺す
・蜘蛛を細かく解体させ、元の形に組み直させる
・糞尿を食事に(自分や他人のもの)など。全容はとても書けないのでほんの一部ですが、
どれもこれも聞いただけで吐き気をもよおしてしまうようなものばかりでした。
中でも動物や虫、特に猫に関するものが全体の3分の1ぐらいだったのですが、これは理由があります。
この家系では男と関わりを持つのは子を産むためだけであり、目的数の女子を産んだ時点で関係が断たれるのですが、
条件として事前に提示したにも関わらず、家系や呪術の秘密を探ろうとする男も中にはいました。
その対応として、ある代からは男と交わった際に、呪術を使って憑きものを移すようになったのです。
それによって、自分達が殺した猫などの怨念は全て男の元へ行き、
関わった男達の家で、憑きもの筋のように災いが起こるようになっていたそうです。
そうする事で、家系の内情には立ち入らないという条件を守らせていました。
こうした事情もあって、猫などの動物を『教育』によく使用していたのです。
『材料』として適した歪んだ常識、歪んだ価値観、歪んだ嗜好などを形成させるための異常な『教育』は、
代々の母娘間で13年間も続けられます。
その間で、三つの儀式の内の二つが行われます。一つは10歳の時、母親に鏡台の前に連れていかれ、爪を提供するように指示されます。
ここで初めて娘は鏡台の存在を知ります。
両手両足からどの爪を何枚提供するかは、それぞれの代の母親によって違ったそうです。
提供するとは、もちろん剥がすという意味です。
自分で自分の爪を剥がし母親に渡すと、
鏡台の三つある引き出しの内、一番上の引き出しに爪と娘の隠し名を書いた紙を一緒に入れます。
そしてその日は一日中、母親は鏡台の前に座って過ごすのです。
これが一つ目の儀式。もう一つは13歳の時、同様に鏡台の前で歯を提供するように指示されます。
これも代によって数が違います。
自分で自分の歯を抜き、母親はそれを鏡台の二段目、やはり隠し名を書いた紙と一緒にしまいます。
そしてまた一日中、母親は鏡台の前で座って過ごします。
これが二つ目の儀式です。この二つの儀式を終えると、その翌日~16歳までの三年間は『教育』が全く行われません。
突然、何の説明もなく自由が与えられるのです。
これは、13歳までに全ての準備が整ったことを意味していました。
この頃には、すでに母親が望んだ通りの生き人形のようになってしまっているのがほとんどですが、
わずかに残されていた自分本来の感情からか、ごく普通の女の子として過ごそうとする娘が多かったそうです。そして三年後、娘が16歳になる日に最後の儀式が行われます。
最後の儀式、それは鏡台の前で母親が娘の髪を食べるというものでした。
食べるというよりも、体内に取り込むという事が重要だったそうです。
丸坊主になってしまうぐらいのほぼ全ての髪を切り、鏡台を見つめながら無我夢中で口に入れ飲み込んでいきます。
娘はただ茫然と眺めるだけ。
やがて娘の髪を食べ終えると、母親は娘の本当の名を口にします。
娘が自分の本当の名を耳にするのは、この時が最初で最後でした。これでこの儀式は完成され、目的が達成されます。
この翌日から母親は四六時中自分の髪をしゃぶり続ける廃人のようになり、亡くなるまで隔離され続けるのです。
廃人となったのは文字通り母親の脱け殻で、母親とは全く別のものです。
そこにいる母親はただの人型の風船のようなものであり、
母親の存在は誰も見たことも聞いたこともない、誰も知り得ない場所に到達していました。
これまでの事は、全てその場所へ行く資格(神格?)を得るためのものであり、
最後の儀式によってそれが得られるというものでした。
その未知なる場所では、それまで同様にして資格を得た母親たちが暮らしており、
決して汚れることのない楽園として存在しているそうです。
最後の儀式で資格を得た母親はその楽園へ運ばれ、後には髪をしゃぶり続けるだけの脱け殻が残る…
そうして新たな命を手にするのが目的だったのです。
残された娘は母親の姉妹によって育てられていきます。
一人でなく二~三人産むのはこのためでした。
母親がいなくなってしまった後、普通に育てられてきた母親の姉妹が娘の面倒を見るようにするためです。
母親から解放された娘は、髪の長さが元に戻る頃に男と交わり、子を産みます。
そして、今度は自分が母親として全く同じ事を繰り返し、母親が待つ場所へと向かうわけです。ここまでがこの家系の説明です。
もっと細かい内容もあったのですが、二度三度の投稿でも収まる量と内容じゃありませんでした。
なるべく分かりやすいように書いたのですが、今回は本当に分かりづらい読みづらい文章だと思います。
申し訳ありません。
本題はここからですので、ひとまず先へ進みます。実は、この悪習はそれほど長く続きませんでした。
徐々にこの悪習に疑問を抱くようになっていったのです。
それがだんだんと大きくなり、次第に母娘として本来あるべき姿を模索するようになっていきます。
家系としてその姿勢が定着していくに伴い、悪習はだんだん廃れていき、やがては禁じられるようになりました。
ただし、忘れてはならない事であるとして、隠し名と鏡台の習慣は残す事になりました。
隠し名は母親の証として、鏡台は祝いの贈り物として受け継いでいくようにしたのです。
少しずつ周囲の住民達とも触れ合うようになり、夫婦となって家庭を築く者も増えていきました。そうしてしばらく月日が経ったある年、一人の女性が結婚し妻となりました。八千代という女性です。
悪習が廃れた後の生まれである母の元で、ごく普通に育ってきた女性でした。
周囲の人達からも可愛がられ平凡な人生を歩んできていましたが、
良き相手を見つけ、長年の交際の末の結婚となったのです。
彼女は自分の家系については、母から多少聞かされていたので知っていましたが、
特に関心を持った事はありませんでした。
妻となって数年後には娘を出産、貴子と名付けます。
母から教わった通り隠し名も付け、鏡台も自分と同じものを揃えました。そうして幸せな日々が続くと思われていましたが、娘の貴子が10歳を迎える日に異変が起こりました。
その日、八千代は両親の元へ出かけており、家には貴子と夫だけでした。
用事を済ませ、夜になる頃に八千代が家に戻ると、信じられない光景が広がっていました。
何枚かの爪が剥がされ、歯も何本か抜かれた状態で貴子が死んでいたのです。
家の中を見渡すと、しまっておいたはずの貴子の隠し名を書いた紙が床に落ちており、
剥がされた爪と抜かれた歯は貴子の鏡台に散らばっていました。
夫の姿はありません。
何が起こったのかまったく分からず、娘の体に泣き縋るしか出来ませんでした。
異変に気付いた近所の人達がすぐに駆け付けるも、八千代はただずっと貴子に泣き縋っていたそうです。
状況が飲み込めなかった住民達は、ひとまず八千代の両親に知らせる事にし、
何人かは八千代の夫を探しに出ていきました。
この時、八千代を一人にしてしまったのです。
その晩のうちに、八千代は貴子の傍で自害しました。住民達が八千代の両親に知らせたところ、現場の状況を聞いた両親は落ち着いた様子でした。
「想像はつく。八千代から聞いていた儀式を試そうとしたんだろ。
八千代には詳しく話したことはないから、断片的な情報しか分からんかったはずだが、
貴子が10歳になるまで待っていやがったな」
と言って、八千代の家へ向かいました。
八千代の家に着くと、さっきまで泣き縋っていた八千代も死んでいる…
住民達はただ愕然とするしかありませんでした。
八千代の両親は終始落ち着いたまま、
「わしらが出てくるまで誰も入ってくるな」と言い、しばらく出てこなかったそうです。数時間ほどして、やっと両親が出てくると、
「二人はわしらで供養する。夫は探さなくていい。理由は今に分かる」
と住民達に告げ、その日は強引に解散させました。それから数日間、夫の行方はつかめないままだったのですが、
程なくして、八千代の家の前で亡くなっているのが見つかりました。
口に大量の長い髪の毛を含んで死んでいたそうです。
どういう事かと住民達が八千代の両親に尋ねると、
「今後八千代の家に入ったものはああなる。そういう呪いをかけたからな。
あの子らは、悪習からやっと解き放たれた新しい時代の子達なんだ。
こうなってしまったのは残念だが、せめて静かに眠らせてやってくれ」
と説明し、八千代の家をこのまま残していくように指示しました。これ以来、二人への供養も兼ねて、八千代の家はそのまま残される事となったそうです。
家のなかに何があるのかは誰も知りませんでしたが、八千代の両親の言葉を守り、誰も中を見ようとはしませんでした。
そうして、二人への供養の場所として長らく残されていたのです。その後、老朽化などの理由でどうしても取り壊すことになった際、初めて中に何があるかを住民達は知りました。
そこにあったのは私達が見たもの、あの鏡台と髪でした。
八千代の家は二階がなかったので、玄関を開けた目の前に並んで置かれていたそうです。
八千代の両親がどうやったのかはわかりませんが、やはり形を成したままの髪でした。
これが呪いであると悟った住民達は、出来るかぎり慎重に運び出し、新しく建てた空き家の中へと移しました。
この時、誤って引き出しの中身を見てしまったそうですが、何も起こらなかったそうです。
これに関しては、供養をしていた人達だったからでは?という事になっています。
空き家は町から少し離れた場所に建てられ、
玄関がないのは出入りする家ではないから、窓・ガラス戸は日当たりや風通しなど供養の気持ちからだという事でした。
こうして誰も入ってはいけない家として町全体で伝えられていき、大人達だけが知る秘密となったのです。ここまでが、あの鏡台と髪の話です。
鏡台と髪は八千代と貴子という母娘のものであり、言葉は隠し名として付けられた名前でした。ここから最後の話になります。
空き家が建てられて以降、中に入ろうとする者は一人もいませんでした。
前述の通り、空き家へ移る際に引き出しの中を見てしまったため、
中に何があるかが一部の人達に伝わっていたからです。
私達の時と同様、事実を知らない者に対して過剰に厳しくする事で、何も起こらないようにしていました。
ところが、私達の親の間で一度だけ事が起こってしまったそうです。
前回の投稿で、私と一緒に空き家へ行ったAの家族について、少しふれたのを覚えていらっしゃるでしょうか。
Aの祖母と母がもともと町の出身であり、結婚して他県に住んでいたという話です。
これは事実ではありませんでした。子供の頃に、Aの母とBの両親、そしてもう一人男の子(Eとします)を入れた四人であの空き家へ行ったのです。
私達とは違って夜中に家を抜け出し、わざわざハシゴを持参して二階の窓から入ったそうです。
窓から入った部屋には何もなく、やはり期待を裏切られたような感じでガクッとし、隣にある部屋へ行きました。
そこであの鏡台と髪を見て、夜中という事もあり凄まじい恐怖を感じます。
ところが、四人のうちA母はかなり肝が据わっていたようで、
怖がる三人を押し退けて近づいていき、引き出しを開けようとさえしたそうです。
さすがに三人も必死で止め、その場は治まりますが、問題はその後に起こりました。
その部屋を出て恐る恐る階段を降りると、またすぐに恐怖に包まれます。
廊下の先にある鏡台と髪。
この時点で三人はもう帰ろうとしますが、A母が問題を引き起こしてしまいました。
私達の時のD妹のように、引き出しを開け中のものを出したのです。
A母が取り出したのは、一階の鏡台の一段目の引き出しの中の『紫逅』と書かれた紙で、
何枚かの爪も入っていたそうです。
さすがにやばいものではと感じた三人は、A母を無理矢理引っ張り、紙を元に戻して帰ろうとしますが、
じたばたしてるうちに棒から髪が落ちてしまったそうです。
空き家の中で最も異様な雰囲気であるその髪にA母も触れる勇気はなく、四人はそのままにして帰ってきてしまいました。それから二,三日はそのまま放っておいたらしいですが、親にバレたら…という気持ちがあったので、
元に戻しに行く事になります。
B両親はどうしても都合があわなかったため、A母とE君の二人で行く事になりました。夜中に抜け出し、ハシゴを使って二階から入ります。
階段を降り、家から持ってきた箸で髪を掴んで何とか棒に戻しました。
「さぁ早く帰ろう」とE君は急かしましたが、
ホッとしたのかA母はE君を怖がらせようと思い、今度は二段目の引き出しを開けたのです。
『紫逅』と書かれた紙と、何本かの歯が入っていました。
あまりの恐怖にE君は取り乱し泣きそうになっていたのですが、
A母はこれを面白がってしまい、E君にだけ中が見えるような態勢で三段目の引き出しを開けたそうです。
E君が引き出しの中を見たのはほんの数秒ほどでした。
「何があった??」とA母が覗き込もうとした瞬間、ガンッ!!と引き出しを閉め、
ぼーっとしたまま動かなくなりました。
A母はE君が仕返しにふざけてるんだと思ったのですが、
何か異常な空気を感じ、突然怖くなって一人で帰ってしまったのです。家に着いてすぐに母親に事情を話すと、母親の顔色が変わり異様な事態となりました。
E君の両親などに連絡し、親達がすぐに空き家へ向かいます。
数十分ぐらいして、家で待っていたA母は、親達に抱えられて帰ってきたE君を少しだけ見ました。
何かを頬張っているようで、口元からは長い髪の毛が何本も見えていたそうです。
この後B両親も呼び出され、親も交えて話したそうですが、E君の両親は三人に何も言いませんでした。
ただ、言葉では表せないような表情でずっとA母を睨み付けていたそうです。この後、三人はあの空き家にまつわる話を聞かされました。
E君の事に関しては、私達に言ったのと全く同じ事を言われたようでした。
そして、E君の家族がどこかへ引っ越していくまでの一ヵ月間ぐらいの間、
毎日A母の家にE君の両親が訪ねてきていたそうです。
この事でA母は精神的に苦しい状態になり、見かねた母親が他県の親戚のところへ預けたのでした。
その後A母やE君がどうしていたのかはわかりませんが、A母が町に戻ってきたのはE君への償いからだそうです。以上で話は終わりです。
最後に、鏡台の引き出しに入っているものについて。空き家には一階に八千代の鏡台、二階に貴子の鏡台があります。
八千代の鏡台には、一段目は爪、二段目は歯が、隠し名を書いた紙と一緒に入っています。
貴子の鏡台は、一,二段目とも隠し名を書いた紙だけです。
八千代が『紫逅』、貴子が『禁后』です。そして問題の三段目の引き出しですが、中に入っているのは手首だそうです。
八千代の鏡台には八千代の右手と貴子の左手、貴子の鏡台には貴子の右手と八千代の左手が、
指を絡めあった状態で入っているそうです。
もちろん、今現在どんな状態になっているのかはわかりませんが。
D子とE君はそれを見てしまい、異常をきたしてしまいました。
厳密に言うと、隠し名と合わせて見てしまったのがいけなかったという事でした。
『紫逅』は八千代の母が、『禁后』は八千代が実際に書いたものであり、
三段目の引き出しの内側には、それぞれの読み方がびっしりと書かれているそうです。
空き家は今もありますが、今の子供達にはほとんど知られていないようです。
娯楽や誘惑が多い今では、あまり目につく存在ではないのかも知れません。
地域に関してはあまり明かせませんが、東日本ではないです。それから、D子のお母さんの手紙についてですが、これは控えさせていただきます。
D子とお母さんはもう亡くなられていると知らされましたので、私の口からは何もお話出来ません。
📚出典と派生・類似伝承
本作の原作は、2009年に怖い話投稿サイト「ホラーテラー」に投稿されたネット怪談である。内容の完成度の高さや恐怖描写の緻密さから、ネット掲示板や怖い話系ブログ、まとめサイトでもたびたび取り上げられている。
類似の構造を持つ怪談には以下のようなものがある:
- 八尺様(はっしゃくさま):近づいた者が呪われる女性型の怪異
- コトリバコ:特定の血筋を狙う呪物と風習
- 口裂け女:女性と呪い、名前・容貌にまつわる恐怖
これらと同様に「禁后」も、女性性・母性・継承といったテーマを内包しており、日本に根付く“血筋の呪い”の系譜に連なる都市伝説である。作品となっている。
🎬メディア登場・現代への影響
2021年にはドラマ『カイダン都市伝説 洒落怖』第4話として映像化されている
このエピソードでは、原作の精神的な恐怖を可能な限り忠実に映像化し、特に“少女が自分の髪をしゃぶるシーン”は大きな話題となった。TikTokなどでも「禁后」に関する短編ホラー動画が制作されるなど、Z世代を中心に再ブームが起きつつある。
🔍考察と文化的背景
「禁后」はただの心霊話ではなく、日本の母娘関係や家制度、呪術信仰の歪みを象徴する作品でもある。
- 母から娘へと継承される儀式
- 名前(本名)に対する禁忌
- “見てはいけない引き出し”という概念
などは、民俗学的に見ても興味深い。特に“名前に霊的な力が宿る”という思想は、アイヌや中国、日本古来の信仰にも共通しており、「本当の名前を知られると呪われる」といった民間信仰を反映していると考えられる。
また「玄関のない家」や「鏡台」といったモチーフは、日本家屋における“内と外”“表と裏”の境界の曖昧さを強調し、精神の奥底への侵食を象徴している。
🗺️出現地点
物語の舞台となる空き家の正確な場所は明かされていないが、投稿者の語り口や文脈からは「郊外の古い住宅地」あるいは「戦後に建てられた和洋折衷の家屋」であると推測される。
舞台が特定されない点も、「どこにでもありそうな場所」に潜む恐怖として、読者の想像力を刺激する効果を生んでいる。
📎関連リンク・参考資料
💬編集者コメント・考察
「禁后(パンドラ)」は、インターネット発の怪談としては異例の深さを持つ物語である。単なる“怖い話”にとどまらず、名前・家系・信仰・母娘という重層的なテーマを含み、読む者の想像力を掻き立てる構造となっている。
一読して終わるのではなく、“何が本当に恐ろしかったのか”を繰り返し考察したくなる類の怪談であり、日本怪談文化における“現代の民間伝承”と呼べるだろう。
今後、ホラー映画や漫画・ゲームなどで再脚色されていく可能性も高く、その行方を見守りたい。
🎧 都市伝説好き必見!“聴く怖い話”体験を始めよう【Audible / audiobook.jp 比較】
👣 この記事を読んで、背筋がゾワッとしたあなたへ。
もし“読む”だけでなく、“耳で聴く”怪談体験に興味があるなら――
オーディオブックサービスの【Audible】と【audiobook.jp】が、あなたをさらなる恐怖の世界へ案内してくれる。
イヤホン越しに囁かれる怨念、静寂の中で始まる恐怖体験。
一度聴いたら眠れなくなるかもしれない、人気の怪談朗読が多数ラインナップされている。
- 🔊 Audible(オーディブル)
Amazon提供。毎月1冊無料で、声優や芸人による怪談朗読をフルで聴ける。
『新耳袋』シリーズや、怪談師・ありがとうぁみ氏の朗読なども人気。
- 📚 audiobook.jp
日本発のオーディオブックサービス。月額で怪談やホラー作品が聴き放題。深夜に“連続再生”でじっくり楽しめる。
- 🎁 どちらも無料体験が可能。
まずは1本、深夜にイヤホンで試してみてほしい。文字では味わえない恐怖が、あなたの耳に忍び寄りよる。
🔥 話題の2大オーディオブックで聴ける《怪談・怖い話》作品
- 🔊 Audible(オーディブル):Amazon提供、1冊まるごと“無料”で試せる。プロ声優や芸能人による本格怪談朗読が魅力。
- 📚 audiobook.jp:月額プランで怪談やホラー作品が聴き放題。深夜にじっくり聴く“連続再生”が人気。
| タイトル | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 👻 新耳袋シリーズ | ✅ | ✅ |
| 🧟♂️ 稲川淳二 怪談ナイト | ✅ | ✅ |
| 🏚 事故物件怪談 恐音 | ✅ | ✅ |
| 🏞 廃墟・廃線にまつわる話 | ✅(一部) | ✅(一部) |
| 😨 実話怪談集 | 豊富 | 豊富 |
👇こんな人におすすめ!
- ✅ Audibleは…月1冊じっくり聴きたい人向け
- ✅ audiobook.jpは…いろんな怪談を聴き放題で楽しみたい人向け
🎧 どっちがいい?かんたん比較表
| 比較項目 | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 月額 | ¥1,500(1冊無料+聴き放題対象多数) | ¥1,330〜(聴き放題プラン) |
| 無料体験 | 30日間 | 14日間 |
| 怖い話の充実度 | ◎(稲川淳二/新耳袋ほか) | ◎(人気作+独自配信もあり) |
| アプリ使いやすさ | ○ | ◎(日本語対応に強い) |
| 配信ジャンル | 海外含め多彩 | 国内作品に強い |
🧟♂️ 聴くだけで“現地にいるような”恐怖体験
あなたは、ひとりでこの朗読を最後まで聴ける自信はあるだろうか?
「イヤホン越しに耳元で囁くような声がして、思わず音量を下げた…」
そんなレビューも少なくない、リアルな恐怖がここにある。
- ✅ 急に部屋が寒くなった気がする
- ✅ 背後に気配を感じた
- ✅ イヤホン越しに“もう一人”の声が聞こえる…
そんな体験を、ぜひ以下のリンクから始めてほしい。
🔽 無料で怪談体験を始めるならこちらから
👇どちらも無料で今すぐ試せるので、気になる作品を1本、まずは深夜に“イヤホンで”聴いてみてほしい――恐怖の臨場感がまるで違う。
\ 30日間無料体験キャンペーン実施中/
※Audibleは無料期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
\ 14日間無料体験キャンペーン実施中/
※audiobookは無料聴き放題プランの期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
👇こちらの記事も要チェック!
【もっと読む】↓