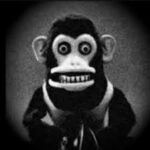🧠コトリバコとは?
※「コトリバコ」を読んだことで、体調不良を訴える方が報告されています。
閲覧する場合は、自己責任でお願いいたします。
「コトリバコ」は、日本のネット掲示板「2ちゃんねる」発祥の都市伝説で、特に「洒落怖(洒落にならないほど怖い話)」ジャンルの中でも高い知名度を誇る怪談である。
「コトリバコ」は「子取り箱」とも書かれ、子どもを産める女性や子どもを対象とした呪いの箱とされている。木製のパズルのような構造を持ち、外見からは中身がわからないように作られている。この箱は、特定の条件下で開封すると、呪いが発動し、対象者に甚大な被害をもたらすとされる。
📖 コトリバコあらすじ
とある田舎町。小学生の少女が、原因不明の体調不良に陥り入院する。次第に少女は人相が変わり、病状は悪化。医者も手が出せず、家族は霊的な原因を疑い、知人の紹介で“視える”男に相談する。
男は家に足を踏み入れた途端に異様な空気を感じ取り、家に隠された箱──「コトリバコ」の存在を突き止める。その箱は呪いの道具であり、かつて迫害を受けた人々によって作られた“復讐の器”だった。
箱には女性や子どもを呪う意図が込められ、特定の年齢や性別をターゲットに強い力を発揮する。少女はその呪いに“年齢が一致”していたため影響を受けていたのだ。
男は仲間と共に箱を分解・浄化し、呪いを封じることで少女を救うことに成功する。だがその過程で明かされるのは、この箱がかつて実際に使われ、多くの命を奪ってきたという恐ろしい事実だった──。
912 :小箱 1:2005/06/06(月) 12:57:48 ID:lJdBivui0
俺、暇なときにまとめサイト見てる者です。
俺自身霊感とかまったくなくて、ここに書き込むようなことはないだろうなぁって思ってたんですが、
先月あったホットなお話を書き込もうかと思い、ここに来た次第。
一応、話の主役の許可は取って書き込んでます。
ここなら多くの人が信じてくれそうなので。
長文かも。(文才もなく、長文カキコもほとんどしたこと無いので読みにくいかも)冒頭述べたように、俺自身にはまったくもって霊感などは存在してません。
なのでこれ、ホントに霊とか絡んでる話かは俺には判別不可。
皆さんに判別してほしい。
会話の内容も、覚えてるものを書いているので、かなり乱文かもしれません。で、本題。
この話は、霊感の強い友達の話。
その友達は中学生の時からの付き合いで、30手前になった今でもけっこう頻繁に遊んだり飲みに行くような間柄。
そいつん家は、俺らの住んでるところでもけっこう大きめの神社の神主さんの仕事を代々やってて、
普段は普通の仕事してるんだけど、正月とか神事がある時とか結婚式とかあると、
あの神主スタイルで拝むっていうのかな?そういった副業(本業かも)をやってるようなお家。
普段は神社の近くにある住居にすんでます。で、その日も飲みに行こうかってことで、とりあえず俺の家に集合することになったんです。
先にそいつとそいつの彼女が到着して、ゲームしながらもう一人の女の子を待ってたんです。
その神社の子をM、遅れてくる子をS、俺のことをAとしますね。Mの彼女はKで。913 :小箱 2:2005/06/06(月) 12:58:15 ID:lJdBivui0
しばらくゲームしながら待ってたら、Sちゃんから電話がかかってきたんです。
S「ごめんちょっと遅れるね、面白いものが納屋から見つかって、家族で夢中になってた~
Aってさ、クイズとかパズル得意だったよね?面白いものもって行くね!
もうちょっと待ってて~~~」
ってな感じの内容でした。で、40分くらいしたころかな、Sちゃんがやってきたんです。
その瞬間というか、Sちゃんの車が俺ん家の敷地に入った瞬間かな、
Mが「やべぇ。これやべぇ。やべ・・・どうしよ・・・父ちゃん今日留守だよ」って言ったんです。
俺「ん?Mどうしたが?また出たんか?」
K「大丈夫!?またなん?」
M「出たってレベルのもんじゃねぇかも・・・はは・・・Aやべぇよこれ、Sちゃん・・・まじかよ」
Mは普段、霊感あるとかオバケみるとか神社の仕事とか、あまり話題には出さないんですが、
たまにこうやって怯えてるんですよ。
俺もSもKもそのことは知ってるんですが、
Mが突っ込んだ話されるのを嫌がるので、普段はあまり話題にしません。Sちゃんが俺の部屋まで上がってきました。
Mは顔面蒼白ってかんじで、
M「Sちゃんよ・・・何持ってきたん?出してみ・・・」
S「え?え?もしかして私やばいの持ってきちゃった・・・のか・・・な?」
M「うん・・・」
S「これ・・・来週家の納屋を解体するんで、掃除してたら出てきたん」
そういってSちゃんは木箱を出したんです。
20cm四方ほどの木箱でした。
電話でパズルって言ってたのはこのことだろう。
小さなテトリスのブロックみたいな木が組み合わさって、箱になってたと思う。914 :小箱 3:2005/06/06(月) 12:59:09 ID:lJdBivui0
M「それ以上触んなや!触んなや!!」
その瞬間、Mはトイレに猛ダッシュ。
「おぅえぇええ。ぅぇえぇうぇええええ」
嘔吐の声が聞えてきました。
Kがトイレに行ってMの背中をさすってやってるようでした。(良い彼女だ・・w)一通り吐き終えたMが戻ってきました。
Mが携帯を取り出し電話をかけました。
M「とうちゃん・・・コトリバコ・・・コトリバコ友達が持ってきた。
俺怖い。じいちゃと違って俺じゃ、じいちゃみたくできんわ・・・」M泣いてました。とうちゃんに電話かけて泣いてる29歳・・・
それほど恐ろしいことなんでしょう。俺も泣きそうでした。M「うん付いちょらん、箱だけしか見えん。跡はあるけど、のこっちょらんかもしらん。
うん、少しはいっちょる、友達のお腹のとこ。
シッポウの形だと思う・・・シッポウだろ?中に三角ある。シッポウ。
間違いないと思う、だって分からんが!俺は違うけん!」なにやら専門用語色々でてたけど、繰り返していってたのはコトリバコ、シッポウ。
もっと色々言ってたけど忘れました。ごめん。M「分かったやる。やる。ミスったら祓ってや、とおちゃん頼むけんね」
Mここで電話を切りました。
最後にMは2分ほど思いっきり大泣きして、しゃくりあげながら「よし」と正座になり、自分の膝のあたりをパシっと叩きました。
もう泣いてませんでした。なにか決意したようで。916 :小箱 4:2005/06/06(月) 13:04:52 ID:lJdBivui0
M「A・・・カッターか包丁貸してごせや」(「ごせ」ってのはうちらの方言で、~してくれとかの語尾ね)
俺「お、おい、何するん!?」
M「誰か殺そうっちゅうじゃない、Sちゃん祓わないけん。
Sちゃん、俺みて怯えるなっちゅうのが無理な話かもしらんが、怯えるな!
KもAも怯えるな!とにかく怯えるな!怯えるな!!負けるか!負けるかよ!!
俺が居る!怯えるな!怯えるな!
なめんな!俺だってやってやら!じいちゃんやってやら!見てろよ糞!糞ぉおおおおお!」Mは自分の怯えを吹き飛ばすかのように咆哮をあげていました。
Sちゃん半泣きです・・・怯えきってました。
俺もKも泣きそうです。ほんとにちびりそうだった・・・S「分かった、分かった、がんばっでみる」
俺もSもKもなにやら分からないけど、分かった分かったって言ってました。
M「A包丁かカッター持ってきてごせや」
俺「お、おぅ・・」
包丁をMに手渡しました。
M「A俺の内腿、思いっきしツネってごせや!おもいっきし!」
もう、わけ分からないけど、Mの言うとおりにやるしかありません。
M「がぁあああああがあぐいうううあああ・・・・・”!!!」Mの内腿をツネり上げる俺。
俺に腿をつねり上げられながら、Mは自分の指先と手のひらを包丁で切りつけました。
たぶん、その痛みを消すためにツネらせたのかな?M「Sちゃん口開けぇ!」
MはSちゃんの口の中に、自分の血だらけの指を突っ込みました。
M「Sちゃん飲みぃ、まずくても飲みぃ」
S「あぐ;kl:;っぉあr」Sちゃん大泣きです。言葉出てなかったです。
M「◎△*の天井、ノリオ? シンメイイワト アケマシタ、カシコミカシコミモマモウス」
なにやら祝詞か呪文か分かりませんが、5回~6回ほど繰り返しました。
呪文というより、浪曲みたいな感じでした。917 :小箱 5:2005/06/06(月) 13:05:27 ID:lJdBivui0
そしてMがSちゃんの口から指を抜くとすぐ、SちゃんがMの血の混じったゲロを吐きました。S「うぇええええええええええおええわええええええええ」
M「出た!出た!おし!!大丈夫!Sちゃんは大丈夫!
次・・・!じいちゃんみててごせや!」Mは血まみれの手を、Sちゃんの持ってきた木箱の上にかぶせました。
M「コトリバココトリバコ ◎△*??Й・・・
いけん・・いけん・・やっちょけばよかった」Mがまた泣きそうな顔になりました。
M「A!っとおちゃんに電話してごせや」
言われたとおりにMの携帯でMのとおちゃんに電話をし、Mの耳元にあてました。
M「とおちゃん、ごめん忘れた、一緒に呼んでくれ(詠んでくれかな?)」
Mは携帯を耳にあて、右手を小箱添えて、また呪文みたいなものを唱えてました。
やっぱり唄ってるみたいな感じでした。M「終わった。終わった・・・・おわ・・・ったぁ・・うぅえぇえええ」
Mはまた号泣してました。大の大人が泣き崩れたんですよ。
Kによしよしされながら20分くらい大泣きしてました。
俺とSとKも号泣で、4人でわんわん泣いてました。
その間もMは小箱から決して手を離さなかったような気がします。
(号泣してたんであまり覚えてませんがw)すこし落ち着いてから、Mは「手と箱を一緒に縛れる位のタオルかなにかないか?」って聞いてきたので、
薄手のバスタオルでMの手と木箱を縛り付けました。
M「さて、ドコに飲みに行く?」
一同「は?」
M「って冗談じゃw 今日はさすがに無理だけん、A送ってくれよ」
(こいつどういう神経してるんだろ・・・ほんと強い奴だなぁ)918 :小箱 5:2005/06/06(月) 13:05:47 ID:lJdBivui0
その日はSもMもKもなんだかへとへとで、俺が送っていくことになりました。
(飲みだったんで、もともと俺が飲まずに送る予定だったんですよ!いやホントにw)で、それから8日ほどMは仕事を休んだようです。
そして昨日Mと会い、そのときのことを聞いてみたんですが。
M「あ~っとなぁ。Sちゃんところは言い方悪いかもしらんが、◎山にある部落でな。
ああいうところには、ああいったものがあるもんなんよ。
あれはとおちゃんが帰ってきてから安置しといた。
まぁ、あんまり知らんほうがええよ」なにやら言いたくない様子でした。
それ以上は、いくら聞こうとしても教えてくれない_| ̄|○ただ最後に、
M「あの中に入っちょるのはな、怨念そのものってやつなんよ。
まぁ入ってる物は、けっこうな数の人差し指の先と、へその緒だけどな・・・
差別は絶対いけんってことだ、人の恨みってのはこわいで、あんなもの作りよるからなぁ。アレが出てきたらな、俺のじいちゃんが処理してたんだ。
じいちゃんの代であらかた片付けた思ってたんだけど、まさか俺がやることになるなんてなぁ。
俺はふらふらしてて、あんまり家のことやっちょらんけぇ、まじビビリだったよw
ちょっと俺も勉強するわ。まぁ才能ないらしいがwそれとな、部落云々とか話したけど、差別とかお前すんなや・・Sちゃんとも今までどおりな。
そんな時代じゃないしな~あほくせぇろ」
俺「あたりめぇじゃんw。
それよりさ、この楽しい話誰かに話してもええの?」
M「お前好きだなぁ 幽霊すら見えんくせにw」
俺「見えんからこそ好きなんよ」
M「ええよ別に。話したからって、取り付くわけじゃないし。
どうせ誰も信じねぇよ。うそつき呼ばわりされるだけだぞ。俺はとぼけるしw」919 :小箱 7:2005/06/06(月) 13:09:18 ID:lJdBivui0
というわけで、ここに書き込ませてもらった次第です。
長文失礼しました~!
まさか奴もこれだけの人数に話してるとは思わねぇだろうな~パソコンオンチだしwそれと最後にひとつ。
この箱ってね、まとめサイトに同じような箱の話ありましたよね?
木箱開けたら爪と髪が入ってて、昭和天皇がどうとかって紙切れが入ってたって話。
昨日Mの話で中身をチラっと言ってたのを思い出して、ふと・・・
そういった呪物の作り方があるのかな?まぁなんだ、午前中フルに使ってまとめたから疲れたよ_| ̄|○
それと>>915。山口じゃないよ。近いけどねw10月を神有月とか言っちゃう地方。
43 :小箱 912:2005/06/06(月) 22:35:54 ID:lJdBivui0
おまたせしました。
いやはや、なんだか大事になってますね、単独スレまでたってるとは。俺の住んでるとことはど田舎で、地域限定されて見物客?とか来られたらさすがに俺も怖いので、
あまり地域は追求しないでください。
部落差別は少なくなったといいますが、俺は見えにくくなっただけだと思っています。
そういった一部の人たちが、新たな差別を生む可能性も怖いので。
ただ、皆さんの推察どおり島根県です。(ばればれですかねw)
(俺のおしゃべり癖を多少後悔・・・だってね、俺も情報欲しいんよ・・・ここなら集まりそうじゃん)さすがに大事になっておりやばいかなって思ったので、さっきMとSに電話してこの経緯を伝えました。
Mいわく、「別にここがどこか分かったって、詳細なんかわかりゃしないよ。安心しろビビリ」とのことです。電話ついでにというか、昨日Mに聞きそびれた事を質問してみました。
1.あの場にいたS以外の人間、つまり俺とKは大丈夫なのか。
2.また、俺の家に来る前に、件の小箱で遊んでたという家族は大丈夫なのか。
3.頼むよ!まじアレなんだったの!?気になって毎夜6時間しか寝られないよ!
以上3点です。以下Mの回答。
1.2.の回答。
アレは子供と子供を生める女にしか影響なし。
Sの父と弟は問題外。母は・・・閉経してるんじゃないか?
Sのばあちゃんもな。もちろんA(俺)も大丈夫。
Kについては危ないかなと思ったけど、触れた時間が短かったため問題なしだろう。
いざとなったら、とおちゃんがいるし大丈夫。(あの日は旅行で、Mの母と外出してたそうです)
とのこと。44 :小箱 912:2005/06/06(月) 22:36:18 ID:lJdBivui0
3.実はM自身も詳細は知らないらしい。ただコトリバコは『子取り箱』だそうです。
*本当かどうかは不明です。俺を何とか反らそうとウソついたのかもしれないですが・・・
昨日の会話の口ぶりからして、知らないはずが無いと思ってます。
ただ、そこまでして隠すほどのことだってことでしょうか。なおさら怖いけど気になります。また単独スレの>>31さんの言われる、『狐酉』がどうかはその時点ではきいてなかったので不明です。
(電話のあとで気づいたため)次、Sちゃんとの会話ですが要約すると、
あの後、業者が納屋を解体しにきたのですが、そのときお隣のおじいさんと一騒動あったそうで、
そのときの内容を明日3人に話しておきたいと。(M、俺、K)
で、S曰く、自分も恐怖より好奇心が勝ってるということ。
当事者として何があったのか、アレはほんとに何だったのかをせめて知りたい、ということでした。
(さすがだぜSちゃん!)で、今Mに話したらOKということで・・・
ちょっと考え込んでましたが。
明日M、S、K、A4者会談開催してきます。Kは来るか分からないけど。Mのお父さんに話を聞ければ一番いいのでしょうが、
さすがにMが渋ってるのに、お父さんに直談判って訳にはいかないでしょうね・・・
もし聞くことが出来れば聞いてみます。ここまで来たら全部知りたいなぁと思ってます。書き込んでみてよかった。だいぶ焦ったけどw
でも、友達なくすようなことはしたくないので、M、S、Kの誰からかストップかかったらカキコは止めますね。
現時点では好奇心にかき消されてますが罪悪感もあるので。308 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:05:48 ID:0GDcLRRy0
昨日の経緯を書きます。嫌になるくらい長文です。
載せようかどうかかなり迷ったんですが、4人で相談しそれぞれ思うところもあり掲載することにしました。
最後にお願いもあります。
かなり長い話だったのでまとめも時間がかかり、
また、俺自身かなり衝撃的なことを偶然聞かされたので混乱してます。
また、5時間近く話しをしてたので、
会話の細部は記憶を頼りにかなり補完して、会話らしくしているということも了承してください。
あと、主要な発言しか書いてません。伏せてる部分も多々あります。
(一応MとSに見てもらい、修正いくつかしてからアップしてます)
文章ぐだぐだかもしれませんがご勘弁を。*文中、『部落』とか『集落』という言い方してますが、実際の話の中ではそう読んでいません。
あくまで便宜上の言い方です。一応ひどい言葉らしいので、伏字みたいなものと思ってくださいね。310 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:06:27 ID:0GDcLRRy0
6日夜の時点では当事者4人、俺の家でSの話を聞くという予定だったのですが、
SがSの家族、そして納屋の解体の時に一騒動あったという隣家のおじいさんも交えて話がしたいとのことで、
Sの家に行くことになりました。M、S、K、A(俺)。
それと、Sの父はS父、母をS母、Sの祖母をS婆、SのおじいさんをS爺、隣のおじいさんをJとしましょうか。
タイプたいぎいので。(S弟は仕事のため不在)話の内容は以下のようなものです。
それと、方言で書くのはなるべくやめます。JとS婆の話、ほとんど異国語なのでw311 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:06:42 ID:0GDcLRRy0
◎まず、Sが事件の後、納屋の解体業者が来た時の話を。俺の家での出来事の2日後になります。
5月23日、頼んでいた業者がきて、解体用の機械を敷地に入れ作業に入ろうかというとき、
S父に隣家のJが話しかけてきたそうです。
S父がおじいさんに納屋を解体することを伝えると、Jは抗議してきたそうです。
S父ともめてたそうで、その声を聞いたSが「もしかしたらあの箱のことを知っているのかも」と思い、
Jに聞いてみようと外にでたそうです。
この時点でSは、家族にあの日のことは話してなかったそうです。「納屋を壊すな!」というJに対し、
「反対する理由はあの箱のことかなのか」「あの箱はいったい何なのか」という様なことを聞くと、
Jは非常に非常に驚いた顔をし、
「箱を見つけたのか」「あの箱はどうした?」「お前は大丈夫か?」とあわてた様子で聞いてきたそうです。
Sが事件の経緯を話すと、Jは「自分の責任だ。自分の責任だ」と謝ったそうです。
そして、
「聞いておかんかったからこんなことになった」
「話しておかんかったからこんなことになった」
「近いうちにお宅の家族に話さないけんことがある」
と言い、帰って行ったそうです。そしてSは、ポカンとしてるS父に事件のことを話したそうです。
そしてJの話を聞いてから、俺らに話そうと思ってたのですが、
Jが話しに来る素振りを見せずイライラしてたところに、昨夜俺から電話があったと言うわけです。
そして昨日俺の電話を受け、Mも来るなら今日しかないと思い、
その『話さないといけないこと』を今日話して欲しいということで、Jを父と一緒に説得して来ていただいたそうです。312 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:07:02 ID:0GDcLRRy0
◎次に、Mの話。S父がJに「お話いただけますか?」と言うと、
俺とKが居ることで話していいものか悩んでいた。(部外者ですもんね)
と、このあたりで、
M「先に話させてもらっていいですか?」
そういってMが話し始めました。M「Jさん・・・本来、あの箱は今あなたの家にあるはずでは?
今の時代、呪いと言っても大概はホラ話と思われるかもしれないが、この箱については別。
俺は祖父、父から何度も聞かされてたし、実際、祖父と父があれを処理するのを何度か見てきた。
箱の話をするときの二人は真剣そのものだった。管理簿もちゃんとある。
それに事故とはいえ、箱でここの人が死んだこともありましたよね。
今回俺が箱に関わったってことと、父が少し不審に思うことがあるということで、改めて昨夜、父と管理簿を見たんです。
そうしたら、今のシッポウの場所はJさんの家になってた。
そうなると話がおかしい。
父は『やっぱり』と言ってました。
俺の家の方からは接触しないという約束ですが、今回ばかりは話が別だろうと思って来ました。
俺の父が行くといったのですが、今回祓ったのは俺なので俺が今日来ました」Jさん、そしてその他一同は黙って聞いてました。MとJにしか分からない内容なので。
313 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:07:21 ID:0GDcLRRy0
M「それでですね、Jさん。
あなたの家に箱があったのなら、Sのお父さんが箱のことを知らないのは仕方がないし、なんとか納得はできます。
Sのおじいさんは◎△(以下T家としますね)さんから引き継いで、すぐに亡くなられてますよね。
(Sのおじいさんは俺らが知り合った時、つまり厨房の時にはすでにお亡くなりだそうです)
M「管理簿では、T家⇒Sの家⇒J家の移動が1年以内になってました。
Sのおじいさんが、お父さんに伝える時間が無かったのだろうと理解はできるんです。
それに約束の年数からいって、Sのお父さんに役回りが来ることはもう考えにくい。
あなたかT家で最後になる可能性が高いですし。でも、今回箱が出てきたのはSの家だった。これはおかしいですよね。
俺、家のことはあまりやってなかったので、管理簿をまじまじと見たことなんてなかったんですが、
昨夜父と管理簿をみて正直驚きましたよ。
Sの話をさっき聞くまでは、もしかしたら何か手違いがあって、
あなたも箱のことを知らなかったのかもしれないと考えてたのですが、あなたは知っていますよね?
知っていたのに引き継いでいない。そして、Sの家にあるのを知ってて黙っていた。俺、今回のこと、無事に祓えたんで、あとは詮索されてもとぼければ済むかなって思ってたんですよ。
何かの手違いで、Sの家の人みんなが知らなかっただけで、結果オーライというか・・・
正直焦りまくったし、ビビリまくったけど・・・
今日だって、昨日父と管理簿見てなかったら、ここには来てなかったと思います。
本来の約束なら、俺の家からこっちに来ることは禁止ですからね。
だから、今日俺が来たってことは伏せておいて欲しい。
でも、そういうわけには行かなくなったみたいです」314 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:07:39 ID:0GDcLRRy0
M「俺は怒ってますよ。俺の父もね。
ただ、顔も知らない先祖の約束を守り続けないといけないって言うのは、相当酷な話だというのも分かります。
逃げ出したいって気持ちも。俺だってそうでしたから。
俺だってあの日、箱を見ただけで逃げ出したかった。
わずかな時間のことだったのに、本気で逃げようかと思った。
アレを下手すれば十数年、下手すれば何十年保管するなんてどれだけ怖いのか。でも、もしこういったことがここ全体で起きてるのだとしたら、残りの箱の処理に関しても問題が起きます。
Sはたまたま、本当にたまたま箱に近づかなかったっていうだけで、
たまたま、本当に偶然あの日、俺と会うことになってたってだけで・・・
もしかしたらSは死んでたかもしれない。
そしてもしかしたら、他の箱で被害がでているかもしれない。
だから、なぜこういうことになってたのか、話していただけませんか?それと、こいつ(Kのこと)はその場に居た女です。もちろん子供を生める体です。
部外者ではないです。被害者です。
それとこいつは(俺のことです)部外者かもしれませんが、そうでもないかもしれません。
こいつの名前は◎○です。ここらじゃそうそうある苗字じゃないですよね?◎○です」俺はなんのことやら分からなかったです。
ただJさんが俺の方をみて、「あぁ・・・そうかぁ・・・」って。315 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:07:54 ID:0GDcLRRy0
◎Jさんの話しに行きますね。(一部S父母の通訳付きです)J「まず、箱のことを説明したほうがいいですかな。
チッポウ(シッポウかと思ってましたがチッポウらしい)は、
Sの家、J家、そして斜め向いにあったT家の3家で、管理してきたものです。
3家に割り当てられて箱です。
そして、あの箱は3家持ち回りで保管し、家主の死後、次の役回りの家の家主が葬儀後、
前任者の跡取りから受け取り、受取った家主がまた死ぬまで保管し、また次へ、次へと繰り返す。
受取った家主は、跡取りに箱のことを伝える。跡取りが居ない場合は、跡取りが出来た後伝える。
どうしても跡取りに恵まれなかった場合、次の持ち回りの家に渡す。他の班でも同じです。
3家だったり4世帯だったりしますが。そして、他の班が持っている箱については、お互い話題にしないこと。
回す理由は、箱の中身を薄めるためです。
箱を受取った家主は、決して箱に女子供を近づけてはいけない。
そして、箱を管理していない家は、管理している家を監視する。
また、Mの家から札をもらい、箱に張ってある古い札と貼り替える。
約束の年数を保管し、箱の中身が薄まった後、Mの家に届け処理してもらう。
M神社(仮にそう呼びますね)と昔にそういう約束をしたらしい」
M「それで、俺の家は昔の約束どおり、持ち込まれた箱を処理・・・供養してたんだ。
ここにある全ての箱と、箱の現在の保管者の管理簿つけて」316 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:08:19 ID:0GDcLRRy0
J「そうです。本来なら私が、S爺が亡くなったときに、箱を引き継ぐはずでした。
でも、本当に怖かったんです、申し訳ない許して欲しい。
Tの父親が死に(Sの家の前任者です)、引き継いだS爺も立て続けに死に、男には影響ないと分かっていても怖かった。
そんな状態で、いつS父が箱を持ってくるのか怯えてたんです。でも、葬儀後、日が経ってもS父がこない。
それで、T(S家の前任者の跡取り)と相談したんです。
『もしかしたら、S父は何も知らないのかもしれない』『箱から逃げられるかもしれない』と。
そしてまず、S父に箱のことをそれとなく聞き、何も知らされていないことを確認しました。
そして納屋の監視は続け、S家に箱を置いたままにしておくこと、
Tは札の貼り替えをした後、しばらくして引っ越すこと。(松江に行ったらしいです)
そうすれば、他班からは『あそこは終わったんだな』と思ってもらえるかもしれないから。
引き継ぐはずだった私が、S家の監視を続けること。
そして、約束の年が来たら、Jが納屋から持ち出しM神社に届けること。そして・・・本当に、本当に申し訳ない。
それまでに、箱にSやSの母が近づいて死んでしまったとしても、
『箱のことはSの家は知らない。他班の箱のことは触れることは禁止だから、ばれることは無いだろう』
と、Tと相談したんです。本当に申し訳ない。
だから、他班の箱のことは分からない。こんなことは無いと思う、申し訳ない」Jさんは土下座して、何度も謝ってました。
S父さんは死んだS爺さんに、納屋には近づくなとは言われていたそうです。
また、実際気味の悪い納屋で、あえて近づこうとは思ってなかったようです。Sも同様に。317 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:08:35 ID:0GDcLRRy0
それで今回、どうせなら取り壊そうという話になり、中の整理をしていて、
そのときにSが箱を見つけてしまった・・・という経緯でした。
S父さん、S母さん、S婆さん、信じられないという感じでしたが、
ただS婆さんだけが、なにやら納得したような感じで、
S婆「納屋はだから近づかせてもらえなかったのか」という風なことをおっしゃってました。319 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:10:17 ID:0GDcLRRy0
M「なるほど、そういうことでしたか・・・
引継ぎはしなかったとはいえ、監視しなければならず、結局は箱から逃げることは出来なかったんですね。
結局苦しんだと。
決まりの年までたしかあと19年でしたよね?
・・・引き継いでいたとしても、結局は俺が祓うことになってたのかなw
S父さん、S母さん、S婆さん、S・・・
現実味の無い話で、まだ何が何だか分からないと思う。
でもこれは現実で、このご時世にアホみたいに思うかもしらんが、現実で。
でも、Jさんを怒らないであげてほしい。
あの箱が何か知ってるもんにとっちゃ、それほど逃げたいもんだけん。
まぁ、もう箱はないんだけん安心だが?
面白い話が聞けて楽しかったと思って、Jさんを許してやって欲しい。Jさんを許してやって欲しい」Jさんうつむいて、うなだれて、見ててなんだか痛々しかったです。
320 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:10:45 ID:0GDcLRRy0
M「それと、たぶんみんな、あの箱の中身が何かを知りたいだと思う。
ここまで話したら、もう最後まで聞いてほしい。
俺も全部は知らんけど、知ってることを話す。
ここはもう箱終わったけん、問題ないと思うし。
正直、残りの箱はあと二つ、たぶん俺が祓わんといけんもんだけん、俺の決意ってのもある。
それと、S父さんは本来知っておかんといけん話だけん。
それとAは、たぶん今話とかんとしつこいけんなぁwあの箱はな、子取り箱っていって、間引かれた子供の身体を入れた箱でな、作られたのは1860年代後半~80年代前半頃。
この部落(俺らの言葉では部落といいませんが、差別用語です)は、
このあたりでも特にひどい差別、迫害を受けた地域なんよ。
で、余りにもひどい迫害だったもんで、間引きもけっこう行われていた。
△▼(地域名です)の管轄にあったんだが、特に△▼からの直接の迫害がひどかったらしい。
で、働き手が欲しいから子供は作るが、まともな給料がなく生活が苦しいから、子供を間引くと・・・
これは一応わかるよな?」321 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:11:08 ID:0GDcLRRy0
M「で、1860年代後半かな?隠岐の島で反乱があったのはしっちょるか?
その反乱は1年ほどで平定されたらしいんだけど、そのときの反乱を起こした側の一人が、この部落に逃れてきた。
島帰りってやつだな・・・
反乱の理由とかは学校で少し習ったろ?隠岐がすごい裕福な土地だったってこととかも。
まぁ、それはいいや。
で、その島帰りの人間、名前がな・・・◎○って言うんだよ」
(俺の苗字と同じでした。なんだか訳わかんね・・・)
◎○⇒以下AAとしますね。M「AAは反乱が平定されて、こっちに連れてこられた時に、隙を見て逃げ出してきたそうだ。
話によるとだけどな。この部落まで逃げてきたと。
部落の人らは、余計な厄介ごとを抱えると、さらに迫害を受けると思って、AAを殺そうとしたんだって。
で、AAが『命を助けてくれたら、お前たちに武器をやる』というようなことを言ったそうだ。
その武器って言うのがな、小箱だ。小箱の作り方。
部落の人はその武器がどのようなものかを聞き、相談した結果、条件を飲むことにしたんだ」322 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:11:25 ID:0GDcLRRy0
M「AAはもう一つ条件を出してきた。
武器(小箱)の作り方を教えるが、最初に作る箱は自分に譲って欲しいということ。
それが飲めるなら教える。どうしてもダメなら殺せと。
部落の人はそれを飲んだ。
そしてAAは、箱の作り方を教えた・・・
『作り方を聞いてからやめてもいい。そして殺してくれてもいい』とも、AAは言ったそうだよ。
それだけ禍々しいものだけん、この小箱ってのは。AAも思うところがあったのかもな。
ただ、『やり遂げたら自分も命を絶つが、それでもやらなければならないことがある』
そうAAは言ってたそうだ」323 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:11:38 ID:0GDcLRRy0
*箱の作り方、全部載せるとさすがにやばそうなので?いくつか省きますね。M「それでその方法がな、最初に、複雑に木の組み合わさった木箱をつくること。
これは、ちょっとやそっとじゃ木箱を開けられないようにするための細工らしい。
これが一番難しい作業らしい。お前らもちょっと見ただろ?あのパズルみたいな箱。アレを作るんだ。次に、その木箱の中を、雌の畜生の血で満たして、1週間待つ。
そして、血が乾ききらないうちに蓋をする。次に、中身を作るんだが、これが子取り箱の由来だと思う。
想像通りだと思うが、間引いた子供の体の一部を入れるんだ。
生まれた直後の子は、臍の緒と人差し指の先。第一間接くらいまでの。そして、ハラワタから絞った血を。
7つまでの子は、人差し指の先と、その子のハラワタから絞った血を。
10までの子は、人差し指の先を。
そして蓋をする。閉じ込めた子供の数、歳の数で箱の名前が変わる。
一人でイッポウ、二人でニホウ、三人でサンポウ、四人でシッポウ、五人でゴホウ、六人でロッポウ、七人でチッポウ。
『それ以上は絶対にダメだ』と、AAは念を押したそうだ。そして、それぞれの箱に、目印として印をつける。
イッポウは△、ニホウは■といった具合に。
ただ、自分が持っていく箱のハッカイだけは、7つまでの子を八人をくれと。
そして、ハッカイとは別に、女1人と子供を1人くれと。
『ハッカイは、最初の1個以外は決して作るな』とも言ったそうだ」324 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:11:53 ID:0GDcLRRy0
M「普通、そんな話まで聞いて、実行なんか出来ないよな。
そんな胡散臭い人間の話。ましてや、そんな最悪の話。
いくら生活苦しくても、自分の子供を殺すのでさえ耐え切れない辛さなのに、さらに殺した子供の死体にそんな仕打ち・・・
でもな、ここの先祖はそれを飲んだんだ。やったんだよ。
どういった動機、心境だったのかは全部はわからないけど、それだけものすごい迫害だったんだろうね。
子供を犠牲にしても、武器を手にしないといけないほどに、すごい・・・そして、最初の小箱を作ったんだと。
各家、相談に相談を重ねて、どの子を殺すかっていう最悪の相談。
そして実行されたんだ。
そして・・・ハッカイが出来上がった。AAは、この箱がどれほどのもので、どういう効果なのかを説明した。要望にあった子供と女を使ってね。
その子供と女の名前は、□■と$*(伏せますね)。
そして、犠牲になった8人の子供の名前は _______(伏せますね)。
聞いたことあるろ?」
(俺らは知ってる名前です。でもいえません。ほんとにごめんなさい)325 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:13:00 ID:0GDcLRRy0
M「で、効果はAに言ってたようなものだ。女と子供を取り殺す。それも苦しみぬく形で。
何故か、徐々に内臓が千切れるんだ。触れるどころか周囲にいるだけでね。
そして、その効果を目の当たりにした住民は、続けて箱を作ることにした。
住民が自分たちのために最初に作った箱はチッポウだった。
俺が祓った奴だな。7人の子供の・・・箱・・・
わずか2週間足らずの間に、15人の子供と、女1人が殺されたんだよ。
今の時代じゃないだろ?・・・ひどいよな・・・そして、出来上がった箱を、△▼の庄屋に上納したんだ。
普通に。住民からの気持ち、誠意の印という名目で。
庄屋の家は・・・ひどい有様だったらしい。女子供が血反吐を吐いて、苦しみぬいて死んだそうだ」326 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:13:22 ID:0GDcLRRy0
M「そしてな、住民は△▼のお偉方達、△▼以外の周囲地域にも伝えたそうだ。
今後一切部落に関わらないこと。放って置いて欲しいこと。
今までの怨みを許すことは出来ないが、ほうっておいてくれれば何もしないということ。
守ってくれるのなら、△▼へ仕事に出ている部落の者も、今後△▼に行くこともしないということ。
そして、もしこのことに仕返しをすれば、この呪いを再び振りまくということ。
庄屋に送った箱は、直ちに部落に返すこと。
なぜ部落を放置するのか、その理由は広めないこと。ただ、放置することだけを徹底すること。
そして・・・この箱はこれからも作り続けること。
既に箱は7つ存在していること。7つあるっていうのは、これはハッタリだったんだろうなと思う。そう思いたい・・・
言い方は失礼なんだけど、
読み書きすら出来なかった当時の住民に、これだけのことが思いつくはずは無いと思うんだが・・・
AAの知恵だったんだろうか。△▼含め、周りの地域は全てこの条件を了承したらしい。
この事件は、その一時期は周辺に噂としてでも広まったのだろうかな、すぐさま部落への干渉が一切止んだそうだ」327 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:13:47 ID:0GDcLRRy0
M「で、この部落の大人たちは、それでも作り続けたんだよ。この箱をね。
すでにAAはどこかに行ってたらしいんだが、箱の管理の仕方を残していったそうだ。
女子供を絶対に近づけないこと。
必ず箱は暗く湿った場所に安置すること。
そして箱の中身は、年を経るごとに次第に弱くなっていくということ。
もし必要なくなった、もしくは手に余るようなら、○を祭る神社に処理を頼むこと。
寺ではダメ。必ず処分は○を祭る神社であること。
そして住民たちは、13年に渡って箱を作り続けたそうだ。
ただ、最初の箱以外は、どうしても間引きを行わなければならない時にだけ。
間引いた子の身体を作り置いておいた箱に入れた、ということらしい。
子供たちを殺すとき、大人たちは『△▼を怨め、△▼を憎め』というようなことを言いながら殺したらしい。
殺す罪悪感から少しでも逃れたいから、△▼に反らそうとしてたんだろうな。箱を作り続けて13年目、16個目の箱が出来上がっていた。
イッポウ6つ、ニホウ2つ、ゴホウ5つ、チッポウ3つ。
単純に計算しても、56人の子供・・・
作成に失敗した箱もあったという話だから、もっと多かったんだろうな」328 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:14:00 ID:0GDcLRRy0
M「そして、13年目に事件が起きた。
その時、全ての箱は1箇所に保管されてたんだが、監視を立ててね。そして事件が起きた。
11歳になる一人の男の子が、監視の目を盗んで箱を持ち出してしまった。
最悪なのが、それがチッポウだったってこと。
箱の強さは、イッポウ<ニホウというふうに、数が増えれば強くなる。
しかも、出来上がって間もないチッポウ。
箱の外観は分かるよな・・・Sが楽しく遊んだっていうように、非常に子供の興味を引くであろう作りだ。
面白そうなおもちゃを手に入れた男の子は、家に持ち帰り、
その日のうちに、その子を含め家中の子供と女が死んだ。住民たちは初めて箱の恐怖を、この武器が油断すれば自分たちにも牙をむくということを改めて痛感した。
そして一度牙をむけば、止める間もなく望まぬ死人がでる。確実に。
そして恐怖に恐怖した住民は、箱を処分することを決めたそうだ」329 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:14:15 ID:0GDcLRRy0
M「それからは大体分かるよな。
代表者5人が、俺の家に来たんだわな。そして、俺の先祖に処理を頼んだ。
しかし、箱の力が強すぎると感じた俺の先祖は、箱の薄め方を提案したんだ。
それはJさんの言った通りの方法。
そして、決して約束の年数を経ない箱を持ち込まないこと。
神社側からは決して部落に接触しないこと。
前の管理者が死んだ後、必ず報告をすること。
箱ごとの年数は、恐らく俺の先祖が大方の目安・・・
箱の強さによって110年とか、チッポウなら140年ほど。
箱の管理から逃げ出せないよう、そのルールを作ったんだ。で、班毎に分かれたあと、一人の代表者を決め、各班にその代表者が届けた。
そしてどの箱をどの班に届けたかを俺の神社に伝え、俺の祖先が控えた後・・・その人は殺される。
これで、どの箱をどの班がどれだけの年数保管するのかは分からない。
そして、班内以外の者同士が箱の話をするのを、タブーとしたそうだ。
なぜ全体で管理することにしなかったのかは、恐らくだが、これは俺のじいちゃんが言ってたんだが、
全体で責任を背負って責任が薄まるよりも、少ない人数で負担を大きくすることで、逃げられないようにしたんじゃないかな?で、約束の年数を保管した後、持ち込まれた箱を処理したと。
じいちゃんの運の悪いところは、約束の年数ってのが、
じいちゃんとおれのひいじいさんの代に、もろ重なってたってことだ。
箱ごとの約束の年数っていうのは、法則とかさっぱり不明で、
他の箱はじいさんの代で全部処分できたんだが、チッポウだけはやたら長くて、俺の代なんだよなぁ・・・
まだ先だと思って何もやってなかったけど、真面目にせにゃ・・・」330 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:15:10 ID:0GDcLRRy0
M「これで全部だ。箱に関すること。俺が知ってること。
そして、俺が祓ったチッポウは、最初に作られたチッポウだってこと」それと、Mはさっき電話で、
M「箱の年数は、どうやって決めたのかは分からない。
俺の先祖が、箱について何かしら知ってたのかも知れないし、
AAという人物からそういう話があったら、そうしてくれと頼まれていたのかもしれない」
と言ってました。以上が昨日の夜の出来事です。
もうね、三文小説のネタにでもなりそうなお話で、
現実に箱事件を目の当たりにした俺も、何がなにやらで混乱してます。331 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:15:22 ID:0GDcLRRy0
これ、ホントは掲載するのどうしようか、本気で迷いました。
明らかにタブーなことだろうと思うし、部落の人にとっては絶対外に漏れては困ることでしょうし・・・
ただ、箱は残りふたつってMが言ってました。チッポウが2。
これは責任持ってMが処理するって言ってたのと、
俺ら4人、話を聞いても謎な部分が多すぎて、皆さんの力を借りたいって思ったから掲載することにしたんです。
冒頭で言ってた『お願いしたいこと』って言うのがそれなんです。
この話読んだ後、なにかこれに関する情報があったら教えていただけませんか?
詳しい地域とか明かせないし、みんなの名前も怖いから教えられないんですが、俺達の個人的な欲で知りたいんです。Mの話を聞いても、MとMのとおちゃんにも不明なことは多いらしく、
また、Sとその家族、Kも出来うる限り知りたいと。
Mも「今の時代なら分からない部分が少しは埋まるかも」と。
オカルトチックな話で、信憑性もかな~~~り薄いことだろうと思います。
俺も箱を実際見とらんかったら信じてないと思うしw332 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:15:40 ID:0GDcLRRy0
AAが誰なのか、もともとは何処から来たのか?
AAは箱の作り方を何処から知ったのか?
また、AAなる人物はどういう理由で隠岐に居たのかとか、
ハッカイとかいう最初の箱はドコに行ったの?とか、
AAはその後どうなったの?とか、
ハッカイ使ってAAは何をしたの?とか、
隠岐は、京都付近の政治犯が送られて来たってのは習ったんでしってますが、
この箱の作り方が、京周辺にあるものなのか?とか。これは俺のルーツ知れるかなぁっていう、個人的な欲も含まれています。
父母が生きてた時、父方の先祖は隠岐から来たってのは聞いてたんですが、
詳しいところは不明なんで、俺がAAと関わりあるのかは不明なんです。
妹どもももちろん知ってるわけないし、母方のばあちゃんに聞いてもわかるわけねぇし・・・歴史に詳しい方、ハッカイとか言う言葉が出てくる郷土史、昔話など、情報でてこないですかね?
333 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:15:56 ID:0GDcLRRy0
箱の呼び名の由来も不明ですし。
ただ、俺の想像なんですが、
イッポウ、ニホウとかは、『一封』、『二封』~~で、
ハッカイって言うのは、『八開』なのかなとも。俺らの名前、特に俺自身の苗字を明かせない、地域の名前とか肝心な部分を伏せてるとか、
こんな状態でお願いするのはお願いになってないし、失礼だとは思いますが、何か情報があったらぜひお願いします。
俺自身も図書館等で郷土史など調べてみるつもりです。
何か分かったらまたここに書き込むつもりです。
よろしくお願いします。334 :小箱 ◆/7qG64DDfc:2005/06/08(水) 22:16:28 ID:0GDcLRRy0
それと最後に。
最後のMの話なんですが、俺自身の思うところや感想を、
Mの言葉を借りて、勝手に盛り込んでる文章になってるかもしれません。
Mは「こんなかっこつけぇな話し方しねぇよ!」って言ってましたしw
ただ、それほど強烈に心に食い込む話だったんです。
何も思わず何も語らずってこと、俺には出来ないです。
でしゃばりかもしれませんが、お許しください。『2重カキコですか?』『連続投稿ですか?』って怒られるほどの長文ですが、
目を通していただけたこと、お礼を申し上げます。
📚出典と派生・類似伝承
◆出典:『洒落怖』に投稿された怪談
「コトリバコ」は、もともと2ちゃんねるのオカルト板内に存在する人気スレッド『死ぬほど洒落にならない怖い話(通称:洒落怖)』に投稿された創作怪談である。投稿者のハンドルネームは「師匠シリーズ」で知られる「夏目悠玄(仮)」とする説もあるが、実際には明確な作者が不詳であることが、逆にその“真実味”を高めている。
2000年代半ばにネット上で爆発的に話題となり、いわゆる「ネット怪談黄金期」の象徴的存在とされた。多くのまとめサイトやホラー検証ブログに転載され、現在ではYouTubeなどで朗読動画としても多数アップされている。
◆派生作品と二次創作の広がり
「コトリバコ」はネット発の怪談としては珍しく、以下のような豊富な二次創作が存在する:
- YouTube怪談朗読:複数の朗読者による音声化により、さらに広い層に伝播。特に「雨穴」や「ゾゾゾ」など、実地検証型YouTuberによる“現地探索動画”風演出も注目された。
- 漫画化:一部のWeb漫画サイトや個人作家によって、コトリバコを題材とした漫画やホラー短編が制作されている。
- 小説・ノベライズ風二次創作:匿名掲示板やPixivにおいて、オリジナル設定を追加した再構築型のストーリーがいくつも投稿されている。
◆類似・関連する伝承やモチーフ
「コトリバコ」は創作である一方、いくつかの民間伝承や呪術信仰と構造的に類似している。以下はその代表例である。
🧳1. 「玉手箱」型禁忌モチーフ
- 概要:決して開けてはならない箱を開けたことにより、災厄が降りかかるという禁忌テーマ。古くは浦島太郎の玉手箱が該当。
- 関連性:「箱を開けたことで呪いが発動する」点が共通しており、禁忌の境界を越えることのリスクが語られる。
🪦2. 丑の刻参り/呪詛箱伝承
- 概要:人形や遺体の一部、呪物などを箱に封じ、対象者に呪いをかける民間呪術。古くは「藁人形」「口寄せ箱」などが存在。
- 関連性:女性や子供の体の一部を使って“封印”されていたとされるコトリバコの描写と非常に近い。
🧙♀️3. 山の神・女神信仰と血忌
- 概要:山の神は女性であり、女性の血(特に生理)はタブーとされるという信仰。血が「穢れ」とされる文化背景があり、それを用いた呪物は“最も強い”と信じられていた。
- 関連性:コトリバコが「女性の血を用いた呪具」である点と重なる。
🧳4. 部落差別・民間呪術との関係
- 概要:被差別部落の住民が生業の一環として呪術を扱っていたという民間伝承が、実在の差別構造と絡めて語られることがある。
- 関連性:コトリバコには「ある集落」が他地域の人々に“復讐の手段”として使用したという暗示があり、社会的迫害と呪術が交差する典型例といえる。
🎬メディア登場・現代への影響
「コトリバコ」は、その独特の設定と恐怖感から、様々なメディアで取り上げられている。YouTubeでは朗読や考察動画が多数公開されており、また、小説や漫画などの創作作品にも影響を与えている。さらに、都市伝説やオカルトをテーマとしたテレビ番組や書籍でも取り上げられることがある。
🔍考察と文化的背景
「コトリバコ」は、日本の民間信仰や差別問題、そして呪術的な道具の伝承が複雑に絡み合った都市伝説である。
差別と呪いの構造
この物語の根底にあるのは、被差別部落の出自を持つ人々に対する歴史的な偏見と迫害である。伝説の中では、彼らがその恨みや悲しみ、そして怒りを“呪術”というかたちで具現化し、支配階級や村の有力者へ復讐するために「呪具=コトリバコ」を生み出したとされる。
この“女性と子どもを狙う”という性質は、命を繋ぐ存在(次世代)を断ち切るという強い意思の表れであり、単なる恨みではなく「血統そのものを断つ」呪いであると考察できる。日本の呪術では、「血」を媒介とした呪いは特に強力とされ、実際に“生理中の血”などが用いられる記述も都市伝説内に登場する。
「呪具」としての文化的意味
日本には古来から、呪具(じゅぐ)やまじない道具を使った伝承が数多く存在する。藁人形、丑の刻参り、封じ箱などが代表的で、コトリバコもまたその一系譜に連なる存在といえる。特に「箱」という閉じた空間に呪詛を込める行為は、「封印」「継承」「伝播」の三要素を備えており、物語の構造とも深く結びついている。
また、「コトリバコ」という名称そのものも謎めいており、「小鳥箱(こども=小さき命)を狙う箱」という語呂合わせ的な意味合いや、「異物を“言葉(コト)”として閉じ込めた箱」という解釈もある。
インターネット時代と“現代の呪術”
この都市伝説が注目を浴びた背景には、インターネット掲示板(特に2ちゃんねるなど)での拡散がある。実在の民俗資料ではなく、物語形式で“実録調”に投稿された点が、現代における「ネット民俗学」「デジタル・フォークロア」の事例として重要である。
その構造はまさに“現代の口承文化”であり、ユーザー間で補完・拡張されていくことで、コトリバコの物語は一種の“共有された幻想”として定着していった。
🗺️出現地点
物語の舞台は明確にはされていないが、島根県の隠岐諸島や石見地方がモデルとされている。特に、石見銀山やその周辺の歴史的背景が物語に影響を与えていると考えられている。また、千人壺と呼ばれる場所や、物部氏に関連する伝承も物語の要素として取り入れられている。
📎関連リンク・参考資料
💬編集者コメント・考察
「コトリバコ」は、現代日本の都市伝説の中でも特に完成度が高く、読者の想像力と恐怖心を同時に刺激する物語構造を持っている。ネット掲示板という匿名性の高いメディアで生まれたにもかかわらず、そこに描かれる“リアリティ”と“歴史的背景”は、一見して作り話とは思えない重厚さを持つ。
この話が人々に深く刺さる理由の一つは、「呪い」「封印」「因習」といった要素が、どれも日本人の文化的記憶に根差しているからである。たとえば“箱に閉じ込められたもの”というモチーフは、昔話『鶴の恩返し』や『玉手箱』など、開けてはいけない禁忌と密接に関係しており、誰もが無意識のうちに畏れを抱く対象となっている。
本作は、単なるホラーにとどまらず、日本社会の暗部——すなわち被差別部落や地域間の階級構造といった、今もなお語りづらい問題を内包している。そのため、「コトリバコ」が単なる怪談としてではなく、どこか“本当にあったこと”のように読まれてしまうのは、ごく自然な反応だともいえる。
読者は恐怖に惹かれながらも、それと同時に「これは差別や迫害に加担してきた側が受ける“報い”ではないか」という、倫理的な問いにも晒される。つまり本作は、ただの“怖い話”ではなく、“怖いことの理由を考えさせられる話”なのだ。
科学が進歩し、迷信や霊的存在が信じられなくなった時代においても、「呪い」という概念はなおも人々の心を捉えて離さない。「信じる/信じない」という二元論を超えた、「怖いから触れたくない」「でも気になる」という矛盾した感情が、コトリバコのような都市伝説を強く生き延びさせている。
特に、女性や子供といった“守られるべき存在”が呪いの対象となることで、読者の恐怖はより身近なものへと昇華される。
「コトリバコ」は、ネット怪談というフォーマットの中で、文化・社会・人間心理のすべてが絶妙に交差した傑作といえるだろう。その“作られた物語”としての巧妙さと、“実際にあるかもしれない”という曖昧な現実感が、日本都市伝説史においても特筆すべき存在である。
🎧 都市伝説好き必見!“聴く怖い話”体験を始めよう【Audible / audiobook.jp 比較】
👣 この記事を読んで、背筋がゾワッとしたあなたへ。
もし“読む”だけでなく、“耳で聴く”怪談体験に興味があるなら――
オーディオブックサービスの【Audible】と【audiobook.jp】が、あなたをさらなる恐怖の世界へ案内してくれる。
イヤホン越しに囁かれる怨念、静寂の中で始まる恐怖体験。
一度聴いたら眠れなくなるかもしれない、人気の怪談朗読が多数ラインナップされている。
- 🔊 Audible(オーディブル)
Amazon提供。毎月1冊無料で、声優や芸人による怪談朗読をフルで聴ける。
『新耳袋』シリーズや、怪談師・ありがとうぁみ氏の朗読なども人気。
- 📚 audiobook.jp
日本発のオーディオブックサービス。月額で怪談やホラー作品が聴き放題。深夜に“連続再生”でじっくり楽しめる。
- 🎁 どちらも無料体験が可能。
まずは1本、深夜にイヤホンで試してみてほしい。文字では味わえない恐怖が、あなたの耳に忍び寄りよる。
🔥 話題の2大オーディオブックで聴ける《怪談・怖い話》作品
- 🔊 Audible(オーディブル):Amazon提供、1冊まるごと“無料”で試せる。プロ声優や芸能人による本格怪談朗読が魅力。
- 📚 audiobook.jp:月額プランで怪談やホラー作品が聴き放題。深夜にじっくり聴く“連続再生”が人気。
| タイトル | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 👻 新耳袋シリーズ | ✅ | ✅ |
| 🧟♂️ 稲川淳二 怪談ナイト | ✅ | ✅ |
| 🏚 事故物件怪談 恐音 | ✅ | ✅ |
| 🏞 廃墟・廃線にまつわる話 | ✅(一部) | ✅(一部) |
| 😨 実話怪談集 | 豊富 | 豊富 |
👇こんな人におすすめ!
- ✅ Audibleは…月1冊じっくり聴きたい人向け
- ✅ audiobook.jpは…いろんな怪談を聴き放題で楽しみたい人向け
🎧 どっちがいい?かんたん比較表
| 比較項目 | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 月額 | ¥1,500(1冊無料+聴き放題対象多数) | ¥1,330〜(聴き放題プラン) |
| 無料体験 | 30日間 | 14日間 |
| 怖い話の充実度 | ◎(稲川淳二/新耳袋ほか) | ◎(人気作+独自配信もあり) |
| アプリ使いやすさ | ○ | ◎(日本語対応に強い) |
| 配信ジャンル | 海外含め多彩 | 国内作品に強い |
🧟♂️ 聴くだけで“現地にいるような”恐怖体験
あなたは、ひとりでこの朗読を最後まで聴ける自信はあるだろうか?
「イヤホン越しに耳元で囁くような声がして、思わず音量を下げた…」
そんなレビューも少なくない、リアルな恐怖がここにある。
- ✅ 急に部屋が寒くなった気がする
- ✅ 背後に気配を感じた
- ✅ イヤホン越しに“もう一人”の声が聞こえる…
そんな体験を、ぜひ以下のリンクから始めてほしい。
🔽 無料で怪談体験を始めるならこちらから
👇どちらも無料で今すぐ試せるので、気になる作品を1本、まずは深夜に“イヤホンで”聴いてみてほしい――恐怖の臨場感がまるで違う。
\ 30日間無料体験キャンペーン実施中/
※Audibleは無料期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
\ 14日間無料体験キャンペーン実施中/
※audiobookは無料聴き放題プランの期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
👇こちらの記事も要チェック!
【もっと読む】↓