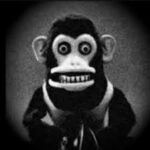🧠お下がりとは?
「お下がり」とは、掲示板サイト2ちゃんねる(現・5ちゃんねる)発の有名な短編怪談である。2008年11月、「死ぬ程洒落にならない怖い話を集めてみない?」というスレッド(通称「洒落怖」)に投稿された実話風の体験談で、身の回りの“もらいもの”に潜む得体の知れない恐怖を描いている。
物語の主人公は貧しい家庭に育ち、衣服から学習机、スポーツ用品、ゲーム機に至るまで、すべて“お下がり”で育つ。しかし、もらった学習机の下から現れる謎の男の子をきっかけに、周囲の死者の形見を次々と受け取っていることに気づき、次第に不吉な連鎖と「見てはならないもの」の存在に追い詰められていく。
この話は一見、心温まるような友情や励ましを装って進行するが、ラストでは全てが一転する。「励まし」ではなく「警告」だったと判明するラストが秀逸であり、読後に強烈な余韻を残す。
📖お下がりあらすじ
語り手は幼い頃、非常に貧しい家庭で育ちました。服や勉強道具もすべて「お下がり」で、当たり前のように使っていたが、ひとつだけ気になる品があった。それは、まだ新品同然の光沢を持つ学習机である。
ある日、その机で本を読んでいると、足元に冷たい何かが触れた。気にせず蹴り込むと「ぐにゃっ」とした異様な感触があり、恐る恐る足の感触で確かめていくと、最後に「細い糸のようなもの」に触れる。覗き込むと、そこには青白い顔の男の子がうずくまっていた。
恐怖で逃げ出した語り手だが、家族に信じてもらえず、机はそのまま使い続けることになる。やがて母親に尋ねると、その机は、入学直前に川で亡くなった近所のワタルくんのものだったと判明する。語り手は「ワタルくんが応援してくれている」と思い込むことで恐怖を乗り越え、勉強に励む。
その後も、野球道具やゲーム機などを父親から“お下がり”でもらうたびに、地元の子供の死亡記事が重なるという偶然が続く。語り手は、徐々にその“偶然”が単なる偶然ではないと気付き始める。
物語は最後、勉強中にまた足元に何かが触れ、語り手がそれを「応援」ではなく、「必死に訴えている」と悟る場面で終わる。彼はもう、机の下を覗くことができなくなっていた。
647 :本当にあった怖い名無し:2008/11/08(土) 22:15:22 ID:piTGUbKC0
俺のうちは昔超貧乏で、欲しいものなんか何一つ買ってもらえなかった。
着てる服は近所の子供のお下がりだったし、おやつは氷砂糖だけだった。
そんな俺でも、義務教育だけはちゃんと受けさせてもらっていた。
ただし、勉強道具はすべてお下がりだった。
生まれてからずっとお下がりばかりだったから、別になにも不満はなかったんだけど、ひとつだけ嫌なことがあった。
それは、お下がりでもらった学習机だった。
その学習机はお下がりなのにまだ新品の光沢を保っていて、ひきだしをあけると木材のかぐわしい香りが楽しめた。
俺はその学習机をひどく気に入って、暇な時間は柄にもなく机の上で本なんかを読んでみたりした。学習机がきて一週間くらい経った頃、妙な体験をした。
いつものように椅子に腰掛けて机の上で本を読んでいると、右足にひんやりとしたものが触れた。
本を読んでいる最中だったので、足に触れたもののことなど気にしなかった。
足をひんやりとしたものに当たらないように少しずらす。
しばらくすると、またひんやりしたものが足に触れた。
気持ち悪かったので、右足でひんやりとしたものを奥に蹴り込んだ。
すると、足の先にぐにゃっとした変な感触があった。
視線は机上の本にありながら、意識は机下の足先に集中した。
俺は右足をそっと動かしながら、そのぐにゃっとしたものの表面を確かめた。
ぐにゃっとしたものは凹凸があり、所々に穴があいていた。
やわらかいかと思うとかたい所もあったりして、何なのかさっぱりわからない。
足先はなめるようにぐにゃっとしたもの表面に触れていき、最後に上部に達した。
そこで細い糸のようなものが沢山ある感覚を感じた瞬間、自分の足が触れているものが何かわかった。
俺はそっと体を曲げて机の下を覗いた。
そこには青白い男の子がいた。俺の足先は男の子の頭に触れていたんだ。
俺はびっくりして椅子ごと背後に倒れた。
でも、顔は常に机の下の男の子を向いていた。
男の子も微動だにせず俺を見ていた。648 :本当にあった怖い名無し:2008/11/08(土) 22:16:11 ID:piTGUbKC0
立ち上がることもできず、ハイハイ歩きで部屋を出た。
すぐにオヤジの所にいき、体験したことを泣きながら話した。
でも、オヤジは全然信用してくれなかった。
もし信用してくれたとしても、うちには新しい机を買うお金なんてないので、買い換えることはできない。
結局俺は、小学校時代ずっとその机を使い続けた。
机で勉強していると足にひんやりとしたものが触れることが度々あったけど、机下を覗かないようにした。
またあの男の子がいたら怖いからだ。
いるのは確実なんだけど、見ないことでやり過ごそうとした。中学になって、それとなく母ちゃんに聞いてみた。
俺の使っている机は誰からもらってきたのかと。
すると母ちゃんは少し困ったような顔をしてから、「あの机は、近所のワタルくんの家からもらってきたんだよ」と教えてくれた。
ワタル君は俺と同い年で、幼稚園が一緒だった。
小学校に入学する数日前に、ワタルくんは川に落ちて死んだ。
頭がよかったワタルくんは、入学する前から勉強を始めていたらしい。
俺が使っている机で勉強しながら、これから始まる学園生活にワクワクしていたんじゃないだろうか。
事情を知った俺は、机下にいるワタルくんのことを怖がらなくなった。
ワタルくんのぶんまで勉強しようと思った。それからもワタルくんは俺の足に触れることがあった。
俺はワタルくんが足に触れるときは、勉強頑張れって励ましてくれていると考えた。
ワタルくんの励ましが支えになって、俺は結構勉強ができるようになった。649 :本当にあった怖い名無し:2008/11/08(土) 22:17:17 ID:piTGUbKC0
少しして中学校で野球がはやった。
俺も参加したかったんだけど、バットやグローブを買うお金がなくて困った。
俺はいつものようにオヤジを頼った。
するとオヤジは、「ちょっとまってろ」と言った。
数ヵ月後、オヤジはバットとグローブを俺にくれた。
またしてもお下がりだったけど気にしなかった。これで野球ができる。
俺は野球のメンバーに混ぜてもらい、思う存分楽しんだ。だけどある日、友達の一人が俺のグローブを見て言った。
「それ、ヨシロウのグローブじゃねぇか」
ヨシロウというのは、中学で野球部に所属していた同級生だ。
野球の才能があって、中一の頃からレギュラー入りを果たしていた。
だけどヨシロウは、つい最近死んだのだ。
帰宅途中に川に落ちて溺れてしまったらしい。
自分が使っていたグローブがヨシロウの物だったことを知り、俺は思った。
ヨシロウのぶんまで野球を楽しんでやろうと。
そのとき、ふと思った。
ヨシロウとワタルくんって、何か似てるなぁと。
二人はどちらも若くして亡くなっており、死因も死んだ場所も同じだ。
そして二人の形見を俺がもらっている。
こんな偶然ってあるのだろうか?数ヵ月後、再び俺はオヤジに頼みごとをした。今度はテレビゲームが欲しいと。
するとオヤジは、いつものように「ちょっと待ってろ」といった。
二週間後、オヤジはテレビゲームをくれた。
またしてもお下がりだった。
オヤジからテレビゲームをもらうちょっと前に、新聞に載っていた記事を思い出した。
近くの川で近所の中学生が溺れて死んだらしい。
体全体に寒気が走った。その日の夜、いつものように自室で勉強をしていると、足先に何かが触れた。
何年もの間、その何かを、死んだワタルくんが俺を励ましているものだと思っていた。
本当は違ったんだ。その何かは、必死に訴えかけていたのだ。俺は今も、机下を覗くことができないでいる。
📚出典と派生・類似伝承
出典元
掲載:2ちゃんねる「死ぬ程洒落にならない怖い話を集めてみない?」スレ
類似の怪談や都市伝説
- 「学校の怪談」シリーズ:物に宿る霊や念が引き起こす怪異として類似テーマが多く登場。
- 「呪いのアイテム」系統:日本の怪談において“形見”や“中古品”に霊が宿るモチーフは定番。
- 『着物を着た少女』:中古の和服に取り憑いた霊が少女に憑依するという話も構造が類似。
- 「事故物件」や「事故物リサイクル」の現代社会的文脈にも通じる。
🎬メディア登場・現代への影響
「お下がり」はその完成度の高さから、以下のような形で様々なメディアで紹介されている。
漫画やホラーゲームに影響を与えたとされる作品もあり、特に“物に宿る怨念”を主題とするストーリーにその痕跡が見える。
- YouTube朗読系ホラー動画:
多くの怪談系YouTuberが「名作」「心霊の王道」として朗読。
キーワード:#お下がり #洒落怖 #2ch怪談 - 書籍化・電子書籍:
一部の2ch怪談まとめ書籍や同人誌にも収録されている例がある。
例:『2ちゃんねるの怖い話大全』『洒落怖・極』 - 創作のインスピレーション元:
漫画やホラーゲームに影響を与えたとされる作品もあり、特に“物に宿る怨念”を主題とするストーリーにその痕跡が見える。
🔍考察と文化的背景
「お下がり」は、経済的貧困と呪物信仰、そして死者とのつながりという日本的なテーマを交差させている。
ホラーと温情のねじれ
怪異が“励まし”と誤認されていたというどんでん返しが、話に深い人間ドラマを与えている。ワタルくんの幽霊が恐怖ではなく支えだったという錯覚こそが、本作最大の皮肉であり恐怖でもある。
お下がり文化の影
戦後日本や経済的に苦しい家庭においては、衣類や学用品の「お下がり」は日常的だった。この文化的現象が、死者の思念が“物”に宿るという日本独自のアニミズム(精霊信仰)と融合して、恐怖を生む下地となっている。
死者の「念」と形見
主人公が受け取る物品はすべて“若くして亡くなった子ども”の形見であり、そこに未練や執着が強く残っていると解釈できる。
🗺️出現地点
物語の舞台となっているのは具体的な地名は明記されていないが、「川」が繰り返し登場する。
- 共通点としての「川」
ワタルくん、ヨシロウ、そして最後の少年も、全員が川で溺死している。
川は「現世と彼岸を分かつ境界」として、古来より日本の怪談において霊的な意味を持つ場所である。
典型例:「三途の川」「河童」「水難事故の怪談」 - 郊外の貧困層地域の描写も匂わせており、社会的格差が怪談と結びつくポイントでもある。
📎関連リンク・参考資料
💬編集者コメント・考察
「お下がり」は、怪談としての完成度が極めて高い名作である。
語り口は素朴で、子どもらしい純粋さがにじむ一方で、物語の構造は二重三重の伏線で緻密に作られている。読者は主人公と同様に、「ワタルくんは励ましてくれている」と思い込んで安心した瞬間に、背後から真の恐怖を突きつけられるのだ。
また、単なる幽霊話ではなく、「貧困が生み出す依存と業」「死者と生者の境界」「親の闇」など、深い社会的テーマも内包している。
「もらいものには魂が宿る」という日本的な価値観をここまで鮮やかにホラーに昇華させた作品は稀であり、現代の怪談として語り継ぐに相応しい傑作だ。
🎧 都市伝説好き必見!“聴く怖い話”体験を始めよう【Audible / audiobook.jp 比較】
👣 この記事を読んで、背筋がゾワッとしたあなたへ。
もし“読む”だけでなく、“耳で聴く”怪談体験に興味があるなら――
オーディオブックサービスの【Audible】と【audiobook.jp】が、あなたをさらなる恐怖の世界へ案内してくれる。
イヤホン越しに囁かれる怨念、静寂の中で始まる恐怖体験。
一度聴いたら眠れなくなるかもしれない、人気の怪談朗読が多数ラインナップされている。
- 🔊 Audible(オーディブル)
Amazon提供。毎月1冊無料で、声優や芸人による怪談朗読をフルで聴ける。
『新耳袋』シリーズや、怪談師・ありがとうぁみ氏の朗読なども人気。
- 📚 audiobook.jp
日本発のオーディオブックサービス。月額で怪談やホラー作品が聴き放題。深夜に“連続再生”でじっくり楽しめる。
- 🎁 どちらも無料体験が可能。
まずは1本、深夜にイヤホンで試してみてほしい。文字では味わえない恐怖が、あなたの耳に忍び寄りよる。
🔥 話題の2大オーディオブックで聴ける《怪談・怖い話》作品
- 🔊 Audible(オーディブル):Amazon提供、1冊まるごと“無料”で試せる。プロ声優や芸能人による本格怪談朗読が魅力。
- 📚 audiobook.jp:月額プランで怪談やホラー作品が聴き放題。深夜にじっくり聴く“連続再生”が人気。
| タイトル | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 👻 新耳袋シリーズ | ✅ | ✅ |
| 🧟♂️ 稲川淳二 怪談ナイト | ✅ | ✅ |
| 🏚 事故物件怪談 恐音 | ✅ | ✅ |
| 🏞 廃墟・廃線にまつわる話 | ✅(一部) | ✅(一部) |
| 😨 実話怪談集 | 豊富 | 豊富 |
👇こんな人におすすめ!
- ✅ Audibleは…月1冊じっくり聴きたい人向け
- ✅ audiobook.jpは…いろんな怪談を聴き放題で楽しみたい人向け
🎧 どっちがいい?かんたん比較表
| 比較項目 | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 月額 | ¥1,500(1冊無料+聴き放題対象多数) | ¥1,330〜(聴き放題プラン) |
| 無料体験 | 30日間 | 14日間 |
| 怖い話の充実度 | ◎(稲川淳二/新耳袋ほか) | ◎(人気作+独自配信もあり) |
| アプリ使いやすさ | ○ | ◎(日本語対応に強い) |
| 配信ジャンル | 海外含め多彩 | 国内作品に強い |
🧟♂️ 聴くだけで“現地にいるような”恐怖体験
あなたは、ひとりでこの朗読を最後まで聴ける自信はあるだろうか?
「イヤホン越しに耳元で囁くような声がして、思わず音量を下げた…」
そんなレビューも少なくない、リアルな恐怖がここにある。
- ✅ 急に部屋が寒くなった気がする
- ✅ 背後に気配を感じた
- ✅ イヤホン越しに“もう一人”の声が聞こえる…
そんな体験を、ぜひ以下のリンクから始めてほしい。
🔽 無料で怪談体験を始めるならこちらから
👇どちらも無料で今すぐ試せるので、気になる作品を1本、まずは深夜に“イヤホンで”聴いてみてほしい――恐怖の臨場感がまるで違う。
\ 30日間無料体験キャンペーン実施中/
※Audibleは無料期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
\ 14日間無料体験キャンペーン実施中/
※audiobookは無料聴き放題プランの期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
👇こちらの記事も要チェック!
【もっと読む】↓