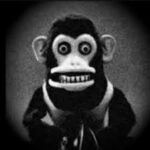🧠エリーゼのためにとは?
「エリーゼのために」とは、日本のネット掲示板「2ちゃんねる」発祥の怪談のひとつである。主に医療従事者を中心に語られる“病院怪談”の代表格として知られ、幽霊、死者との交信、電子機器の異常など、現代ホラーの定番要素をすべて備えている。
この話の核心は、亡くなった患者が安置された隔離室から繰り返しナースコールが鳴り響くという現象だ。しかもそのナースコール音は、誰もが知るクラシック曲「エリーゼのために」である。蘇生失敗、遺族との断絶、冷たい現実——そのすべての背景に不気味な旋律が絡むことにより、静かな恐怖をより一層強調している。
📖 エリーゼのためにあらすじ
語り手は研修医。
4月、研修が始まったばかりのある夜、酔っ払いの救急搬送で忙しくしていた中、心肺停止の若い女性患者が搬送される。
懸命な蘇生もむなしく、死亡が確認される。
この女性は過去に何度も自殺未遂を繰り返していた人物で、家族や知人からも見放されていた。
遺体は検視のため朝まで病院に留め置かれ、「隔離室(本来はインフルエンザ患者などを一時的に隔離する病室)」に安置される。
その部屋は奥まっており、鍵をかけて完全に施錠された状態だった。
深夜1時半ごろ、突然ナースコールが鳴る。
そのメロディは「エリーゼのために」。
確認すると、鳴っていたのは遺体を安置した隔離室から。
しかしその部屋は完全に施錠されていて、鍵は上級医が持ったまま。
もちろん、中に誰かがいるはずはない。
上級医は冷静に「故障だ」「考えるな」と言いながらナースコールを切るが、
その後も何度も、何度も、「エリーゼのために」が病棟中に鳴り響く。
最後には、メロディがどんどん歪んでいき、「ミレミシミレミシミレミレミレ…」と壊れたように鳴り続ける……。
268 :1/6:2009/12/15(火) 22:15:46 ID:1fSqPHYk0
病院にまつわる幽霊系の話はよく聞きますが、自分では1つしか体験したことがありません。
というわけで、その唯一を…。これも研修医時代、しかも働き始めの4月です。(日付まで覚えています)
おりしも世間はお花見+新歓シーズン真っただ中。
浮かれすぎてべろんべろんになって、救急車でご来院いただく酔っ払いで、深夜も大忙しでした。ちなみに、ある意味洒落にならないことに、前後不覚の酔っ払いは研修医のいい練習台です。
普段めったに使わない太い針で、点滴の練習をさせられたりしました。
一応治療上、太い針で点滴をとって急速輸液ってのは、医学上正しいのも事実ですよ?
でも、血行がよくて血管がとりやすく、失敗しても怒られず、しかも大半は健康な成人男性というわけで、
上の先生にいやおうなしに一番太い針を渡され、何回も何回もやり直しをさせられながら、
半泣きでブスブスやってました。
普通の22G針は、研修医同士で何回か練習すればすぐ入れれるのですが、
16Gという輸血の為の針になるとなかなかコツがつかめず、入れられる方も激痛…
でも練習しておかないと、出血で血管のへしゃげた交通事故の被害者なんかには絶対入らないわけで。
(皆様、特に春は飲みすぎには注意ですよ!)269 :2/6:2009/12/15(火) 22:16:37 ID:1fSqPHYk0
話を戻します。
その日の深夜、心肺停止の患者が搬送されてきました。
まだ本当に若い方で、医者になりたての若造は使命感に燃え、教科書通りに必死に蘇生を行いました。
しかし結局30分経過したところで、ご家族と連絡をとった統括当直医の一言で全ては終了。
その方は、(自分は知りませんでしたが)今まで何回も自殺未遂で受診していた常連さん。
しかもいわゆる『引き際を抑えた見事な未遂』で、ギリギリ死なない程度でとどめていたようです。
しかし今回、運が悪かったというのか自業自得というのか…
だいぶ薬のせいで心臓が弱っていたらしく、(推測ですが)まさかの心停止。
駆けつけた知人という人も、固定電話から救急車は要請したものの、到着時にはその場におらず連絡不能。
状況から事件性が否定できないため、警察に連絡。
検視が行われることになりましたが、『たまたま大きな事件があったので朝まで引き取れない』とのこと。家族と連絡を取る時、やむを得ず故人の携帯を見て連絡をとりましたが、あっさり蘇生中止を希望。
『生前、家族全員をさんざん振り回し、借金を負わせ、みんなが疲れきって病んでしまった。
自殺が最後の希望だったろうから、頼むから逝かせてやってくれ』と…。
死亡確認後、改めて連絡しましたが、
地方に住んでいて、今晩は引き取りにも付添にもいけないとのことでした。
最後に携帯から電話をしていた(おそらく通報者でしょう)異性の知人にも連絡をとりましたが、
『今までまとわりつかれ、逃げようとすれば自殺未遂をされて疲れ切っていた。
家族でも友達でも何でもない。もう関わりたくない』
と泣き声で通話を切り、その後はつながらず…。暗澹とした気分になりました。最初の社会勉強でした。
271 :3/6:2009/12/15(火) 22:17:53 ID:1fSqPHYk0
結局「遺体をどうしようか」という話になり、もう一度話は警察へ。
誰かが面会に来た時にすぐ会えるようにという配慮から、『隔離室』に安置することとなりました。
この隔離室、少し説明しにくいのですが、救急の一番奥まったところにあります。
手前から診察スペース(ウォークインの診察室と救急車受け入れ)があり、処置のスペースがあります。
私たちはだいたい、この処置スペースと診察スペースを行き来しています。
さらに奥に経過観察用のベッドが10台あるのですが、そのさらに突き当りにあります。
カーテン付きのドアで仕切られていて、救急室のベッド側と廊下2か所から出入りできますが、
どちらも施錠できます。(以前知らない間にホームレスが入っていたりしたことがあったので…)
正しい使用方法はインフルエンザの患者の点滴などですが、今回はそこに入っていただこうというわけです。
空調も別になっているので、その部屋だけ最低温度に設定してクーラーをかけ、施錠しました。ショックを受けていた自分も、すぐにまた怒涛のように運び込まれる酔っ払いの相手をしているうちに、
その患者のことが頭から抜け落ちて行きました。
それがだいたい11時ごろ。
異変が起きたのは、深夜1時半ごろでした。272 :4/6:2009/12/15(火) 22:18:50 ID:1fSqPHYk0
観察用ベッドと隔離ベッドは、先ほども言ったように近いとはいえ少し離れているので、
各ベッドに一つずつナースコールがあり、鳴らすと『エリーゼのために』が流れます。
意外と音が大きく、救急全体で聞こえるので、
だいたい看護師さんが誰か手を止めて、ベッドのところに行ってくれます。
(しょうもない要件ばかり何回も言ってると、何もしないこともあるみたいですが)
しかし、悲しいことに看護師よりも研修医の方が立場が下で…あとは察してください。というわけでぱっと板を見に行くと、観察室のランプがチカチカ。
何も考えずにナースコールを取って、「どうしましたか?」と言った瞬間、
後ろからぱっと別のドクターが切ってしまいました。
(ちょうど壁についてる固定電話みたいになっています)
「え・・・」
「お前良く見ろ、隔離室だぞ」
「あっ・・・え、あのー、酔っ払いが忍び込んでる、とか?」
「鍵は俺がかけた」
そういってポケットから鍵を出す上級医。
「そして今も持ってる。あとは聞くな、考えるな。こういうことも、たまにある」
そして鍵を戻してぼそっと、
「ただの故障だ、厭な偶然、それだけだからな」もうそのあとは怖くてしかたありませんでした。
しかし自分がやらかしてしまったせいでしょうか、その後ベルが鳴る鳴る…。
ひっきりなしにエリーゼのためにがガンガン流れます。
そのたびにめんどくさそうに受話器をガチャギリする上級医。
しかしベルはひどくなる一方でした。273 :5/6:2009/12/15(火) 22:19:51 ID:1fSqPHYk0
♪ミレミシレドラ~…、のメロディーが流れるのですが、
途中くらいから、こちらが切らなくても勝手に途中で切れるのです。
ミレミシレドミレミシレド、みたいな感じで。
最後はミレミシミレミシミレミレミレ…みたいになってましたね。
明らかにこちらをせかしていました。
私と同じく入りたての看護師さんもいたのですが、彼女は完全に腰が抜けて泣きながら座り込んでいたし。
そして、「おい!うっせーんだよ!!さっさと行ってやれやゴルァ!!!!」と空気の読めない酔っ払い共。
中にはオラオラ言いながら隔離室のドアを蹴るDQNまでいて、ちょっとしたカオスでした。そんな中、一人不機嫌オーラを立てていたのは師長さんでした。
とうとうしびれを切らした彼女は、ツカツカと受話器のところに行ってさっと取ると一言、
「 黙 っ て さ っ さ と 死 ね ! ! ! ! ! 」274 :6/6:2009/12/15(火) 22:20:51 ID:1fSqPHYk0
救急中にしっかりと声が響き、ぱたりと途絶えたナースコール。
理解したのかしないのか知りませんが、空気をやっと読んでくれた酔っ払い達。
くるりと振り返った師長さんは、それはそれは、頼もしいとかじゃなくて純粋に恐ろしかったです。
「 仕 事 し ろ ! 」その後は馬車馬のように働きましたとも。
酔っ払いはいつも居座ってしまって返すのに苦労するのですが、皆様本当に理解が早かった。腰を抜かしていた看護師さんはその後、
「ICUで死ぬ間際の人が氷をポリポリ食べていて、その音が耳から離れない」
と言い残して辞めて行きましたが、師長さんいわく「軟弱もの」だからだそうです。女社会、子供を5人育て上げ、なおかつ893やDQNのやってくる救急外来をあえて選ぶ、そんな猛者。
今でも心底恐ろしいです。あと、心当たりがあっても、この話はあまり広げないでくださいね。
特定されたら…考えたくないですから。278 :本当にあった怖い名無し:2009/12/15(火) 23:07:23 ID:W3vfcLsc0
>>274
これ単に蘇生したとかいうことは、ないの?281 :本当にあった怖い名無し:2009/12/15(火) 23:44:00 ID:1fSqPHYk0
>>278
当時の自分もちょっと考えましたが、やはり何度考えても答えはNOでした。
挿管こそしませんでしたが、
三次救急病院の蘇生メニューで、全くのAsys.(心臓が完全に止まった状態)でしたからね…
特に低体温などの特殊な状況だったわけでもありませんし。
医学的常識を超えて蘇生してくるケースを全く否定するわけではありませんが、非常に考えにくいです。ちなみに、隔離室はかなり広めの個室です。
インフルエンザの時期、5組のインフルエンザの子供+保護者を収容できる広さです。
その中央に、柵付きのベッドを一台だけぽつんと置いた状態。
ナースコールは一台のみで壁に固定です。
生きている人を寝かせるときには、延長ケーブルでボタンを持たせますが、
当然当時は必要ないので、ケーブルは収納していました。
鍵はあくまで外からの侵入を防ぐためなので、中からはつまみ一つで簡単に開きます。
本当に生き返って、柵をはずして壁まで歩いてナースコールを鳴らすぐらい元気だったら、
せめてカーテンを開けて助けを呼ぶくらいしてほしかったかなあ。あと、救急外来のナースコールは電話と違い、かけることはできても切ることはできません。
こっちから切らない限り、新しくかけなおすことはできないはず。なので、もっとも科学的に説明がつくのは『故障』なんでしょうね。
なにはともあれ、自分には色々と洒落にならなかったです。
📚出典と派生・類似伝承
この怪談は、2009年12月に「死ぬ程洒落にならない怖い話を集めてみない?」スレッド(通称「洒落怖」)に投稿されたもので、この話には以下のような類似伝承や怪談が存在する:
- 「○○号室のナースコール」:病室のナースコールが誰もいないのに鳴るという病院怪談の定番。
- 「赤い部屋」:一見ただの都市伝説に見えるが、PCや機械を通じて“死”とリンクする点で共通する。
- 「くねくね」や「八尺様」のように、正体不明かつ説明されない“存在”が出現する点も共通。
また、“エリーゼのために”という曲自体がオカルティックに扱われる事例も少なくない。
🎬メディア登場・現代への影響
現時点で「エリーゼのために(洒落怖)」の直接的な映像化はされていないが、YouTube上では朗読・考察動画として多数紹介されている。
特に怪談朗読系チャンネルや「2ちゃんねるの怖い話」シリーズでは定番のネタであり、
「ナースコールが鳴る怖い話」として高再生数を誇る。
また、本作の要素は以下のようなホラー作品にも共鳴している:
『Another』…死者と生者の境界が曖昧な環境描写
映画『感染』(2004)…病院内での説明不能な異常現象
『リング』シリーズ…電話を通じて死が忍び寄る演出
🔍考察と文化的背景
この怪談がこれほどまでに恐怖を呼ぶ理由は、読者にとって「実際にありそう」と思わせるディテールにある。
ナースコール音として有名曲が使われる設定や、病院内の構造、上級医のリアクションなどが極めてリアルであり、読者に「これは本当にあった話なのでは?」という錯覚を与える。
また、日本における病院=死と隣り合わせの空間という文化的認識が背景にある。
死を迎えた者の“声”が機械を介して現れるという構造は、現代の霊的概念とテクノロジーの接点とも言えるだろう。
「エリーゼのために」は本来、軽快で明るいクラシック曲であるにも関わらず、この怪談によって不気味な旋律としてのイメージを持つ者も少なくない。
🗺️出現地点
この物語に登場する病院の詳細は明かされていないが、設定からして大都市圏にある研修医制度を持つ大病院と推測される。
隔離室の構造やナースコールの仕組みなど、医療関係者のリアリティある描写が物語を補強しており、看護・医療現場での実体験と錯覚する読者も多い。
📎関連リンク・参考資料
💬編集者コメント・考察
「エリーゼのために」は、“誰もが知る安心の旋律”が“死を告げる異常音”に変質することで、深い印象を与える怪談である。
機械が発する異常な信号、医療従事者のやり場のない恐怖、そして死者が最後に何かを伝えようとする姿は、単なるオカルト話以上の余韻を残す。
また、“死者に対する社会の冷淡さ”や“家族関係の断絶”といった現代的テーマも内包しており、読後の読者に心理的な問いを投げかける。
単に怖いだけでなく、「我々が死とどう向き合うか」という普遍的なテーマを突いているのだ。
🎧 都市伝説好き必見!“聴く怖い話”体験を始めよう【Audible / audiobook.jp 比較】
👣 この記事を読んで、背筋がゾワッとしたあなたへ。
もし“読む”だけでなく、“耳で聴く”怪談体験に興味があるなら――
オーディオブックサービスの【Audible】と【audiobook.jp】が、あなたをさらなる恐怖の世界へ案内してくれる。
イヤホン越しに囁かれる怨念、静寂の中で始まる恐怖体験。
一度聴いたら眠れなくなるかもしれない、人気の怪談朗読が多数ラインナップされている。
- 🔊 Audible(オーディブル)
Amazon提供。毎月1冊無料で、声優や芸人による怪談朗読をフルで聴ける。
『新耳袋』シリーズや、怪談師・ありがとうぁみ氏の朗読なども人気。
- 📚 audiobook.jp
日本発のオーディオブックサービス。月額で怪談やホラー作品が聴き放題。深夜に“連続再生”でじっくり楽しめる。
- 🎁 どちらも無料体験が可能。
まずは1本、深夜にイヤホンで試してみてほしい。文字では味わえない恐怖が、あなたの耳に忍び寄りよる。
🔥 話題の2大オーディオブックで聴ける《怪談・怖い話》作品
- 🔊 Audible(オーディブル):Amazon提供、1冊まるごと“無料”で試せる。プロ声優や芸能人による本格怪談朗読が魅力。
- 📚 audiobook.jp:月額プランで怪談やホラー作品が聴き放題。深夜にじっくり聴く“連続再生”が人気。
| タイトル | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 👻 新耳袋シリーズ | ✅ | ✅ |
| 🧟♂️ 稲川淳二 怪談ナイト | ✅ | ✅ |
| 🏚 事故物件怪談 恐音 | ✅ | ✅ |
| 🏞 廃墟・廃線にまつわる話 | ✅(一部) | ✅(一部) |
| 😨 実話怪談集 | 豊富 | 豊富 |
👇こんな人におすすめ!
- ✅ Audibleは…月1冊じっくり聴きたい人向け
- ✅ audiobook.jpは…いろんな怪談を聴き放題で楽しみたい人向け
🎧 どっちがいい?かんたん比較表
| 比較項目 | Audible | audiobook.jp |
|---|---|---|
| 月額 | ¥1,500(1冊無料+聴き放題対象多数) | ¥1,330〜(聴き放題プラン) |
| 無料体験 | 30日間 | 14日間 |
| 怖い話の充実度 | ◎(稲川淳二/新耳袋ほか) | ◎(人気作+独自配信もあり) |
| アプリ使いやすさ | ○ | ◎(日本語対応に強い) |
| 配信ジャンル | 海外含め多彩 | 国内作品に強い |
🧟♂️ 聴くだけで“現地にいるような”恐怖体験
あなたは、ひとりでこの朗読を最後まで聴ける自信はあるだろうか?
「イヤホン越しに耳元で囁くような声がして、思わず音量を下げた…」
そんなレビューも少なくない、リアルな恐怖がここにある。
- ✅ 急に部屋が寒くなった気がする
- ✅ 背後に気配を感じた
- ✅ イヤホン越しに“もう一人”の声が聞こえる…
そんな体験を、ぜひ以下のリンクから始めてほしい。
🔽 無料で怪談体験を始めるならこちらから
👇どちらも無料で今すぐ試せるので、気になる作品を1本、まずは深夜に“イヤホンで”聴いてみてほしい――恐怖の臨場感がまるで違う。
\ 30日間無料体験キャンペーン実施中/
※Audibleは無料期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
\ 14日間無料体験キャンペーン実施中/
※audiobookは無料聴き放題プランの期間が終了する前に解約することで一切料金は発生しません。
👇こちらの記事も要チェック!
【もっと読む】↓